125 PTA文化セミナー
附属中学校の保護者の皆様、こんにちは。
PTA文化部長の松本加奈と申します。
さて、6月4・5日にPTA文化部主催にて、PTA文化セミナーを開催しました。
本年度は「カラーサンドアートを描く ~色で遊ぶ、砂で魅せる。世界にひとつのアート体験」というテーマを掲げ、講師に坂本圭子先生をお迎えしました。
皆様、カラーサンドアートを体験したことはありますか?
カラーサンドアートとは、色のついた砂をガラスの器に重ねて模様をつくるアートです。
正解不正解のない、100人いたら100通りのものができる、世界にひとつだけのアート作品を作るのです!!!
見本はありますが、見本の通りにしようと思ってもできない・・・(近いものはできるかもしれません)、そして見本からアレンジすることもできる、はたまた、まったく自由な発想で、自由な組み合わせ、重ね方をしても、全部が全部、大正解なのです。
講師の坂本先生に砂の落とし方のレクチャーを受けた後、思い思いに積んでいかれる様子、その色の組み合わせに衝撃を受けました。
皆様が選んだ色の組み合わせ、「お、その色いくの!」と内心思いながら見ておりました。
ところが、カラーサンドを積み重ねていくにつれ、「そんな積み方、重ね方がありなの!」「この色の組み合わせ、かわいい!」「差し色がポップ!」
附中生の保護者の発想力はすごいのです。子供たちに負けていません。いや、アートは勝ち負けではありませんが。
沢山の方に教えていらっしゃる坂本先生も「このような色の組み合わせ、積み方があるのね!発想がとてもすばらしいです。」とおっしゃっておられました。
6月4日にご参加いただきました、小林教頭先生、河合先生、小野田PTA会長もオリジナルのとても素敵な作品を作っていらっしゃいました。
6月5日にご参加いただきました松岡副校長先生の作品は、きれいな青に差し色の黄色、海辺のさわやかな香りが漂ってきそうですね。
参加された皆様、思い思いのカラーサンドアートを楽しんでいただけましたか?
少しでも良い時間を過ごしていただくことができましたら、文化部一同大変うれしく思います。
文化セミナーまで様々なご準備をして頂き、また当日すばらしいご指導を頂きました坂本圭子先生、文化セミナー開催にあたり、ご協力を頂きました先生方、日々お忙しい中でいろいろなお願いごとを快諾して頂きました佐野先生、セミナーに参加して頂きました皆様、ご協力頂きましたすべての皆様に感謝申し上げます。
素敵な作品、ぜひお部屋のどこかに飾ってくださいね。
ありがとうございました。
PTA文化部長 松本加奈







124 PTA活動を楽しみましょう!
こんにちは。
令和7年度PTA副会長を務めさせていただきます犬塚嘉奈子と申します。
一年間どうぞよろしくお願いいたします。
新年度が始まり3学年とも宿泊行事を終え、本格的に1学期の追究学習などに取り組んでいることと思います。
私たちPTAも総会を終え、今年度の活動を開始しています。
今年度は多くのPTA活動が1学期に予定されており、去る5月12日(月)には教育文化講演会が開催されました。
※講演会の内容は小野田PTA会長からの報告(5月19日付ブログ)をご覧ください。
6月には文化セミナー・スポーツ懇親会の開催が予定されており、各部評議員の皆さんが精力的に準備を進めてくださっています。
ご参加のお申し込みをいただいた皆さま、当日を楽しみにしていてください。
また、今回は残念ながらご参加いただけなかった皆さま、今後も清掃等の奉仕活動「附中ファンミーティング」なども予定しておりますので、そちらの方でお会いできますことを楽しみにしています。
PTA活動は、保護者同士や先生方との交流を深める機会になり、学校というコミュニティをより豊かなものにしてくれる活動だと思います。
子ども達だけでなく、私達保護者も一緒に附中生活を楽しみましょう。
どうぞよろしくお願いいたします。
令和7年度 PTA副会長 犬塚嘉奈子
…………
【体育部】
今年度、体育部長および3年学年代表を務めさせていただくことになりました、作田陽子です。
これまで一緒に活動してきた前部長の想いを引き継ぎながら、「附属中学校のことがもっと好きになった」と皆さんに感じていただけるような活動を目指し、微力ながら精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
体育部では、5月15日(木)に第2回目の部会を行いました。
そしていよいよ、6月14日(土)に開催されるスポーツ懇親会に向けて、本格的に準備が始まっています。部会当日は、本番と同じく90分間を歩いて、フォトロゲイニングのポイント確認を行いました。
参加される皆さまにとって楽しい一日となるよう、部員一同、心を込めて準備を進めております。
参加申し込みは締め切りましたが、もしまだ迷っている方がいらっしゃいましたら、5月中であれば、お気軽に体育部の部員までお声がけください。
スポーツ懇親会を通して、学校のことをより深く知ったり、参加される保護者の皆さまや先生方とのつながりを感じられるような機会になればと思っています。
一年間、どうぞよろしくお願いいたします。
令和7年度 PTA体育部長 作田陽子

……………
【文化部】
今年度、文化部長を務めさせていただきます、松本加奈です。精一杯努めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。
文化部では、PTA会員の皆さま同士の親睦を深めることを目的に、楽しく参加できる企画を考えています。
今年度は「カラーサンドアート」の制作体験を6月4日(水)・5日(木)に開催予定です。
準備のため、5月21日に第2回文化部会を行い、楽しい企画に向けて、和やかな雰囲気で準備を進めました。色とりどりの砂を使って、世界に一つだけのアートを楽しみましょう!多くの皆さまのご参加をお待ちしています。
文化部一同、心をこめて準備を進めてまいります。
一年間、どうぞよろしくお願いいたします。
令和7年度PTA文化部長 松本加奈


123 【教育文化講演会】影山知明さん「ゆっくりいそげ」 ―― “自分の時間”を生きるということ
令和7年度 PTA教育文化講演会にて、「クルミドコーヒー」店主・影山知明さんをお招きし、「ゆっくりいそげ」というテーマでご講演いただきました。穏やかな語り口ながら、影山さんの一貫した確かな考えが、中学1年生から3年生、そして保護者にまで、わかりやすい言葉でまっすぐに届けられる、そんなひとときとなりました。
【笑いと安心が生まれる場面】
講演が始まってすぐ、「宿題やっていない人、いますか?」という影山さんの問いかけに、数人の生徒が正直に手を挙げると、会場には自然と笑い声が広がりました。影山さんは「そういうの、いいですね」と微笑み、場の空気がふっとやわらぎました。
その後、生徒から予想外のリクエスト――「ミッキーマウスの声マネをしてほしいです!」。影山さんは少し照れながらも「いつもはやらないんですけど……今日は特別」と、小さな声で披露。会場は笑いに包まれ、生徒、保護者、そして先生までもが一体となり、まるで大きなカフェのような温かな空間が広がっていきました。
【「ゆっくりと、いそげ」を行ったり来たりする】
「ゆっくりいそげ」という講演タイトルについて、影山さんは次のように語りました。
“いそぐ時期”と“ゆっくり進む時期”がある。それはどちらかに決めるものではなく、行ったり来たりすることでこそ、よい成長ができるのだと思います。
勝つためにやることもあれば、楽しむためにやることもある。どちらかに偏るのではなく、その間を揺れ動くことが自然な生き方なのだと語ります。目まぐるしく価値観が移ろい、常に結論を急かされるように感じていた私たちにとって、“ありのままでいい”“ゆっくりといそげがあるからこそ、揺らぎ、悩み、それが人を成長させる”という言葉は、悩むことを肯定してくれる、ある種の救いになったように感じられました。
【「自分の時間を生きる」ということ】
今回の講演で繰り返し語られていたのは、「自分の時間を生きる」という考え方でした。
影山さんはこう述べます。やらなければならないことの中にも、自分なりの意味を見出そうとする姿勢が大切。そして、それを自分で決められるかどうかが重要なんです。
将来の選択肢が広がっている現代においては、何を選ぶかよりも、「誰が選ぶのか」という主体性の方が、はるかに大切なのだというメッセージでした。
誰かに決めてもらうのではなく、自分で決める。それができるかどうかで、人生は大きく変わっていきます。
「いい大学」や「安定した職業」を目指す前に、自分の心が何を感じているのかに耳を傾けること――それが、進むべき道を選ぶ上での指針になるのだと、力強く伝わってきました。
【「それぞれの人が、それぞれの人らしい命を全うする」】
特に心に残ったのが、次の言葉でした。
“自分らしく”とは、自分にしかできない生き方をすること。それぞれの人が、それぞれの命を全うしていくことが、社会全体の豊かさにつながっていくのです。
誰かと同じである必要はない。それぞれが「自分だけの時間」「自分だけの人生」を生きることが、他者への尊重につながる。そして他者を尊重することは、同時に自分自身を大切にすることでもあるのだと、気づかされました。
【今後の夢は「独立国家をつくること」】
講演の終盤、子どもたちの鋭い質問を受けて、影山さんは今後の夢について語ってくださいました。それは「独立国家をつくること」。
もちろん、物理的な国家を建国するという話ではありません。自分たちの価値観やルールを持ち、自立して暮らしていけるような、小さな共同体をつくってみたい――という構想でした。
暮らしや仕事を自分たちで生み出し、経済や教育も含めてゆるやかに設計していく場所。そこには、“自分の時間を生きる人”たちが集まってくるのかもしれません。
人と人との関係性を暮らしのなかで丁寧に築いていくことで、たしかにそれは“国”と呼べる存在になるのかもしれない――会場の空気がふっと納得へと変わった瞬間でした。
その話を聞きながら、生徒たちのなかには「そういう夢の持ち方もあるのか」と、あらたな気づきを受け取った子もいるのではないでしょうか。
【おわりに】
「ゆっくりいそげ」
「自分の時間を生きる」
「それぞれの命を全うする」
「独立国家をつくる」
影山知明さんの言葉は、情報とスピードに翻弄されがちな現代において、ひとりひとりが“自分の命を生きる”ことの尊さを、やさしく、でも確かな言葉で伝えてくださいました。
この講演会で生まれた空気とメッセージが、参加した生徒や先生、保護者の心に、静かに、そして長く残っていくことを願っています。
PTA会長 小野田 整

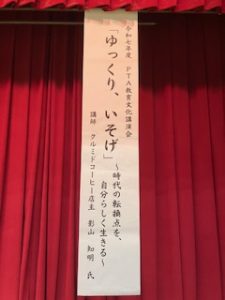
122 令和7年度の新たなPTAが始まりました
令和7年度が始まり、早くも1か月が経ちました。
去る5月2日に、PTA総会が開催され、新体制での1年が幕を開けました。
一方生徒たちはというと、1年生はオリエンテーション合宿に向けての話し合いを深め、2年生は自然体験学習を通して、思考と実践を結びつける「シンカ」に取り組み、3年生は修学旅行を通じて、自らの「コウドウ × ヘンカク」を実践しています。
各学年がそれぞれにテーマを掲げ、主体的に学びを深めている姿に、頼もしさを感じます。
先生方もまた、「躍動」というテーマのもと、子どもたち一人ひとりの志を支え、豊かな人生と持続可能な社会の実現に向けて、日々教育の探究に取り組んでくださっています。
この附属中学校は、自治体立の学校とは異なり、地域や教育委員会との関わりが比較的少ない分、大学と連携し、各地から集まった優秀な先生方が研究と実践を両立させた教育に取り組まれているのが特長です。
PTAの活動もまた、地域との連携よりも、子どもたちや先生方の学校生活を直接支えることに重きを置いているといえます。
今年度も、文化部主催の「文化セミナー」、体育部主催の「スポーツ懇親会」、掃除等の奉仕活動「附中ファンミーティング」などを予定しております。これらの活動は、保護者同士や先生方との交流を深め、学校というコミュニティをより豊かなものにすることにもつながっています。
PTAと聞くと、「堅苦しい」「面倒」といった印象をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし実際には、子どもたちの学校生活を支える“もう一つの大人のコミュニティ”ともいえる活動です。
親同士が顔見知りになり、先生方との距離が少し縮まることで、子どもたちにとっても家庭と学校の間の安心感がぐっと増すことでしょう。
PTA活動を通じて「ちょっとした顔見知り」が増え、「挨拶が交わせる関係」が広がれば、それだけでこの学園はさらに温かく、豊かな場所になると私は信じています。
「いままでPTA活動に興味がなかった」「参加に不安がある」という方も、ぜひ一度、気軽に足を運んでみてください。
普段は話す機会の少ない方と出会えたり、先生方の熱意に触れたりと、家に帰ったときの食卓の話題がひとつ増えるような、そんな機会になることを願っています。
今年度1年間、どうぞよろしくお願いいたします。
令和7年度 PTA会長 小野田 整
121 1年を終えて
3月5日に卒業式、13日に修了式が行われ、子どもたちはそれぞれに今年度の学校生活を終えました。
PTAの役員は5月の総会まで継続しますが、令和6年度のPTAの事業も無事に終えることができました。
これも保護者の皆様方のご理解とご協力があってのことと思っております。
本当にありがとうございました。
卒業式ではPTAを代表して、卒業生に話をする機会をいただきました。
その中で最も子どもたちに伝えたかったことの一節をこちらにも書かせていただきます。
これからも皆様とともに子どもたちや学校を支えていければと思っております。
そして、わたくしから、ここにお集まりの保護者の代表として、皆様と共通して言えると思うことは、「君たちへの感謝」です。
心も身体もここまで大きく成長する中で、良い時も悪い時も、いろいろなことがありましたが、成長を見守る喜びを初めて気付かせてくれました。
あなたがいなければ、経験出来なかったこと、感じることが出来なかったことがたくさんあります。
親としてだけでなく、私たちの人生を楽しく、豊かにしてくれている大切な存在です。
私たちはあなたたちをこれからもずっと応援し、一番のファンであり、どんな時でもあなたの味方で居続けます。
だからこそ、必要があればいつでも頼りにしてください。
そして、君たちからもらうたくさんの新しい刺激も楽しみにしています。
本当にありがとう。
令和6年度 PTA会長 柴田 健史
120 第43回岡崎市PTAコーラスフェスティバル
https://www.youtube.com/live/m_g7xd93rjY?si=aorZbNniPautXmdn
219 PTAスポーツ懇親会
暦のうえでは冬となりましたが、天候にも恵まれて少し暑いくらいの11月の土曜日。令和6年度PTAスポーツ懇親会を開催いたしました。校舎改修工事の影響で、今年度の会場は岡崎市の甲山会館です。
1.講演会
講演テーマ:「歩くはすごい!」1日1分の骨盤スクワットで美姿勢になるウォーキングメソッド
講師:みのわあい。先生(ウォーキングヘルスケアコーチ)
「シュッ、シュッ、シュッ」
みのわあい。先生の元気な掛け声から始まった講演会。太陽のように明るい先生の、楽しくて分かりやすいお話に会場は終始笑顔に包まれました。
また、実際に体を動かすことでの気づきもたくさんあり、気が付けば、あっという間の60分でした。
先生曰く、「骨盤スクワットはコスパ最強」講演会での内容を思い出し、1日1分、姿勢を意識しましょう。
2.ミニフォトロゲイニング
早いチームは、講演会が始まる前から熱心に作戦会議をしていたミニフォトロゲイニング。
従来のフォトロゲイニングのルールに加えて、今回は附中懇親フォトロゲ特別ルールを設けました。
スタート前にチェックポイントを選んで、ポイント写真のシールをスコアシートに貼ってから出発です。
川村先生の合図とともに、どのチームも慌ただしく会場を後にしました。
例年よりも短い40分の制限時間でしたが、ゴール後の記念撮影では笑顔が溢れていました。
3.懇親会
コロナ禍以降、中止されていた夜の懇親会。5年振りに復活しました。今回の親睦会のテーマは「昭和」。
テーマを意識した会場内およびテーブル回りの装飾は、体育部員さんの力作です。
校長先生のお言葉、PTA会長の乾杯の掛け声から始まった歓談タイム。受付で渡されたドリンク引換コインを持って、ビールサーバーへ直行される方、ソフトドリンクやお菓子を取りに行かれる方。それぞれの楽しみ方ができました。普段はなかなか交流する機会のない保護者同士、先生方との親睦を深めることができて、大変有意義な時間となりました。
次は、東海3県出身者には懐かしい天才クイズ。クイズの内容は附中にちなんだ問題ですが、どんどん上がる難易度に驚きつつ、会場の皆さんも、「イエース」「ノー」と元気に〇×帽を掲げました。
天才博士役を快くお引き受けいただきました、鈴木悠里先生。ありがとうございました。
3回参加者とミニフォトロゲイニングの表彰、いよいよクライマックス。
体育部員から選ばれた皆さんによる、「明日があるさ」の大合唱。この瞬間、会場は熱気に包まれました。
今回のスポーツ懇親会にご参加いただきました皆様、素敵なイベント進行と会場設営、装飾等、9月の暑い日にフォトロゲの下見でコースを歩いてくださった体育部員さん、川村先生、そして体育部小部会メンバー、関わっていただきましたすべての皆様へ、心からお礼を申し上げます。
令和6年度 体育部部長 大橋 久美子






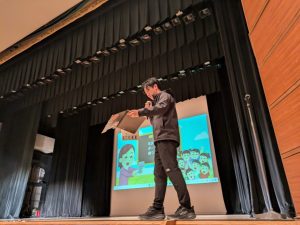






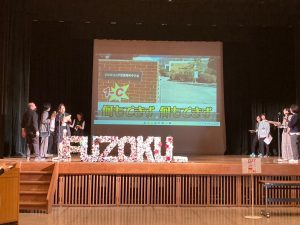
118 第2回「附中ファンミーティング」
10月12日(土)14:00~、秋晴れの中、総勢約80名の方々にご参加いただき、無事開催することが出来ました。
今回のファンミーティングの目的は、親同士の横のつながりをつくること、親と先生とで協同作業することで互いの人間関係をつくり、よりよい学園をつくっていくこと。そして来月開催される体育大会で子どもたちに素晴らしいグランドコンディションで活動してもらえるよう、運動場に生い茂る大量の雑草を除去することでした。
当初の想定よりも気温が高く夏の気配が漂う炎天下での作業、また雑草の繁殖はすさまじく、抜くではなく根こそぎ掘り起こして整地していく土木作業となりました。
幾度となくくじけそうになりながらも、このきつい作業は我々にしか出来ないことと、使命感を掻き立てながら、皆で声を掛け合い、後半は音楽をかけ「負けないで」を歌いながら80分間の作業を続けました。最終的に皆で取った雑草の重さは約350kg。全員が疲労感を感じながらも、大量の雑草の詰まった袋を目前にして「子どもたちのために汗を流し、頑張ってよかった」と誰もが思い、充実感へと変わった瞬間でした。
今回も、事前にチーム分けをし、獲得した雑草の重さをゲーム形式で競い合いました。
優勝チームには「すやの栗きんとん」が贈呈され、余りは「じゃんけん大会」を行い、皆さんの笑顔がはじけます。最後は大いに盛り上がることができました。ご参加いただいた皆様には感謝しかございません。本当にありがとうございました。
また、附中ファンミーティングと名称変更をした効果で、心温まる出来事もございました。それは、このファンミーティングのためだけに、遥々京都から、附中卒業生である京都大学2年生の学生さんが参加してくださいました。実は第1回の時も別の附中卒業生の学生さんが参加してくれていました。私はその学生さんの想いをきいて、附中って本当に素晴らしい!附中をこよなく愛する、後輩想いの素晴らしい先輩がいるこの学校に、我が子たちが通えて本当によかったと、そう思える出来事でした。
これからも、「附中ファンミーティング」が、全ての附中ファンのよりよい活動の場、ふれあいの場となりますよう、皆様のお力添えをいただけますと幸いです。
令和6年度PTA副会長 牧原広和








117 全附連 PTA研修会
9/27(金)、9/28(土)に東京で開催されました「全国国立大学附属学校PTA連合会 PTA研修会 第15回全国大会」にPTA役員で参加してきました。
二日間の研修では幅広い分野での講演や説明が行われましたが、最も印象に残ったものは、哲学研究者の永井玲衣氏の「問いあう、ききあう、考えあう」の演題で、『哲学対話』についての講演でした。
『哲学』と聞くと何か難しい事と捉えてしまいますが、一つの『問い』について互いに意見を述べ、聞き合うことを通じて、互いを理解し合うことを学びました。対話と言いつつも重要なことは聞くことであるとの話があり、子どもや家族はもちろんのこと、仕事や社会生活の中でも聞くことの大切さをあらためて再認識する機会となりました。
また、省庁行政説明や他の附属学校の取り組みを聞く中で、国立大学附属学校園の意義や在り方を再確認し、PTAとして何が出来るのかを考えさせられるとともに、他の附属学校とのつながりを持つことの重要性も感じることとなりました。
今回の研修の様子は会員に向け10/17(木)から10/31(木)までYouTubeによる動画配信が行われます。
またあらためて学校から皆様に通知がありますが、是非ご覧いただき新たな気づきに繋がるきっかけとなれば幸いです。
令和6年度PTA会長 柴田 健史

116 PTA文化展
9/25日(水)にPTA文化展を開催いたしました。
本年度は、文化セミナーで制作していただいたポーセラーツマグカップ68点を展示いたしました。
今年度の文化祭は市民会館での開催となったため、文化展も2階ロビーが会場となりました。
外から日の光が射し込む明るい空間で、皆さんの個性あふれる作品が会場を彩ってくれました。
大切な作品をご出展くださった皆さま、ありがとうございました。
また、当日会場に足を運んでくださった皆さま、会場設営にご協力いただいた文化部員の皆さん、お力添えをいただいた先生方…関わってくださったすべての皆さまに感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
今年度の文化部の活動はこれで終了となりますが、今後行われます各イベントにも奮って参加し、私たち保護者も附中を楽しめたらと思います。
令和6年度PTA文化部長 犬塚嘉奈子





115 2学期スタート
2学期スタート
皆様、こんにちは。
夏休みが終わり、2学期がスタートしました。
例年よりも長い夏休みで子どもたちは充実した時間を過ごせたと思いますが、保護者の皆様はいかがだったでしょうか。
先日、全国国立大学附属学校連盟東海地区会・東海地区国立大学附属学校PTA連合会 研究協議会・実践活動協議会に多くの先生方とともに、PTA役員も参加してきました。
講演会に続くPTA部会では、防災について他の附属学校PTA役員とディスカッションを行い、災害時にPTAとして出来ることを議論しました。
附属中では、公共交通機関で通う生徒が多いこともあり、通学中で被災した場合の想定や、連絡が取れない場合どのようにするかなどを考えておく必要性を感じました。
南海トラフ地震臨時情報が初めて発表されたこともあり、あらためて災害に対する意識を高めるきっかけとなりましたので、皆様もぜひ親子で防災について話し合っていただければと思います。
さて、2学期は文化祭、体育大会と子どもたちが作り上げる大切な行事が行われます。
それぞれの立場で頑張っている子どもたちをたくましく思い、その成果を見られることを楽しみにしているところです。
またPTA活動では、体育大会前に第2回附中ファンミーティングの開催を予定しています。
さらに11月にはPTA体育部主催でスポーツ懇親会を開催いたします。
どちらの行事も保護者同士や先生とのつながり、学校をより知ってもらうきっかけになればと思っていますので、皆様の参加をお待ちしております。
PTA会長 柴田 健史
114 令和6年度第1回「附中ファンミーティング~われらの学園親子会~」
皆様、こんにちは。
昨年度まで「OYAZY’S会」として開催していた親父の会ですが、今年度より名称を新たに『附中ファンミーティング 〜われらの学園親子会〜』として開催することにいたしました。これは、今まで大好評だった「親父の会」を男親に限定せず、誰もが気軽に参加しやすくするためにネーミングを変更したものです。
この会は、附中をこよなく愛するファンが集まり、子どもたちのため、そして学園のために、楽しく貢献しようという趣旨で行われます。また、このご縁を通じて、親同士や親と先生がゆる〜くつながり、安心で楽しいわれらの学園をつくることを目指しています。
そして、そんなファンミーティングの第1回が、去る6月8日に開催されました。内容は、校舎改修工事に伴う生徒の引っ越し準備です。昨年を上回る45世帯、65名の方々にご参加いただき、各種作業に取り組みました。
作業内容は、椅子や机の運搬・廃棄、育朋館のシート貼り、倉庫整理など多岐にわたりました。軽作業かと思いきや、本格的な引っ越し作業で、子どもたちでは難しく、先生方が子どもを見ながら行うには時間がかかる作業でしたので、まさにファンミーティングに相応しい内容でした。参加者の皆さんにとっても予想外の作業量でしたが、おかげで連帯感が生まれました。
椅子を運ぶ際には自然とリレー体制ができ、声を掛け合いながらの作業はまさにワンチームでした。体育倉庫から最後の椅子を運び出したときには歓声が上がり、お祭りのような雰囲気でした。大変でしたが、楽しい時間でした。
また、育朋館にはすでに6クラス分の仮教室が設置され、家庭用エアコンも取り付けられていました。土足シートを貼りながら、附中生が普段とは違う環境で前向きに学校生活を送る姿を想像しました。このような制約も、この時期にしか体験できない貴重な経験だと前向きに捉え、この形でしか生まれないものを生み出してくれるだろうと期待が膨らみました。
少し予定時間を超えての作業となりましたが、参加者の皆さんは附中に深く関わり、お子さんたちに良い話を持ち帰ることができたと思います。参加者の皆さん、そして先生方、本当にお疲れ様でした。
最後に、附中ファンミーティングは今年度第2回も計画中です。この会は、親同士のつながりを深めるとともに、先生方とも連携し、皆でより良い安心な学園をつくることを目的としています。ぜひご都合に合わせてご参加いただき、子どもたちとともに附中を楽しみましょう。
令和6年度PTA副会長 小野田 整











113 附中文化セミナー開催!
保護者の皆さん、こんにちは。
6月4日(火)・6日(木)の2日間計4回にわたり令和6年度附中文化セミナーを開催いたしました。短い募集期間ではありましたが96名の皆さんにご参加いただくことができました。
1日目には手島副校長先生・小林教頭先生・柴田PTA会長が、2日目には貴宝先生がご参加くださり、皆さんと一緒に楽しく制作をしてくださいました。
今年度は『ポーセラーツで作るオリジナルマグカップ~お気に入りで彩る楽しい暮らし』と題し、講師に軍魁栄先生をお迎えしました。
ポーセラーツとは、磁器に転写紙と呼ばれるシールを貼り付けオリジナルの食器やインテリアを作ることができるハンドクラフトです。
10種類ほどの転写紙の中からお好きな柄を選び、自由にデザインしてマグカップに貼り付けていきます。中には数種類の転写紙を組み合わせてデザインされる方も!
皆さんそれぞれの工夫が見られて『世界にひとつだけ』のオリジナルマグカップが出来上がりました。
講師の先生からは『みなさんの発想に感動♡こんなアイデアあるんだ!とデザインすることの面白さを改めて実感させていただきました』とのお言葉をいただきました。
また、セミナー期間を通して先生方のご協力・部員さん達の連携に驚かれ、感謝のお気持ちを伝えてくださいました。
制作中は、皆さん転写紙選びやご自身の作業に没頭されつつも、参加者さん同士でお喋りされる様子、講師の先生方の丁寧で優しい雰囲気に自然と会話が弾みあちらこちらで談笑する様子が見られるなど和やかな空間だったことが印象的で、とても嬉しく思いました。
また、お帰りの際には講師の先生方に『楽しかったです!』と笑顔で直接感想を伝えられる方が多くいらっしゃったことも嬉しかったです。
今年度は、改修工事で会場の確保が難しい中、例年通りに開催できるようご配慮くださった先生方、また日々お忙しいにも関わらず準備の段階から様々なお願い事に快く対応してくださった今村先生、ご参加いただきました皆さん、ご協力いただいたすべての皆さんに心から感謝いたします。本当にありがとうございました。
お作りいただいた作品は、講師の先生が焼き上げてくださり、およそ1ヶ月後にお手元に戻って参ります。
作品との再会を楽しみにお待ちください。
令和6年度PTA文化部長 犬塚 嘉奈子






112 令和6年度PTAスタート!
5月2日に令和6年度総会が行われ、新役員や予算・事業計画などをご承認いただき、ようやくPTAも新年度がスタートいたしました。
この附属中学校はお住まいの市町や学区を越えて、附属中での生活に夢を持ち、望んで来られた子どもたちが集まっています。また保護者の皆様もそのお子様の想いを支えていこうとの考えをお持ちのことと思っております。
PTAはその子どもたちの想いを支え、保護者の皆様の想いを具現化するべく、活動していきたいと思っております。
また、この附属中は大学と連携して実践的な教育や先進的な取組みを行うことが一つの使命であり、独自性の高い実践を進められています。
そういった学校だからこそ、実践的な取組みを進める学校や先生方を支えていくことが重要であり、保護者としても必要あれば意見を述べて、学校や先生方とより深く連携していくことも附中PTAの大きな役割であると思っております。
まずはPTAが他人事だと思わず、一度活動に参加して、お子様が通う学校に来てみてください。
学校内を見ることや、保護者同士や先生方と交流することで、学校の状況やお子様の学校生活をより深く知ることができ、それがお子様との会話のきっかけにもなると思います。
今年は校舎改修があり、イレギュラーで少し不自由な1年になるとは思いますが、子どもたちはその逆境をプラスに考えて、様々な考えを巡らせています。
私たちも子どもたちに負けないよう、出来ることからですが、子どもたちのために活動していきたいと思っております。
校訓である「われらの学園」、これは子どもたちや先生方だけのものではありません。
私たち保護者にとっても「われらの学園」であります。
保護者の皆様にも、子どもたち先生方とともに「われらの学園」としての想いを持っていただき、子どもたちが充実した学校生活を送れるよう皆様で協力していきましょう。
一年間どうぞよろしくお願いいたします。
令和6年度 PTA会長 柴田 健史
111 「われらの学園」
乙川の河津桜も満開を迎え、足元の草花も徐々に鮮やかさを増すよき日に、第76回卒業式を迎えさせていただくことができました。
卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。
心から皆さんの卒業をお祝いし、これからの益々のご活躍を願っております。
保護者の皆様、お子様のご卒業おめでとうございます。
また、3年間にわたりPTA活動に対し深くご理解をいただき、本当にありがとうございました。
至らぬ点もあったかと思いますが、附中を見守る皆様の温かいお気持ちのおかげで、今日まで活動を行うことができました。
これからも『われらの学園』にお心を寄せていただけたら嬉しく思います。
卒業生の皆さんをはじめ、保護者の皆様の益々のご多幸とご健康をお祈りし、この場をお借りして皆様に厚く御礼申し上げます。
ありがとうございました。
在校生の皆さん、保護者の皆様、これからも大切な『われらの学園』で益々輝いてください。
令和5年度 PTA
会 長 山内 勇吾
副会長 近藤 健児
副会長 加藤亜紀子
体育部長・3年学年代表 髙橋貴志子
110 「第2回 OYAZY’s会」
冬日和の土曜日の朝、第2回おやじの会を開催いたしました。
総勢約40名の保護者のみなさんと先生方にご参集頂きました。
今回も多くのお母様にもご参加いただき、また生徒さんも参加してくださいました。
ご多用の中これだけ多くの方々にご協力いただけたことに感謝致しております。
今回は子供たちの生活の場である教室(窓、エアコン)の清掃を中心に行いました。
多くの保護者のみなさんは、階段の踊り場や教室内の掲示物などを見て、子供たちの附中生活を想像しながら清掃に取り組んでくださったと思います。
またご参加くださった保護者のみなさん同士や先生方とも子供たちの話ができたのではないでしょうか。
皆さん埃まみれになりながらも窓は曇り一つない素晴らしい磨き上げ具合に、エアコンは埃ひとつない綺麗なフィルターに仕上げてくださり、子供達への思いの込もった作業をして頂けました。
今年度のおやじの会は今回が最終回です。
いつもご参加してくださっている3年生の保護者のW様にお一言コメントを閉会時にお話しして頂きました。
実は参加し始めたきっかけは「お子さんからの参加要望だった」というエピソードをお伺いし、とても感動をいたしました。
急なお願いにも関わらず皆さんの前でお話ししてくださることをご快諾いただきましたW様本当にありがとうございました。
最後になりますが、本日ご参加くださった多くの保護者のみなさん、先生方に心から感謝申し上げます。
また9月に開催した第1回おやじの会(グランドの石拾い&草刈り大会)にご参加くださった保護者のみなさんにも改めて感謝申し上げます。
おやじの会の活動を通じ私たちの大切な子供たちが生活する学校に一人でも多くの保護者のみなさんに触れて頂き、関わっていただける機会になっていれば幸いであります。
附属岡崎中学校に関わるすべての方が「われらの学園」として末永く関わっていただけることを強く願っております。
今年度おやじの会に関しまして、至らぬ点も多々あったかと思いますが、保護者のみなさんのご理解とご協力、先生方のご支援のおかげで無事遂行することができました。
本当にありがとうございました。
来年度もおやじの会の活動は計画されることと思います。
是非お一人でも多くの保護者のみなさんのご参加をお待ちいたしております。
附属岡崎中学校
令和5年度 副会長 近藤健児

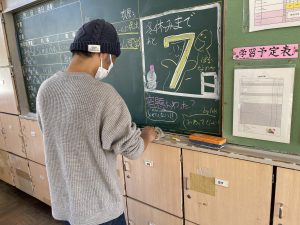

















109 「附中懇親フォトロゲイニング」
みなさま こんにちは。
11/18 (土) 附中懇親フォトロゲイニングを開催しました。
総勢115名。
たくさんの保護者のみなさんと先生方がご参加くださいました。
当日、欠席になってしまった方、参加できなかった方なども含めまして、たくさんのみなんさんに、ご賛同、ご参加いただけましたこと、心よりお礼申しあげます。
今年は11月開催となり、肌寒さを感じつつも、フォトロゲイニング日和となったと思います。
フォトロゲイニングとは、チェックポイントと同じ写真をとってポイントを競うスポーツです。
附中懇親フォトロゲイニングは、楽しい写真を撮って親睦を深めるスポーツ懇親会です。
今年は、60カ所のチェックポイントを設定しました。
優勝めざして、ポイントをとる?
行ってみたいポイントへいってみる?
親睦重視でゆる~りと岡崎の街めぐり?
クラス別保護者に先生が加わったチームごと、自由に作戦をたてて。
やる気持ちか?みなさん早々の出発でした。
本部に送られてくる写真はどれも、全力で楽しんでる最高の笑顔のものばかりでした。
気持ちよく楽しく歩いて、走って、ゴールした後は、コロナに阻まれていた懇親会への一歩として、プチ懇親会を用意しました。
スパークリングりんごジュースでカンパイ!
先生のこと身近に感じられるクイズや、先生方の整理体操?なる企画もしていただいて、子ども達がどんな先生と過ごし、どんな雰囲気の附中を満喫しているのか。
子どもの情報交換に驚いたり、笑ったり、うれしくなったり。したことと思います。
ぜひお子さまとも、お話ししてみてもらえたら、それがいちばんうれしいです。
附中らしさ。そのもの。と思えるような一日になったのではないでしょうか。
たくさんのみなさんから、
楽しかった!来年も参加するね。
本当に何よりのご褒美をいただきました。
ぜひ、来年もたくさんのみなさんの笑顔あふれるスポーツ懇親会ができることを心から願っています。
来年もよろしくお願いいたします。
こんな素敵な機会を許可して下さる、附属中学校は最高です。
多大なるご尽力を惜しみなくして下さった、貴宝先生、加藤副会長、体育部員のみなさん、おつかれさまでした。
ありがとうございました。
PTA体育部長 髙橋 貴志子




108 「Pネット講座」開催!
本年度の「Pネット講座」は、
1 高齢化社会に対して自分たちにできること
2 スマホ、ゲームヘビーユーザー必見!目を大切にする 講座
3 蜂の子を食べる文化について知ろう
4 笑顔いっぱい‼︎アイシングクッキー
5 新聞を利用した講座
6 煎茶のお手前、お菓子のいただき方
7 歌おう、Jポップ!
8 BLS、AED体験
9 煎茶のお茶会の作法
10 生物の実験・観察
11 体操教室
12 ネイルセラピー
13 超初心者のための伝える、楽しむ、写真講座
14 押し花講座
15 生成AIを体験しよう
16 めちゃモテ!DJ講座
17 ギター沼の世界へようこそ
18 附中二郎を食す
の18講座が開催されました。
普段の教科とはかけ離れた、先生方の講座もありました。
ズラリと並んだ、学校では学ぶことのできないような講座は見ているだけでワクワクします。
この幅広いジャンルの中から、それぞれ興味のある講座を選択します。
希望通りの講座、そうでなかった子どもたちもいたかと思いますが、普段触れることの無い世界を仲間とともに垣間見れたことが、とても良い経験になったと思います。
講師の方々は、90分という限られた時間内で、五感をフル活用し、子どもたちに楽しくわかりやすく丁寧に伝えてくださっていました。
ぜひお子さんに、どんな講座だったのか聞いてみてください。
私たちの世界も一緒に広がることと思います。
※全てのお写真を掲載できず申し訳ありません
講師のみなさま、ありがとうございました。
そして、ぜひ今後もよろしくお願いいたします。
PTA副会長 加藤亜紀子





107 「PTA文化展」
11/2にPTA文化展を開催しました。
本年度は、文化セミナーで作成したリボンアートフラワーと、附属特別支援学校PTAサークルで作成したアクセサリーを展示させていただきました。
リボンアートフラワーは60点、アクセサリーは15点と大変多くの作品を出展していただきました。
また、美術部員さんが黒板に素敵な絵を描いてくれました。
展示室に彩りを加えていただきありがとうございます。
作品を出展いただいた皆さん、会場設営に協力いただいた部員さん、サポートしていただいた先生方、とても多くの方に支えられ文化展が存在していると改めて感じました。
本当にありがとうございます。
今年度の文化部の活動はこれで終了しますが、PTA活動はまだまだ続きます。
今後の各イベントにもぜひご参加いただき、附中を楽しんでいただけたらと思います。
引き続きよろしくお願い致します。
令和5年度PTA文化部長 平手 恵子



106 「体育大会」
PTA役員の北川と申します。
9月16日(土)に、体育大会が開催されました。
天気は快晴、を通り越して9月中旬の気候とは思えない猛暑日でした。(最高気温34度)
この暑さをものともせず、体育大会を全力でやり切った附中生たちの姿を見て、今年も大きな感動をもらいました。
附属岡崎中学校の体育大会は、生徒たち中心で競技・制作物・グループ応援などの内容を決めて、自主的に準備、運営をすることが伝統であり特色の一つでもあります。
学年を超えた仲間たちと協力しながら、自分たちで作り上げた体育大会を見事に終えた子どもたちは、充実感や達成感のある凛々しい顔をしていました。
大会を迎えるまで子どもたちをずっと見守り続け、大会当日は朝早くから夕方まで応援をしてくださった保護者の皆さま、本当にお疲れ様でした。
そして、体育大会を最後まで支えてくださった先生方、関係者の皆様、本当にありがとうございました。
こういった素晴らしい行事をこれからも続けていけるように、引き続き保護者の皆様のご支援とご協力をいただけましたら幸いに存じます。








105 「第1回 OYAZY’s会」
皆様こんにちは。
令和5年度PTAで会計を務めさせていただく小野田です。
日頃はPTA活動にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。
さて、9月2日、9月最初の土曜日。
晴天には恵まれましたがその分しっかりと暑い日。
令和5年度第1回のOYAZY’s会が開催されました。
今回は、体育大会を控えて運動場の草取りです。
子ども達が日頃の成果を気持ちよく思いきり出せるように、集まっていただいた皆さんで雑草を一掃です。
また、せっかくなら楽しく草取りをしようということでくじ引きで9チームに別れ、チームごとでの抜いた雑草の重さで競いました。
参加したのはお父さんを中心にお母さんやお子さん、そして校長先生始め先生方。
みなさん暑さに気をつけて、水やタブレットで補給しながら楽しく草取りに励みました。
スコップで草を根こそぎ掘り起こす方、そこから草を選り分ける方、気づくと連携が取れている姿が印象的でした。
そして雑草の取りにくさ具合から先日のバスケットボール日本代表の勝利、そして子供達の日々の暮らしなど、たわいもないことを話しながら気づくとあっという間の1時間でした。
雑草が集まったら、ドキドキの計測タイムです。
大きな体重計に役員が集めた草を持って乗り、皆その数字を注視しています。
そして優勝は16.15kgもの草を集めた2-Aチーム!
(くじ引きで決めたチームなのでクラスではありません。)
そのほかのチームもそれぞれ頑張り、とれた雑草はなんと合計で91.35Kg!
当日参加された、オヤジを中心とした皆様そして先生方、お疲れ様でした。
あとは、体育大会で魂を燃やす子ども達を応援するのみ!
自分は今までPTA活動にはそこまで積極的に参加するタイプではなかったのですが、ご縁があって役員をやらさせていただき、この活動を通して日頃子供が学校生活を送っている環境が良くなったり、親同士や先生との交流の機会が生まれるのはもちろんのこと、親自身が学校環境を知ることで、子どもとの会話が増え、親としての生活も豊かになるなぁと感じました。
今年度のOYAZY’s会は第2回も計画中です。
ぜひ、ご都合に合わせてご参加ください。
子どもだけでなく親も附中を楽しみましょう!
令和5年度PTA会計 小野田 整






104 「第1回 OYAZY’s会 開催のご案内」
みなさん、こんにちは。
いつもPTA活動にご理解をいただきありがとうございます。
保護者のみなさんと学校をつなぐお手伝いをさせて頂いています、副会長の近藤です。
さて少し先のお話になりますが、9月2日(土)の朝9時より、『第1回 OYAZY’s会』を開催いたします。
(先日お子様を通じてご案内を配布させていただきました。またマメールでの配信も行っております)
OYAZY’s会とは、「学校とゆるく関わりたい」、「学校のために何かをしたい」、「スポ懇、文化セミナーに参加できない」という保護者のみなさまが学校に関わる機会を設けるための会です。
お父様を中心にご参加を頂いてきておりますが、お母様及び在校生とその兄弟姉妹の参加も歓迎いたします。ふるってご参加ください。
第1回目は体育大会前のグランド整備および草取りを主に行ってまいりたいと思います。暑い時期ですので開催時間帯を『朝の時間帯9:00~10:30』として行います。
どうかご協力の程お願いいたします。
ご協力、ご参加いただけます方は下記サイトおよびQRコードよりアクセスいただき参加登録をよろしくお願いします。
申込期限 令和5年8月24日(木)23:59まで
申し込み→ https://forms.gle/JsPPhiXCtvUvk6zX7

103 「令和5年度PTA文化セミナー」
保護者の皆様こんにちは
PTA文化部長の、平手恵子です。
6月2日(金)と6日(火)の2日にわたり、文化セミナーが行われました。
1日目は手島副校長先生、山内PTA会長、2日目は村上教頭先生にご参加頂き、皆さんと共に楽しく素敵な作品を作って頂きました。
本年度は、『リボンでつくるアートフラワー〜生活に花を、人生に華を〜』をテーマに、長坂裕見子先生を講師に迎え開催しました。
一本のリボンからバラを生み出し、それに葉や飾りを加えながらアレンジしていきます。
そして最後は撮影スポットで写真を撮って完成です。
完成した作品は、花の大きさやアレンジ方法など様々な個性があり、皆さんの発想力に驚かされるばかりでした。
「リボンからボンドと歯ブラシでどう花を作るの?と思ったけど良く分かった!」
「リボンのしわが良い感じになるのね。」
「癒しの時間になりました。」
などうれしい感想を多数頂けました。
また、初めて取り組む方が多い中、講師の長坂先生もホワイトボードや手元を写すモニターを使いながら、丁寧に分かりやすく教えて頂きました。
とても楽しく作品を仕上げる事ができたと思います。



今年度は新型コロナも5類に移行し、大変多くの方に参加して頂く事ができました。
これも過去3年間、試行錯誤をしながらセミナーを継続開催して下さった歴代文化部長さんのおかげだと思います。
また、松井先生はお忙しい中にもかかわらず、準備の段階から様々な依頼にも快く迅速に対応して下さいました。ご協力頂いた皆様に感謝いたします。
本セミナーが、皆さまにとって癒しの時間となりましたなら幸いです。
生活に花をそえ、人生が彩り華やかなものになりますように。







102 「PTAコーラスクラブ 初回顔合わせ会」
皆さんこんにちは。
本年度PTAコーラスクラブ代表の浦邉です。
去る5/22、初回顔合わせ会が附中音楽室にて行われ、本年度のコーラスクラブが始動いたしました。
まだ知り合いの少ないお母様が不安にならないように、温かい雰囲気を心掛けて、準備をいたしました。
何より指導の柴田さんが素敵で、皆さんファンになられたのではないでしょうか。
一年生保護者はもちろん、二年三年の保護者の方々にも新たに12名、入部を希望していただきました。
皆さんが笑顔で帰っていかれた姿が印象的な初日でした。
私たちは、歌い継がれている名曲を一年間かけて歌います。
名曲は歌い込むほど見えてくる景色があります。
思春期、中学生の子供たちは急に何かに憑かれたように変化して、そっぽを向いてしまう時があります。
子供が帰宅した時、習い事の送迎の時、食事を作る時、親が一年間ずっと同じメッセージの曲を歌い続けることは、そんな子供達の重たいリュックにお守りのキーホルダーをつけるようなことだと感じています。
今年も二曲歌います。
一曲目は嵐の『カイト』
TOKYO2020オリンピックのNHKテーマソングとして、米津玄師さんが作詞作曲されました。
支えてくれた人、支えたい人の顔を思い浮かべながら歌い、夢に向かって歩む子供達に思いを届けられたらと思って選曲しました。
二曲目は、童謡『にじ』(庭のシャベルが)
雨の気分から最後には晴々とした気持ち(きっと明日はいい天気)になる名曲です。
大人も子供も日々色々な事があります。
そんな日常生活の中で、こんな気持ちになれるんだよという情景を歌えたらと思っています。
ピアノ伴奏の大人っぽいアレンジもお楽しみ下さい。
昨年の活動にも反響をいただいております。
伴奏の安田さんは昨年文化祭に感動されてのご参加です。
フルタイム勤務の保護者、平日の練習参加が毎回は難しい方からも参加したいとの要望をいただいております。
次回6/5にも新たに3名の方が見学されます。
特にテノールで参加される方を熱望しておりますが、まだまだ他パートでも歓迎しています。
文化祭、憧れの育朋館でお子さんへメッセージを伝えてみませんか?
お世話係の池江、齋藤、内山ともに、サポートさせていただきます。
お近くの部員まで、お問い合わせください。




101 「かっこよかったよ!」
皆さんこんにちは。
令和5年度、PTA副会長を務めさせていただきます加藤亜紀子です。
1年間どうぞよろしくお願いいたします。
さて、頑張る附中生の総体結果を、皆さんもご覧になりましたか?
私は今回、ベスト4へと勝ち進んだサッカー部の応援へ行かせていただきました。
この日は朝から少し肌寒かったのですが、両チームとも、たくさんの温かい応援に包まれキックオフ。
前回王者に果敢に挑みました。
午後からは、冷たい風と雨が降りしきる中での試合となりました。
どんどん体力を奪われていく様子の子どもたちは、接触して足を引きずりながらも、懸命に声を出し、前を向こうと必死に戦っていました。
心が折れそうになる様な状況の中、それでも諦めずに戦い切った姿に、心を揺さぶられたのは私だけではないでしょう。
ピッチで戦う選手、ベンチでサポートする選手、体調管理、送迎のサポートをした保護者のみなさん、友の勇姿を応援する仲間、たくさんの人たちの思いが詰まった、とても良い試合を見せていただきました。
真剣に全力で取り組む姿は人の心を打つのだと、改めて実感した一日となりました。
きっと、他の部活動の試合でも子どもたちの勇姿が見られたことと思います。
みなさん
お疲れ様でした!


100 「皆さまよろしくお願いします」
今年度 体育部長・3年学年代表を務めてさせていただくことになりました。髙橋貴志子です。
ぜひ変化を楽しみながら、附属中学校をより大好きになったね。とみなさんにも思っていただけるような活動になるよう、微力を尽くしたいと思っています。
よろしくお願いいたします。
4/20㈭ 令和5年度PTA・育朋会
役員会、評議員会が開催されました。
コロナ対策も日々緩やかになって変化していく中、ほぼマスク着用ではありますが、一堂に会してのピリッとした雰囲気の中で、新年度のスタートをきりました。
コロナ禍により、たくさんの変化をせざるを得なかった、この数年。できないことばかり。でしたが、だからこそ気がつくこともたくさんあったと思います。
ようやく、たくさんの制限が解除されていきます。
元の生活に戻る!というよりは、自由にやりたいことをすることができる!と考え、新しい生活ができたらよいと思っております。
節度はわきまえる必要はいつ何時もあるのですが。。
楽しんだもの勝ち!!と、自由な発想と行動で1年を満喫してほしい。と願っています。
難しい一年を過ごし、最大のご尽力をしてくださいました、昨年度の役員のみなさま。お疲れさまでした。ありがとうございました。
4/24早朝、3年生は修学旅行へ出発していきました。3泊4日です。開催できる喜びとご尽力いただいた先生方に、親子共々感激です。
1年間、よろしくお願いいたします。
体育部長 髙橋貴志子
ーーーーーー
令和5年度文化部長を務めさせて頂きます、平手恵子と申します。
4月20日、初の顔合わせとなる第1回文化部会が行われました。
今回は自己紹介と今後のスケジュールについてお知らせさせて頂きました。
文化部の主な活動は、PTA文化セミナーとPTA文化展になります。
本年度も皆様にとって、楽しい作品作りの場、保護者同士の交流の場となるよう、部員一同準備を進めてまいります。
多くの方にご参加いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
文化部長 平手恵子



99 「2023年度の附中のメンバー集結!」
4月10日 晴天の下、入学式が執り行われました。
大きめの制服に身を包み込み、少し緊張した面持ち。
「ようこそ附中へ」という思いとともに歓迎するつもりが、逆に、新入生の皆さんの姿に大きな可能性を感じ、力をいただきました。
また、上級生の頼もしさと附中らしさを感じる式でもありました。
代表の歓迎の言葉はもちろん、学園歌披露であったり、入退場の際の生演奏であったり、附中らしさがあると思いませんか。
改めて、素敵な学校だと思いました。
新入生のみなさん、入学式から1週間が経ちましたが、附中生活はいかがですか?
とにかく考えることを求められる授業に、不安や戸惑いも感じ始めている頃かもしれませんね。
2年生の皆さんは、クラス替えを経て新たな仲間との再スタートですね。
3年生はいよいよ最終学年。
皆さんの個性、カラーが2023年度の附中らしさに大きな影響を与えることでしょう。
さあ、2023年度の附中のメンバーが揃いました。
附中生の皆さん、思いきり附中生活を楽しんで下さい。
そして、どんな時でも周りに目を向けることは忘れないでください。
楽しさを分かち合える仲間がいます。
うまく行かず、時に悩むこともあるかもしれません。
ヒントをくれる仲間、助けてくれる仲間がいます。
ヒントを参考にし、助け合いながら、自分の意見、自分らしさ、クラスらしさ、学年らしさ、皆さんの時代の附中らしさをぜひ作り上げてください。
2023年度附中生のみなさんを応援しています。
PTA会長 舩山 哲 


98 ~ 「正解」探し ~
厳かな式の中で、卒業生が歌ったのがRADWIMPSの「正解」でした。
(歌詞抜粋)
あぁ 答えがある問いばかりを 教わってきたよ だけど明日からは
僕だけの正解をいざ 探しにゆくんだ また逢う日まで
次の空欄に当てはまる言葉を
書き入れなさい ここでの最後の問い
「君のいない 明日からの日々を
僕は/私は きっと □□□□□□□□□□□□□□□□□□」
制限時間は あなたのこれからの人生
解答用紙は あなたのこれからの人生
答え合わせの 時に私はもういない
だから 採点基準は あなたのこれからの人生
「よーい、はじめ」
卒業生は、この歌とともに新たなスタートを切りました。
これからも、支えてくれるであろう仲間の声に耳を傾け、また、培った附中での経験を生かしながら、時に大胆に、時に軌道修正しながら、それぞれの正解に近づいてほしいと思います。
保護者である私たちも、正解探しの手助けができれば。
しかし、人生は僕のこと。私のこと。自ら選び、判断しなければいけません。
附中で学び、大きく成長した今、手助けはこれまでよりは少し控えめでも良いのかもしれません。
式に同席された在校生の皆さんも、卒業生の「正解」から何か感じるものがあったのではないでしょうか。
ぜひ、その感じたことを大切に、残りの附中生活を過ごしてほしいと思います。
皆さんの正解探しもすでに始まっているのかもしれません。
保護者の皆さま。
役員一同、こどもたちのためというのはもちろんですが、皆さまにとっての中学校生活が少しでも充実したものになるよう、模索しながら取り組んでまいりました。
この1年の思い出のひとつに、附中、PTAに関係したものがあればうれしい限りです。
今日までご協力をいただきましたことに感謝致します。
評議員を務めていただいた皆さま、コーラス部に参加していただいた皆さま、PTA行事に参加していただいた皆さま、リレーマラソン・駅伝に参加していただいた皆さま、同じ時間を過ごした附中生のすべての保護者の皆さま、本当にありがとうございました。
最後になりますが、校長先生をはじめ先生方。そして職員の皆さま。
こどもたちを叱咤激励し、また、支えていただき本当にありがとうございました。
そして、お忙しい中、PTA活動にもご尽力いただきありがとうございました。
皆さまの愛情とご尽力には、感謝と尊敬しかありません。
令和5年3月31日
令和4年度 愛知教育大学附属岡崎中学校PTA(卒業生保護者)
会長 舩山 哲
副会長 髙原 浩之
副会長 芝原 明恵
書記 鈴木 友則
体育部長兼3年学年代表 丹羽 由紀子
私たちの正解探しもまだまだこれから…
97 出会い
時々こんなことを考えています。人との出会いが自身の人生を豊かにする。しかもその出会いは特にこちらの準備が出来てない状態で突然やって来る。出会いによって人生のターニングポイントになることは滅多にありませんが、ただ一緒に笑って話しているだけで後からあの時間はよかったなと振り返ることはありませんか。そんな時間が次ももう少し頑張ってみようかなという原動力になるのです。
さて、先日、私は、学校のコーラス部の最後の活動に参加しました。その日は合唱曲への想いを共有し、またコーラス部長及びスタッフへの労いの言葉などで胸が熱くなりました。それからサプライズで指揮者の千晶先生がヴァイオリンのミニコンサートを開いてくれました。美しい音色が音楽室に響き渡り、コーラス部員は皆感動に包まれました。そして、レクリエーションでは、とりとめのない会話や笑い声を通じて、心地よい時間を過ごすことができました。




「本当に大切なものは目に見えない」という言葉が、サン=テグジュペリの『星の王子さま』の一節であります。私たちの人生にとって目に見えるものよりも大切なものは大した目的がなくてもいいかもしれません。ですから、あまりあれこれ考えず気軽に参加してみることが大切だと感じます。そうすることで、私たちは未知の世界に踏み出し、新しい出会いや経験を得ることができるからです。
今日、卒業する生徒たちは、来月からは新しい高校生活がスタートします。そして、次の新しい出会いが待っています。新しい環境で新たな仲間をつくり、または新たな分野に挑戦してみるのもいいかもしれません。別れや出会いを通じて、私たちは少しずつ成長していきます。ときには辛いことや苦しいこともあるでしょう。しかし、皆さんには、新しい出会いに向けて少しの勇気があれば、人生がより豊かになることを思い出していただきたいと思います。
PTA書記 鈴木友則
96 令和4年度 第3回OYAZY’s会「残す」
2月18日(土)
令和4年度OYAZY‘s会最終回が開催されました。
今回のミッションは、普段こどもたちにはなかなかできないであろう、教室のエアコンのフィルター清掃と高い位置の窓ふき。
まさにPTA版「附中ピカピカプロジェクト」です。
ご家庭からお持ちいただいた脚立やハンディクリーナーを用いて行われたエアコンのフィルター清掃では、途中、刷毛やブラシを用いることが効果的であることの発見もありましたが、校長先生はじめみなさん、ほこりまみれになっての作業となりました。

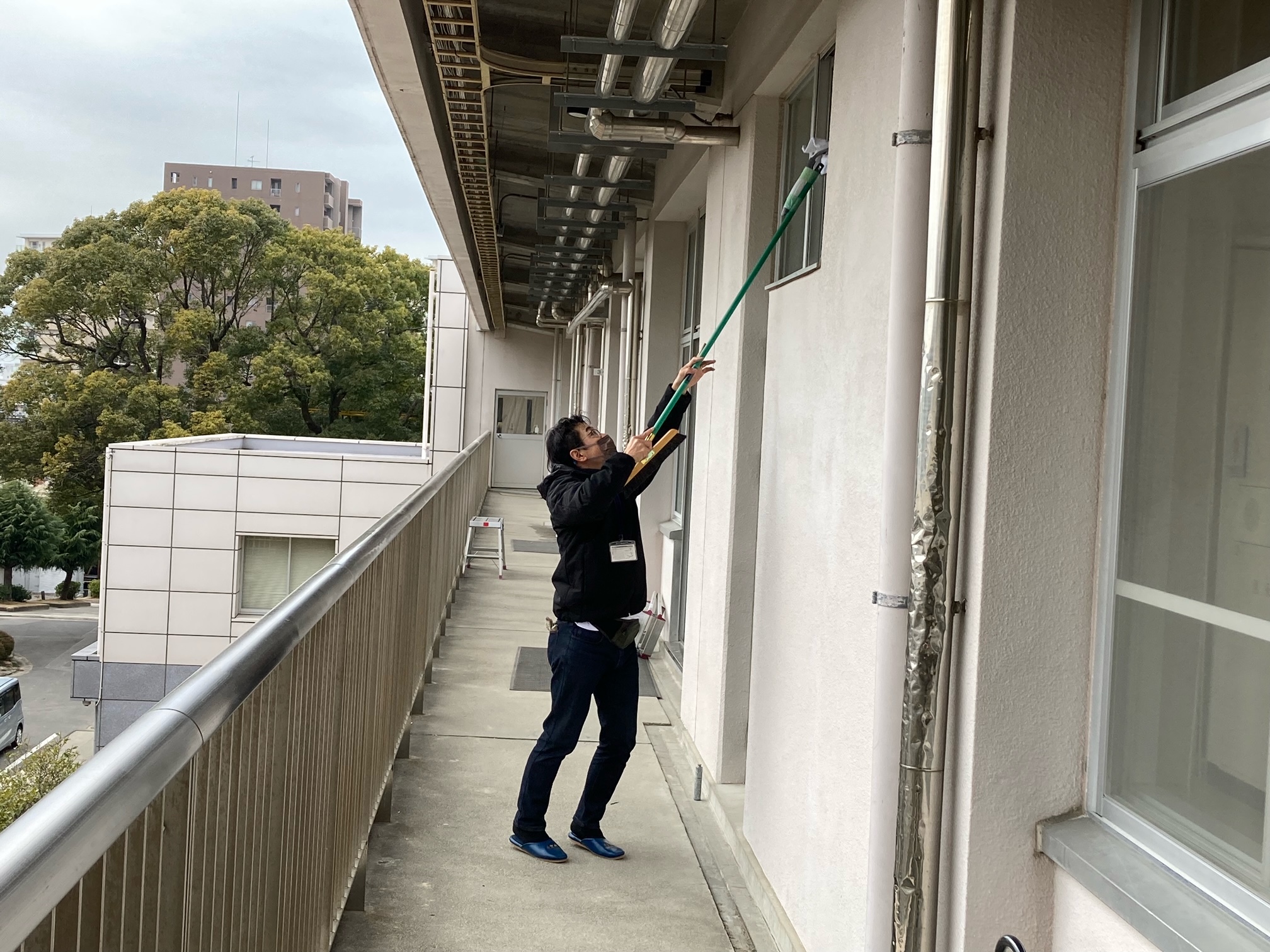



いつもは煩わしさも感じるマスクですが、この時ばかりは大助かりでした。
フィルターが目詰まりしているエアコンでは、冷暖房の効率が低下し、電気の使用量が増えるとのこと。
電気料金が高騰している昨今、清掃したことで節電、電気代の低減にもつながれば良いのですが。
教室北側の窓ふきでは、手の届かない範囲が気になり、工夫して道具を自作する姿も見られました。
附中生同様に、保護者のみなさまが工夫し、協力する姿が印象的でした。
後半は育朋館での紙ヒコーキ飛ばし。
晴天のもと運動場でヒコーキを飛ばしたかったのですが、天候もいまいちで育朋館内での開催となりました。
折り紙でヒコーキを折る姿、試験飛行をする姿はこちらも真剣そのもの。
ルールはシンプルに一番遠くまで飛ばした人が勝ち。



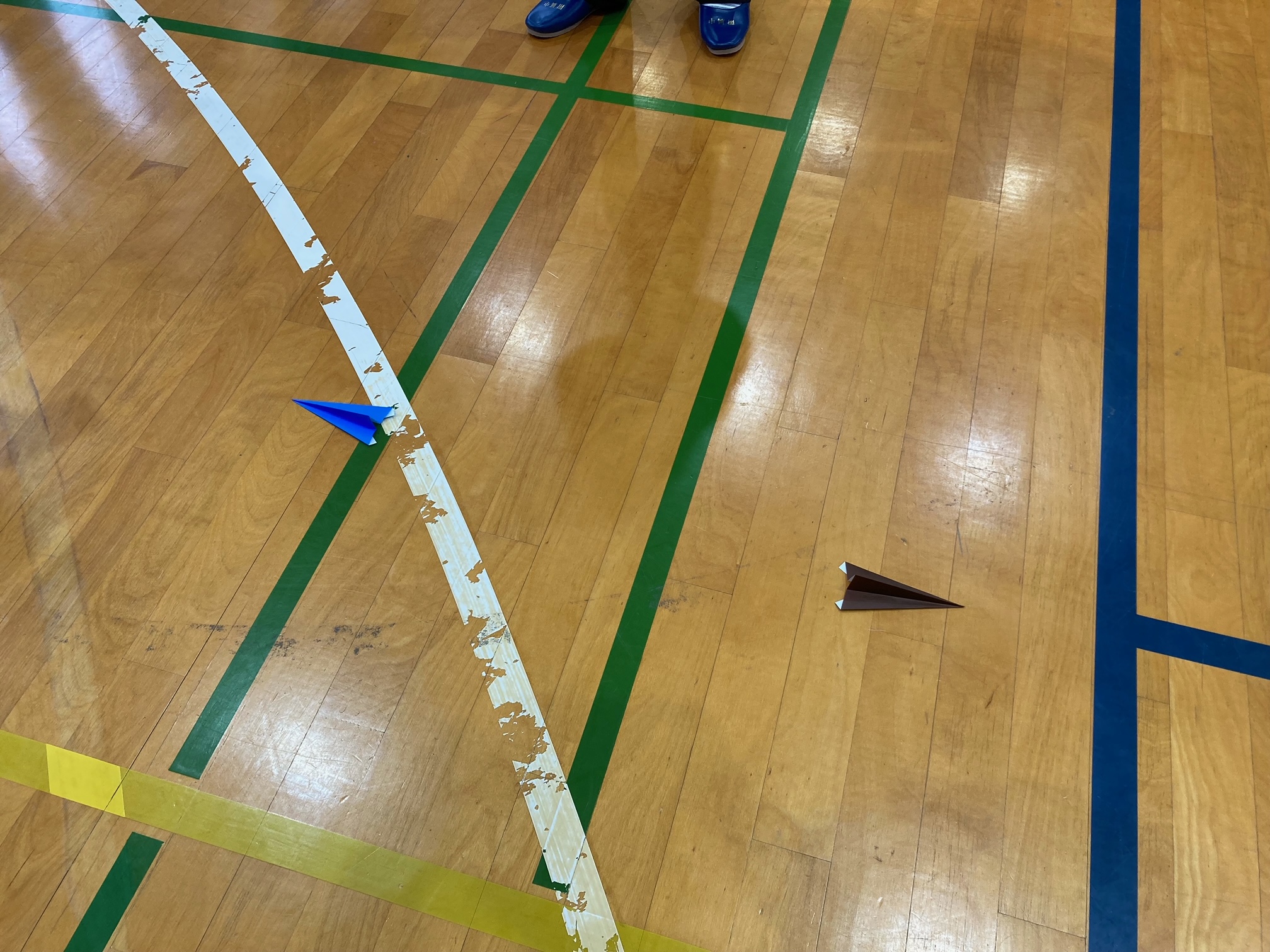
果たして優勝は誰の手に?
結果に興味のある方は、PTA役員もしくは当日の参加者までお尋ねください。
ちなみに、気になる記録ですが、舞台からちょうど育朋館の中央を超える辺りまで飛びました。
令和4年度のOYAZY‘s会は、「学校のために何かをしたい」という方はもちろん、学校を見る機会が減っているコロナ禍において、「学校とゆるく関わりたい」、「スポ懇、文化セミナーに参加できない」といった皆様の受け皿にもなるべく、テーマをもって、その時に相応しい作業と交流を目的としたゲームを組み合わせた企画をしてまいりました。
名前も「OYAZY’s会(※読み方は未だ統一できておらず。)」とすることで、父親に限定しない活動の浸透を図りました。
「見つける」と題して行った第1回 。
学校周辺での清掃作業を通して、通学路等周辺の様子を知ってもらうだけではなく、チームで学校探索をすることで、自分たちで改善できる課題(補修すべき箇所等)を見つけていただきました。
第2回「整える」では、第1回で見つけた課題の解決を図るべく、美術館前渡り廊下のペンキ塗りをしていただきました。また、体育大会を直前に控えてのグラウンド整備は恒例となり、今年も立派なグラウンドに仕上げられました(長縄跳びで確認!?)。
そして迎えた今回。テーマは「残す」。
エアコンのフィルター清掃と窓ふきを行ったことで、子どもたちに「明るい陽射し」と「きれいな空気」が残せたのではないかなと思います。紙ヒコーキ飛ばしでは、笑顔とともに作業以上に真剣な眼差しも見られました。
毎回、多くの皆様にご参加いただき、本当にありがとうございます。
そして、皆様の附中生活の思い出のひとつとして「残る」OYAZY’s会となっていれば、うれしい限りです。
残念ながら参加いただけなかった皆様、来年度タイミング合うようでしたらぜひご参加ください。きっと何か「気づき」があるはずです。
最後になりますが、今回も事前準備だけではなく、当日も多くの先生方に御協力をいただきました。
この場をお借りしてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
令和4年度PTA会長 舩山哲
95 岡崎市PTAコーラスフェスティバル
第41回岡崎市PTAコーラスフェスティバルが岡崎市せきれいホールにて3年ぶりに開催された。2年間フェスティバル中止という悔しさをばねに、今回の演奏会は絶対に成功させたいという市内小中学校のPTA合唱クラブの皆さんと想いは同じだ。
演奏が始まるとそれぞれ合唱部の歌声が響き渡り、心を動かされる瞬間だ。
次から次へと歌い終わる中でトリを務めることになった附中コーラスは大丈夫だろうか?ホール全体に響くのだろうか?本番を迎えるにつれ少しずつ緊張してきた。でも大丈夫。指揮者の千晶先生のもと練習に練習を重ねて出来ることは全てやった。人数はどこよりも多い。だからきっと上手くいく。
第1曲目は『Triangle』女性パートのみで歌う。皆さん、笑顔で力強くそして何より楽しんで歌っている。いやいや感心している状況ではない。次は我々男性パートの出番。段差はゆっくりとそして落ちついて。舞台に上がるとライトで眩しい。手に汗握る瞬間。
光の中で観客の視線を感じる。そして2曲目『手紙~拝啓十五の君へ~』が始まった。
「とくかく笑顔で女性パートを支えるような気持ちで」という千晶先生の言葉を心の中で反芻した。その甲斐あって大きなミスはなく各パートが互いのパートを聴きあい素敵な音色を奏でることができたと思う。3曲目の『さようならみなさま』は全員合唱とされていたので気楽に考えていたがこれもまた舞台上で注目を浴びていたので気が抜けなかった。途中、少し危ないところもあったが何とか乗り切れた。


こんなドキドキする経験が出来たのも男性パートのために練習する場を準備して頂き、またチームをひとつにまとめて下さったコーラス部長の千種さん、そしてスタッフの皆様のお陰。感謝しかない。そしてピアノ伴奏の服部さんも絶対に失敗出来ない状況での演奏、頭が下がる。


そして最後に男性パートの暁生さん、河村さん、そして船山さんの参加は心強かった。お陰でなんとか女性17人の力強い歌声を支えることが出来た。
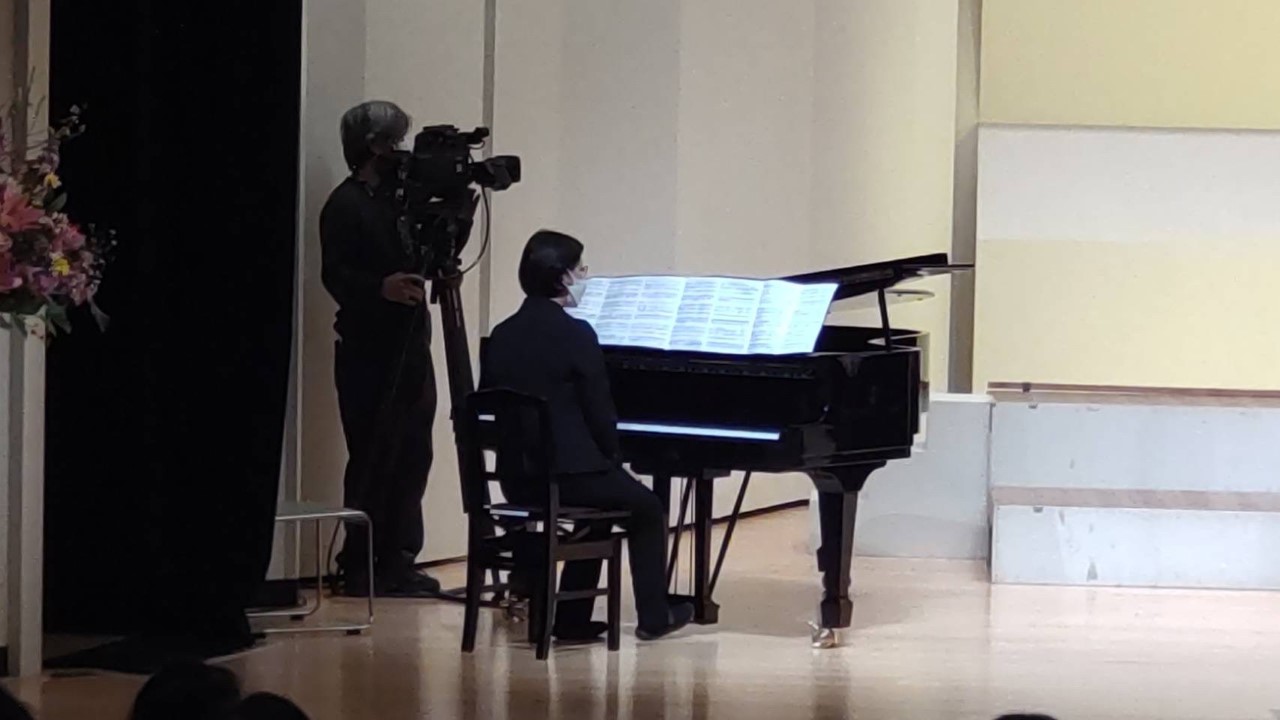

演奏会が終われば何もなかったかのようにまたいつもの日常に戻っていくと思う。しかし、この興奮と感動は思い出のアルバムの1ページとしていつまでも忘れることはないだろう。
PTA書記 鈴木友則
94 附中生であることを誇りに思って―20歳の集い―
皆さまこんにちは芝原です。
令和5年も引き続きPTA活動にご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。私事ですか、長女が先日1月8日に成人式を迎えました。『20歳のつどい』と名称は変わりましたが、無事にこの日を迎える事ができましたことを周りの方々に感謝いたします。初めてのことではありますが、何事も子どもの成長を祝う日がこんなにも喜ばしいことなのだなと感慨深く思いました。
せきれいホールで行われたお式ですが、附中を卒業してから5年ぶりの仲間との再会、先生方との再会に歓声があがっていました。様々な状況の5年間を経ての再会は、とても刺激的だったことでしょう。
20歳という節目に、仲間との再会があり、日常から一瞬で附中生にタイムスリップできたのではないでしょうか。それぞれの進路に進んでも附中魂は生き続け、自分自身の核となっていると思います。そう感じたのは、20歳のつどいの後の附中での集まりでした。中心となる子たちが積極的に企画をして、先生方や仲間と交流する時間を設けてくれました。

普段の生活で忙しい中、行動を起こして実行する。また、それを最大限に楽しむ。素敵な子ども達の姿がとても頼もしくみえました。そこにも、状況を理解してくださり温かく協力してくださる先生方がみえました。いつも味方になり支えて下さった先生方に改めて、感謝申し上げます。
集いでは、貴重な先生方からの話を胸に刻み、新たに20歳としての自覚といつまでも附中生である。という誇りを再確認できたのではないでしょうか。かけがえのない仲間との再会。今回は会うことができなかった仲間も、永遠に附中生です。附中生活で培った感性に胸を張って、今後も日常生活を潤わせていって欲しいと思います。いつまでも応援しています。
令和4年度PTA副会長 芝原明恵
93 2023年もよろしくお願い致します。
皆さま本年もよろしくお願い致します。
2023年は、少し大袈裟かもしれませんが、本校及び本校PTAにとって更なる団結と飛躍が求められる1年となります。
学校行事に加えて、8月には、全附連東海地区研究協議会・実践活動協議会が本校幹事のもと開催されます。
東海4県にある国立大学附属学校21校の教員、PTA役員等が岡崎市に集結し、教育現場での取組やPTA活動について意見交換を行います。
NHK大河ドラマの舞台にもなり、脚光を浴びるであろう今年の岡崎市。
その盛り上がりにもあやかり、全附連東海地区研究協議会・実践活動協議会の成功を収め、2023年の本校及び本校PTAの活動が充実することを期待しております。保護者の皆さまには、例年以上のお手伝いをお願いさせていただく機会があるものと思われます。
ご理解をいただくとともに、できる範囲でのご協力をよろしくお願い致します。
さて、1月15日には、令和5年度入学者選抜検定が行われます。
そして同日、3年ぶりに岡崎市民駅伝が開催され、本校男子チーム、女子チームが出場します。
コロナ禍での開催、声を出しての応援は控えるよう求められていますが、友達やその家族の姿が視界に入るだけでも選手の力になることは間違いありません。
ご都合のつく方は、ぜひ、寒さ対策、感染症予防策を施した上で沿道での応援をお願い致します。
ちなみに、附中PTAチーム(一般男子2部)も出場します。
※附中RT2022-2023(附中PTAランニングチーム)
また、附中PTAチームではないものの、市民駅伝に参加される保護者の方もいらっしゃいます。
もちろん、こどもたちへの応援優先ですが、こちらの応援もよろしくお願い致します。
選手の皆さん、楽しく、かっこよく走り切ってください!
令和4年度PTA会長 舩山哲
92 どんな未来を作り上げますか?(令和4年度PTA教育文化講演会)
11月22日 育朋館にて令和4年度PTA教育文化講演会が開催されました。
今回ご講演くださいましたのは附中卒業生であります岡田シギー様です。
岡田様は株式会社SEG JAPAN代表取締役・ホスピタリティマイスター・クイジーンクリエーターとしてご活躍です。
『現役附中生と見る未来予想図~貴方はどんな未来を作り上げますか?~』と題してご講演頂きました。
会長の挨拶に続き早速講演は始まりましたが、穏やかな雰囲気からのスタートです。
自己紹介をされているお話からすでに生徒たちからは笑いも起きています。
話がすすんでいくと、驚いたことに岡田様自ら壇上から降り生徒のもとへ歩み寄りインタビューをはじめられました。
もうこれには生徒も大爆笑。生徒全員の目や耳は岡田様にくぎ付けです。
岡田様はこのようにおっしゃいました。
附中を卒業してから気付いた附中のすばらしさがあると。岡田様は卒業されてから約20年になられますが、話せば話すほど附中愛がどんどん溢れ出てきます。
もう話が止まりません。
そして会場内のすべての人が岡田様の話の虜になっていきます。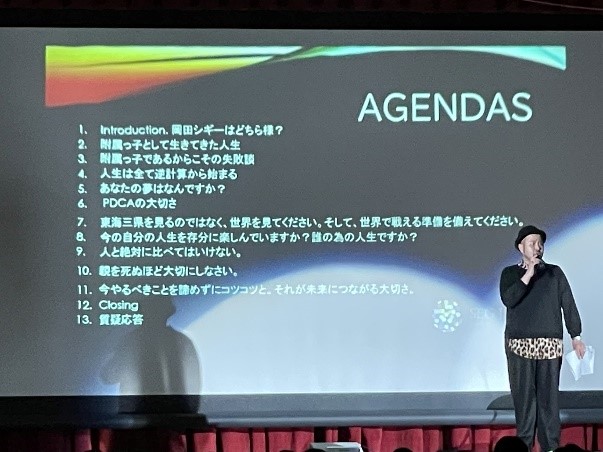
そこで何度か出てきた言葉は『夢』。
一度抱いた夢はそう簡単に諦められるものではないとも。
そして夢を実現するためには一心不乱に頑張らなくてはいけない時があるということも。
人生はすべて逆計算。夢を実現するために何時までに何が必要で、何をしなくてはいけないのか。
PDCAの考え方がとても大切であることも。
たくさんある夢の中で何からはじめて良いのか迷ったときはブレインストーミング、などなど。多くの学びをこのご講演で与えて下さいました。
岡田様と楽しく過ごせた講演もあっという間にお時間となってしまいました。
最後に生徒からのいくつかの質問に答えて下さいました。
ここでもやっぱり生徒のところまで行って目を見てお話をしてくださいます。
岡田様は附中生が大好きなのですね。
そして附中が大好きなのですね。
そのような岡田様の附中愛にいっぱいに包まれたご講演をいただきました。
令和4年度 PTA 近藤健児
91 1年生学年保護者会
皆さま こんにちは
1年学年代表の平手です。
11月11日に1年生学年保護者会が開催されました。
今回は岡崎警察署 生活安全課から山本様をお迎えし、近年、社会問題になっているネットモラルについての講演会を実施しました。
今は中学生の8割が自分専用のスマホを持つ時代、私たちにとっても避けて通れない話です。講演ではネットに潜むトラブル例やその対処法について具体的に紹介して頂きました。
私たち保護者はスマホの無い時代に育ちました。今回改めて子どもと一緒に学ぶことができたと思います。家族で今一度安全に使うルールやマナーを話し合うことが大切ですね。
続いて、先生から学習、生活についてのお話がありました。
学習については、
①計画的に取り組む事の大切さ
②アフターケア(結果を冷静に受け止め、なぜ間違えたか?を分析する事)の重要性
③上記のサイクルをしっかり回す事
等についてアドバイス頂きました。
生活面では服装の自由化についての確認などがありました。
親子で学ぶ良い機会になったと共に、行事では感じ取れない普段の子どもたちの様子も見ることができ、貴重な時間となりました。ありがとうございます。
1年学年代表 平手恵子
90 2年生学年保護者会
今年度、2年学年代表を務めております 平野一代です。
11月9日に2年生学年保護者会に参加しました。
まず、学年主任の渡邉先生から、自然体験学習のお話がありました。ドキドキワクワクで臨んだ登山の様子に感動しました。みんなの成長を感じるお話でした。
次に修学旅行についての説明が、実行委員の生徒からありました。
テーマ『Action』、今までの活動、これからの展望をわかりやすく説明していました。今からとても楽しみです。

最後に『Lifework』の代表生徒の発表がありました。4名の生徒が1年生の時から追究したことを話していました。個人的には、しっかり催眠術にかかり、よい体験をさせていただきました。これから更なる追究を頑張ってほしいです。
いつも支えてくださっている先生方に感謝するよい時間でした。ありがとうございました。
2年学年代表 平野一代
89 岡崎市 PTA研修会
皆さまこんにちは 芝原です。
去る11月1日岡崎市PTA連絡協議会のPTA研修会が開催されました。
『親子で始めるハッピートークトレーニング』と題して、講師に池崎晴美先生をお迎えし充実した時間を体感する事ができました。会場では研修に参加された皆さまと手遊びをしました。童心にかえりじゃんけん大会です。まずは舞台上の先生のグー、チョキ、パーに対し、あえて「後出しで勝つ」ということをしました。次は「後出しで負ける」です。勝つか負けるか、当たり前ですが「勝つ」方がとても気分がよくなりますよね。じゃんけんで勝つときのように、気分よく家庭でも、家族や子供に接するときには気分のよい言葉を発することが重要です。たとえば「今日もおつかれさま」や「よくがんばってるね」などプラスの言葉です。これを先生はハッピートークとおっしゃっていました。
ハッピートーク®とは話し方、コーチング、脳の動きを組み合わせたトレーニングです。実践やワークを行い、わかりやすく、すぐに役にたつように考えられています。毎日の実践により、親子のコミュニケーションや人間関係が豊かになっていくと素敵な言葉の魔法です。
ハッピーになるためのノウハウを紹介されていたので、少し掲載させていただきます。
① 脳は上からプラスの言葉を入れると使わない言葉は下へ移動する。プラスと言 葉のインプットは朝と夜が一番効果的
② 言葉は自律神経を介して身体に影響を与えるのだそうです。良い言葉を使うと言葉にピッタリのホルモンが分泌する。
私も家族でハッピートークを試してみました。「〇〇かわいいね」「いつもありがとうね」はじめはとっても恥ずかしいですが、少しずつ家庭で、子供に笑顔が増えてきた気がします。
皆様方のご家庭でもハッピートークいかがですか?まずは恥ずかしがらずに、そのご家庭オリジナルのハッピートークを考え実践してみてくださいね。きっと今までとは少しちがった笑顔がこぼれるご家庭のきっかけになると思いますよ。
88 兵どもが夢の跡
晴天の中開催された今年の体育大会は、Bグループの完全優勝で幕を閉じました。
スポーツ観戦や実際に運動することが好きということもあるのですが、私にとっても体育大会は一大イベントです。
観戦歴を重ねると、この種目はこの子、このチームに注目しようという見方も出てきます。
皆さんはそんなことありませんか?
今年も期待どおりに活躍した子がいました。
ガッツポーズは喜びに満ち溢れ、チームに笑顔をもたらしました。
まさに絵になる瞬間。
バトンパスがうまく行かなかったチーム、残念ながら失速してしまった子もいました。
悔しい表情や涙とともに、隣にはチームメイトを慰める友達の姿。
仲間に共感し、フォローする姿には胸が熱くなりました。
そしてまた、新たな注目選手も誕生します。
足の速い子はもちろんですが、国歌を歌い上げる子、応援団で機敏な動きをしている子、太鼓の達人・・・
それだけではありません。
大勢の注目というプレッシャーのかかる障害物競走でボールをボックスに投げ入れる子、実況放送で大会を盛り上げる子、レースのスターター、スタートブロックをセットし外す子…
こんな子もいたんだ、こんな役割もあったんだと新たな発見をしながら、一生懸命な姿やその子なりの考えや工夫が見て取れると、さらに応援の熱が上がります。
ひとりひとりの役割と活躍を通してみんなで創り上げていることが見て取れる。
そんな体育大会に惹かれているのだと思います。





今年は想定外?のことも起こりました。
風の影響です。
生徒や先生の懸命な努力にもかかわらず、応援合戦の際にはりぼてとNEOがすべて揃うことはありませんでした。
来年は、製作物も万全な状態での応援合戦を期待します。
「自然には勝てない」とよく言いますが、附中生なら何か考えてくれるのではないでしょうか。
勝てなくても「適応すること」はできるかもしれない。
反省会では「完全優勝」ならぬ「改善優勝」という言葉も聞かれました。
1、2年生の皆さんは、今年の体育大会で見たこと、感じたことを来年に生かしてください。
きっと得られるものがあると思います。
PTA会長 舩山 哲
87 コーラスコンクールを終えて
10月25日(月)
皆さま こんにちは
小楠先生から引き継ぎ、2学期から今年度のコーラスクラブ指導者として活動させていただいている加藤と申します。私は、声楽専攻ではないので迷いもありましたが「PTA活動を楽しく、かっこよく」のモットーにとても共感していたことと、これまでのPTA活動で出会えた方たちや先生方と一緒に歌いたい、そしてその想いを子どもたちに伝えたいという気持ちで引き受けさせていただきました。
コーラス部員の皆さまがいろいろとあたたかく受け入れてくださり、短期間でしたが曲(手紙)を仕上げていくことができました。練習のたびに歌声が一つにまとまっていくことや、部員さんの笑顔がとてもうれしく、気がつけば自分が一番楽しんでいるのでは?と思うくらいでした。本番は「気持ちを込めて楽しく歌えたら、きっと何かが伝わる‼」と思っていましたが3年生からのスタンディングオベーションを見て、私たちの想いが伝わったと実感でき本当にうれしかったです。

 コーラスコンクールを終え、子どもたちの本気の歌声、そしてPTAコーラスの余韻に浸りながら、私自身次へ向かうパワーをいただけたことに感謝しております。
コーラスコンクールを終え、子どもたちの本気の歌声、そしてPTAコーラスの余韻に浸りながら、私自身次へ向かうパワーをいただけたことに感謝しております。
皆さんお忙しいと思いますが、あまり練習に参加できなくても、練習の仕方は色々あります。“合唱っていいな” “音楽っていいな”と少しでも感じたり、音楽を通じて仲間と一緒に楽しめたりする場(コーラスクラブ)があることをもっともっと知っていただけたらうれしいです。
さて、次は1月のコーラスフェスティバルです。
岡崎市内の小中学校が参加しますが「楽しく、かっこよく」附属中らしさが出るように練習していきたいと思います。皆さまのご参加をお待ちしています。
PTAコーラス部 指導者 加藤 千晶
**************************************************************
コーラスフェスティバルを終えて
一人ひとりの歌声を重ねる。こんなにも素敵なハーモニーが生み出されるものなんだと改めて感じられたコーラスフェスティバルでした。子どもたちの熱い想いがあふれ、温かい心地に包まれたひと時でした。
そのような中で、今年もPTAコーラス部が先生方と一緒に歌うことができたことを大変嬉しく思います。ありがとうございました。自分たちの歌声にのせて子どもたちに何かを伝えたい。部員一同、年に一度のこの機会を大切に、そして楽しみにしています。これからも子どもたちの歌声、先生方と保護者の歌声が附中に響き渡り続けることを願っています。
拝啓 十五の君へ。十年後、三十年後もあなたが笑顔で前を向き、幸せでいられますように。
PTAコーラス部 部長 千種 亜矢
*******************************************************************
今週末は体育大会ですね。
1年生にとっては初めての!
2年生は、先輩の意志を受け継ぐ大事なチャンス!
3年生は最後の集大成!
それぞれの思いを全て出し切って悔いなく過ごせますように!!
有志を見守っていますね。
PTA副会長 芝原 明恵
86 第72回西三河中学校駅伝選手権大会
10月22日(日)
岡崎市龍北総合運動場で第72回西三河中学校駅伝競走選手権が開催されました。
女子は5区間。1区と5区が3㎞。2~4区が2㎞。
男子は6区間。全区間3㎞。
今年度初めての大会はなかなかタフな距離設定です。
しかも、龍北総合運動場の地形を生かし、起伏に富んだコースは、選手のフィジカル、メンタルの両方を削ります。
文化祭や体育大会の準備で忙しいこの時期、練習も十分にできず、スタートラインに立てるのか不安もありましたが、出場した選手たちはタフなコースに苦しみながらも、堂々と襷を繋ぎました。
そして、補欠となったメンバーもしっかりとチームを支えてくれました。
チームで参加する駅伝には、メンバー全員にそれぞれの役割があります。
レース後のメンバーの表情や会話からは、疲れとともに清々しさも感じ取ることができました。
みなさん本当にお疲れさまでした。

また、当日は、卒業生の先輩も会場に駆けつけてくれました。
先輩の思いが襷とともに引き継がれてゆくというのも駅伝の魅力ですね。
~駅伝部Tシャツについて~
背中の「威」の文字には「堂々と走り切る」という思いが込められています。
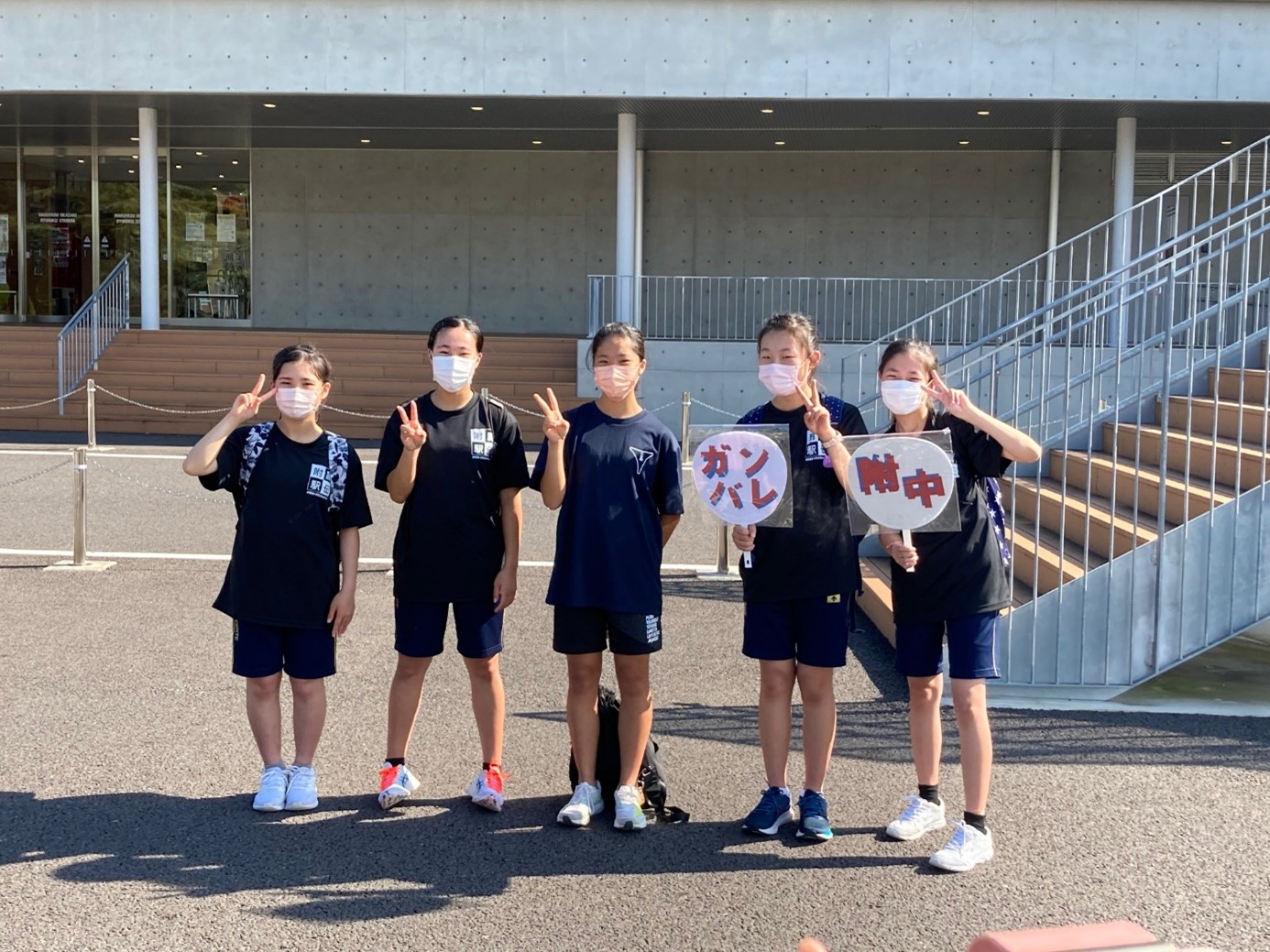
それを囲む「輪」は、駅伝の象徴でもある「襷」をイメージし、チームの「絆」を表わしているそうです。
次の大会も附中らしく、チームの絆を大切にしてがんばってください!
PTA会長 舩山 哲
85 PTA文化展
皆さま こんにちは 芝原です。文化祭2日間、無事に開催出来ました事を、先生方、携わって頂いた方々に感謝申し上げます。
正門には『文化祭』の手書き立て看板が。左側黒板には、子ども達が描いてくれた絵があり とても温かみを感じました。
2日間を終え、保護者の皆さま、子ども達、どんな感想だったのでしょう。ご家庭での温かな団欒の様子が目に浮かびました。
それぞれが、色んな思いを持ち 忘れられない附中の想い出が増えたのではないでしょうか。
色褪せずにずっと色濃く記憶に残ってほしいと思いました。
子ども達が頑張ると同時に、保護者もがんばりました 本日は、文化展を大盛況に導いた文化部の代表として、部長の加藤亜紀子さんからメッセージを頂きました。
本日は、文化展を大盛況に導いた文化部の代表として、部長の加藤亜紀子さんからメッセージを頂きました。
附中文化祭、とっても盛り上がりましたね。
会場で、配信で、様々な場所で子どもたちの活躍をご覧になられたことと思います。
私たち保護者の成果もご覧になっていただけましたか?
文化祭2日目に、電気室にてPTA文化展を開催いたしました。
学習するにはとても良い環境のこのお部屋。
なんとか展示会場にしようと、部員一丸となり変身させました。
文化部員、担当の渡邉先生、他にも多くの方々のご協力とアイデアのお陰で、短期間の開催にもかかわらず、約100名のみなさまにご来場いただきました。
ご都合がつかずセミナーには参加できなかった方も、足を運んでくださいました。
ありがとうございました。
さて、本年度の文化セミナーでは、つまみ細工講座を開催しましたので、参加者のみなさんの作品を中心に、つまみ細工についても、少しご紹介させていただきました。
ずらっと並んだ作品を見ると、同じ材料を使っていても一つとして同じ物が無く、その違いに驚かれたのではないでしょうか。
こんなアイデアもいいな!
こんな風に作ってみたいな!
と、文化展ならではの楽しみもありますね。
江戸時代から続く日本の伝統工芸のつまみ細工も、少しはみなさまにお伝えできたでしょうか。
講師の村田先生からご紹介のあった「子どもつまみ細工コンテスト」に参加者のお子さんが応募し、見事SDGs賞を受賞されました。
この作品は、ご本人の思い出のドレスを使って作られたそうです。
つまみ細工も元々は、使用しなくなった着物を使って作られていました。
「これぞつまみ細工」と、審査員の評価を得られた作品だと村田先生から伺いました。
附中で次世代へと繋がったことが、尚のこと嬉しいですね。
本年度のPTA文化展も、お楽しみいただけましたか?
「以前より小規模ですね」と仰る先生もみえましたが、コロナ禍を経て新しい形を探し出す附中生の姿に学び、新しい文化展を開催できたのではないでしょうか。
この活動も次世代へと繋がりますように。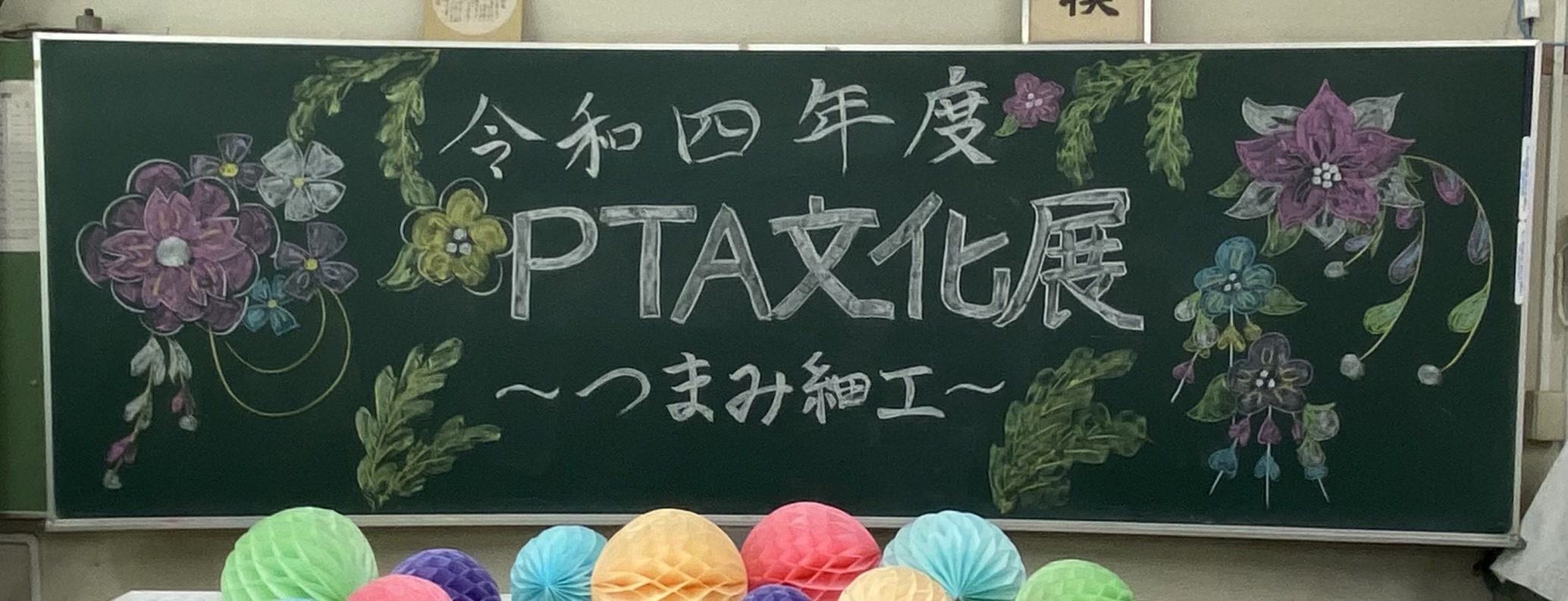

明日以降、コーラス部代表の千種さんと、指導者の加藤千晶さんからのメッセージを載せさせていただきたいと思います。楽しみにおまちくださいませ♪
84 第2回OYAZY’s会『整える』
10月15日
晴天どころか季節はずれの暑さの中、第2回OYAZY‘s会が開催されました。当日の様子を紹介させていただきます。
第3回も企画中。多くの保護者の皆様のご参加をお待ちしております!もちろん、はじめての参加となる方も大歓迎です。
■附中OYAZY’s会 「附中園芸」
高校野球の聖地「甲子園」
高校球児のハレの舞台を陰で支えるグラウンド整備のプロ集団がいる。
その名は「阪神園芸」
附中の聖地「附属中グラウンド」
附中生のハレの舞台を陰で支えるグラウンド整備のプロ集団がいる。
その名は「附中園芸」



我ら「附中園芸」の想いは一つ、
附中生のハレ舞台「体育大会」で、練習の成果を発揮し、クラス・グループで一体となり、みんなが輝ける環境を作ること。
それに向け、スポンジで水を抜き、新しい土をいれ、平らにならし、石やゴミを拾い、プロフェッショナルなグラウンド整備を行いました。
体育大会では一人ひとりの役割があり、応援を作り上げ、競技を行います。
私たち「附中園芸」(親)もその中の一つの役割として、生徒の皆さん、先生方とともにあります。
みんなが輝く姿、楽しみしています!
PTA会計 柴田 健史
■附中OYAZY’s会 「附中塗り」
美術室前の渡り廊下を丁寧な仕事(ペンキ塗り)で整える!
※第1回OYAZY’s会で見つけた課題の改善のための作業になります。
絶好のペンキ塗り日和の中、皆んなで一致団結、楽しみながらも真剣な表情で、作業をして頂きました。
最初は手探りのスタートでしたが、要領を掴んでからは、スムーズに三度塗りをこなし、プロ並みの仕上がりに!






イメージが一新され、爽やかな渡り廊下に生まれ変わりました。
多くの子供たちが笑顔になってくれるといいな〜。
これからも、皆で力を合わせて、素敵な学園にして参りましょう!
令和4年度PTA 監査 牧原 広和
■グラウンドコンディション確認?
最後は整備したグラウンドのコンディション確認も兼ねて参加者有志による長縄を行いました。
記録は9回!ケガなく無事に飛び終えました。
10月29日に開催される体育大会に向けて準備万端です。


83 全附連 70周年記念式典
子どもたちとこの国の未来のために ~附属がこれまでやってきたこと、これからやっていくこと~ 』を開催スローガンに、附属学校PTA全国組織である全附連主催で「PTA研修会 第13回全国大会(70周年)」が開催されました。
日時:9月30日~10月1日 会場:ハイアットリージェンシー東京
秋篠宮皇嗣同妃両殿下のご台臨をいただき、今まで経験したことのない厳戒態勢での開会式に臨みました。複数回、私服警官と思われる方のチェックを受けやっと入場です。入場後は数十分出入り禁止という厳粛な雰囲気の中で開催されました。
講演・分科会やディスカッションなどが以下のように2日間にわたりびっしりスケジューリングされており、すべてを吸収して帰ろうと身の引き締まる思いで参加しました。
【1日目】
〇記念講演 岸 博幸氏 「SDGsと日本の未来、今教育に求めること」
〇特別分科会 「GIGAスクール構想 ~ICTを活用したこれからのPTA活動~」
〇分科会 1 「学校の働き方改革と今後の地域部活動の在り方」
○分科会 2 「感染症から未来を守る」~コロナだけではない感染症の話~
〇分科会 3 「かしこさと非認知能力の育成の秘密」
〇分科会4 「みんなの放課後に音楽を!」~元PTA会長が広げる余暇の楽しみと笑顔
【2日目】
〇齋藤 孝氏 講演 「生きる力を育てる学力」
〇省庁行政説明及び全附 P 連活動報告
〇パネルディスカッション 「SDGsから考える〜附属のこれまでとこれから〜」等
勉強させていただいたことは少しずつPTAの企画・運営に反映させていただくとして、
ここでは今回の研修で特に印象に残ったことをお伝えしたいと思います。
【世界最先端の教育とは?】
慶応大学岸先生の講演より『世界最先端の教育』のお話がありました。私なりに骨子をまとめてみましたのでよろしければご参照ください。
- 問題・課題を自分で設定、定義する能力を身につける
⇒学校にいる間は、学校が問題や課題を提示してくれます。しかし、いざ社会へ出るとだれも問題を提示してくれません。自分で世の中の変化を見つけ出す能力。これが社会を生き抜く能力として大事なひとつです。
- クリエイティブな問題解決能力
⇒現代はどんなことでもネットで検索すれば、答え(らしきもの)が出てきます。しかしネットで見つかる答えはクリエイティブ(創造的)ではなく、ステレオタイプ(きまりきった答え)がほとんど。自分の頭でクリエイティブな考えをしていかないと新しい変化の時代に対応できない。次世代のリーダーは①で見つけた課題をクリエイティブに解決していく能力を身に着けたい。
- チームで解決を図るためのコミュニケーションが必須
⇒デジタル全盛の現代では、SNSやWEB上のやりとりが多くを占め、リアルコミュニケーションが不足している。さらに、リアルコミュニケーションを避けるような動きさえある。一人で問題解決を図ることは難しい。チームで解決するためにはリアルコミュニケーションが必須であるとのことである。
上記①~③が世界最先端の教育の要諦とのこと。当たり前のようだが世界のリーダー教育はこの当たり前を子供たちに伝えるために凌ぎを削っているのだ。
これを附中に当てはめてみる。
「問題課題を自分たちで見つけ」
「クリエイティブに問題解決していき」
「仲間とリアルコミュニケーションをとっている」
まさに附中生は、知らず知らずのうちに、世界最先端の教育に触れているのだ。附中の教育方針にあらためて感謝する機会となりました。
岸先生はこうもおっしゃった。「社会はどんどん進化していく。教育ももちろん進化しなければいけないが、生き残るためには『組織』も進化して行かないといけない」
ここでいう『組織』とは学校でありPTAであり、最小単位の組織は家庭ではないでしょうか。この含蓄のあることばを心にとめ、これから子供の卒業までの残り数ヶ月間をPTAを通じて学校に貢献していきたいとあらためて誓った貴重な研修でした。
PTA副会長 髙原 浩之
【参考】全附連HPより
「全国国立大学附属学校PTA連合会創立 70 周年記念式典」秋篠宮皇嗣殿下お言葉
https://www.zenfuren.org/wp-content/uploads/2022/10/20220930_%e7%9a%87%e5%97%a3%e6%ae%bf%e4%b8%8b%e3%81%8a%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%b0%ef%bc%88%e5%85%a8%e5%9b%bd%e5%9b%bd%e7%ab%8b%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e9%99%84%e5%b1%9e%e5%ad%a6%e6%a0%a1%ef%bc%b0T%ef%bc%a1%e9%80%a3%e5%90%88%e4%bc%9a%e5%89%b5%e7%ab%8b70%e5%91%a8%e5%b9%b4%e8%a8%98%e5%bf%b5%e5%bc%8f%e5%85%b8%ef%bc%89.pdf
82 おかざきサタデーナイトマラソン
10月1日に「附中RunningTeam2022-2023」のみなさんと、
「おかざきサタデーナイトマラソン」に参加しました。

9月のメンバーに附中生4名が加わり、10名での参加でした。(結果12位/56チーム)
スタート時はまだ明るく、少し暑かったのですが、次第に暗くなっていき、まさに「ナイトマラソン」といった感じでした。前回よりもずいぶん走りやすかったです。
メンバーそれぞれベストを尽くして、襷を繋ぐことができました。1人で参加する大会よりも絆を感じ、達成感も倍増でした。
一緒に参加してくださった皆さま、応援に来てくださった皆さま、ありがとうございました!
2年学年代表 平野一代
81 オカザキリバーサイドマラソン
9月11日のブログでもお伝えしたとおり、保護者と教員で結成された「附中Running Team2022-2023」がオカザキリバーサイドマラソン(ハーフリレーマラソンの部)に参加しました。
当日は、目まぐるしく天候が変わり、曇り空から晴れ間が現れたかと思えば大雨になることも。足元を含めコンディションの悪い中でしたが、選手6人でしっかりと襷を繋ぎ、完走しました(13位/35チーム参加)。
普段のジョギング以上の力を出せたというメンバーもいれば、冬のランニング、マラソンシーズンに向けて調整段階、これからというメンバーもいるなど、ペースは一人一人それぞれ。しかし、走り終わった後の雨でずぶ濡れの姿と清々しさで溢れた表情は共通していました。
チームとして大会に参加することで、楽しさや達成感を共有し、交流を図っていただけたのであれば、今回の参加にも意味があったのではないかと思います。

次走は10月1日のおかざきサタデーナイトリレーマラソン。残念ながら今回エントリーできなかったメンバーも満を持して参加予定です。
それ以降で新たなメンバーの募集も考えていますので、興味のある方はぜひ!
最後になりますが、悪天候の中、応援に駆けつけていただいた皆様、本当にありがとうございました。沿道からの応援が力になりました。
PTA会長 舩山 哲
80 附中Running Team2022-2023
9月11日夜
仕事からの帰り道を歩いていると、家から外に出て双眼鏡を覗いている人に出くわしました。
明らかに夜空の方向を眺めていることを確認した上で、つられて南東の空を見上げてみると…
そこには満月が! ※正確には9/10が満月。
そういえば中秋の名月と言っていたような。
しかも月の隣には一際輝く星が!
家に帰って調べてみると、それが木星であることがわかりました。
みなさんは月と木星が寄り添う姿を見ましたか。
さて、9月18日(日)朝9時頃から、乙川河川敷で「オカザキリバーサイドマラソン」というランニングイベントが開催されます。
詳しくは → htts://okazaki-rm.net
そこには、6月に行われたフォトロゲイニング(ジョギングの部)に参加された保護者のみなさまを中心とし、教員も加わり結成された「附中Running Team2022-2023」が参加します。
21.0975㎞、6人で襷をつなぎ、完走を目指します。
順位よりも「自分のペースで楽しむこと」がモットー。
お時間のある方、ぜひ応援をよろしくお願い致します。
走ることに興味にある方も、ぜひお声掛けください。
Every day I listen to my heart
ひとりじゃない
~Jupiterより~
自分を信じて
そして チームみんなで 楽しく かっこよく
PTA会長 舩山 哲
79 応援歌
8月19日
現在開催されている第104回全国高等学校野球選手権大会も残すところ準決勝、決勝となりました。スポーツ観戦好きな自分にとって、勝敗はもちろん気になるところですが、それよりも試合の流れやチーム、個人のちょっとしたドラマに心を動かされています。自分都合でしかないのですが、それを求めてか、ここ数年は愛知県予選にも足を運んでいます。全国大会とはまた違った魅力がそこにはあるように思います。今年は、母校の逆転勝利、少年野球をしていた長男の当時のチームメイトの出場にも立ち会えました。
また、附中の卒業生の姿も見ることができました。
守備から戻ってくるチームメイトに声をかけ、ボールを渡す君、外野手とキャッチボールをする君。
君は今、どのようなことを考えてグラウンドに立っているのかな…。
ユニフォーム姿を見ながら、スタンドでずっと考えていたのですが、それは余計な詮索ですね。
輝く姿に、この夏一番のエネルギーをもらいました。
高校野球といえば、斎藤佑樹さんの手紙(一枚の応援歌/日本郵政)がネットで少し話題になっていましたね。
みなさんは読みましたか?
人生いろいろな出来事が待ち受けています。
今まさに不安や挫折と対峙している人もいるかもしれません。
附中でのこれまでの生活、これからの生活が、人生において、皆さんを奮い立たせる記憶になると良いなと思います。
さあ、2学期がはじまります!
PTA会長 舩山 哲
78 市長杯(バレーボール女子)
7月4日
2022.7.2
第75回岡崎市中学校市長杯総合体育大会バレーボール女子(於:中央総合公園体育館)
附中女子バレーボール部は岩津中学校に敗れ、3年生は引退となりました。
3年生のみなさんお疲れさまでした。
そして、ご指導いただいた先生方本当にありがとうございました。

思い起こせば2年前。
当時の1年生(今の3年生)には、ほぼ出場の機会はありませんでしたが、1点を獲るのがやっとというチームでした。
そして迎えた今日の試合。
他校と比べればまだまだですが、サーブ、レシーブなどの技術、声を掛け合いチームでつなごうとする姿に成長を感じました。
対戦相手の岩津中学校には歯が立ちませんでしたが、緊張感のある雰囲気の中で、選手は力を出せたのではないかと思います。
隣の岡崎レッドダイヤモンドスタジアムでは、第104回全国高校野球選手権大会愛知県大会が幕を開けました。
今年も聖地「甲子園」を目指して熱い戦いが繰り広げられます。
「甲子園出場」を目標に掲げれば、それを達成できるのは愛知県で1校のみ。
厳しい世界です。
附中女子バレーボール部は、どんな目標を立てていたのかな?
その目標は達成できたのでしょうか。
試合中そして試合後、コートの外でも輝く姿を見つけました。
唯一の2年生部員が、コートチェンジの際、ベンチの消毒をひとりで黙々としていました。
試合終了後、緩和状態にある写真撮影時にもチームの荷物を抱えて・・・。
プレーする姿、伸び伸びした姿に目が行きがちですが、規律を大切する姿を目にし、清々しい気分になりました。
これからは2年生がチームの中心です。
どんな目標を立てるのかな?
1年生とともに、その目標を達成できるといいね。
これからも附中女子バレーボール部を応援します!

もちろん他の部のみなさんも応援しています!
PTA会長 舩山 哲
77 「Pネット講座」3年ぶりの開催
7月4日
こんなことを聞いてはいけないのかもしれませんが、保護者のみなさま「Pネット講座」ってご存知でしたか?
附中では当たり前のように使われがちな言葉ですが、本格的に開催されたのは3年ぶりということもあり、知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
まずは「Pネット講座」の前に「Pネットバンク」から。
学校での追究を進める上で、子どもの多様なニーズに応えるため、保護者のみなさま等にご協力いただける内容を登録していただくデータベースです。
そして、その内容をこどもたちに還元する場が「Pネット講座」です。
すでにアップされている附中日記の「Pネット講座開催」にもありましたが、2022年度は6月25日に16講座が開催され、多くの保護者のみなさまにご活躍をいただきました。
必要な道具や機材だけではなく、クイズや資料を準備していただくなど、それぞれの講座に工夫が見られ、子どもたちに対してわかりやすく、しかも楽しく技術や知識を伝えたいという思いがひしひしと伝わってきました。
子どもたちの中には、希望していた講座を受講できなかったという子もいるかもしれませんが、前のめりな姿や笑顔を見る限り、普段の授業とはまた違った気づきがあったのではないかと思います。








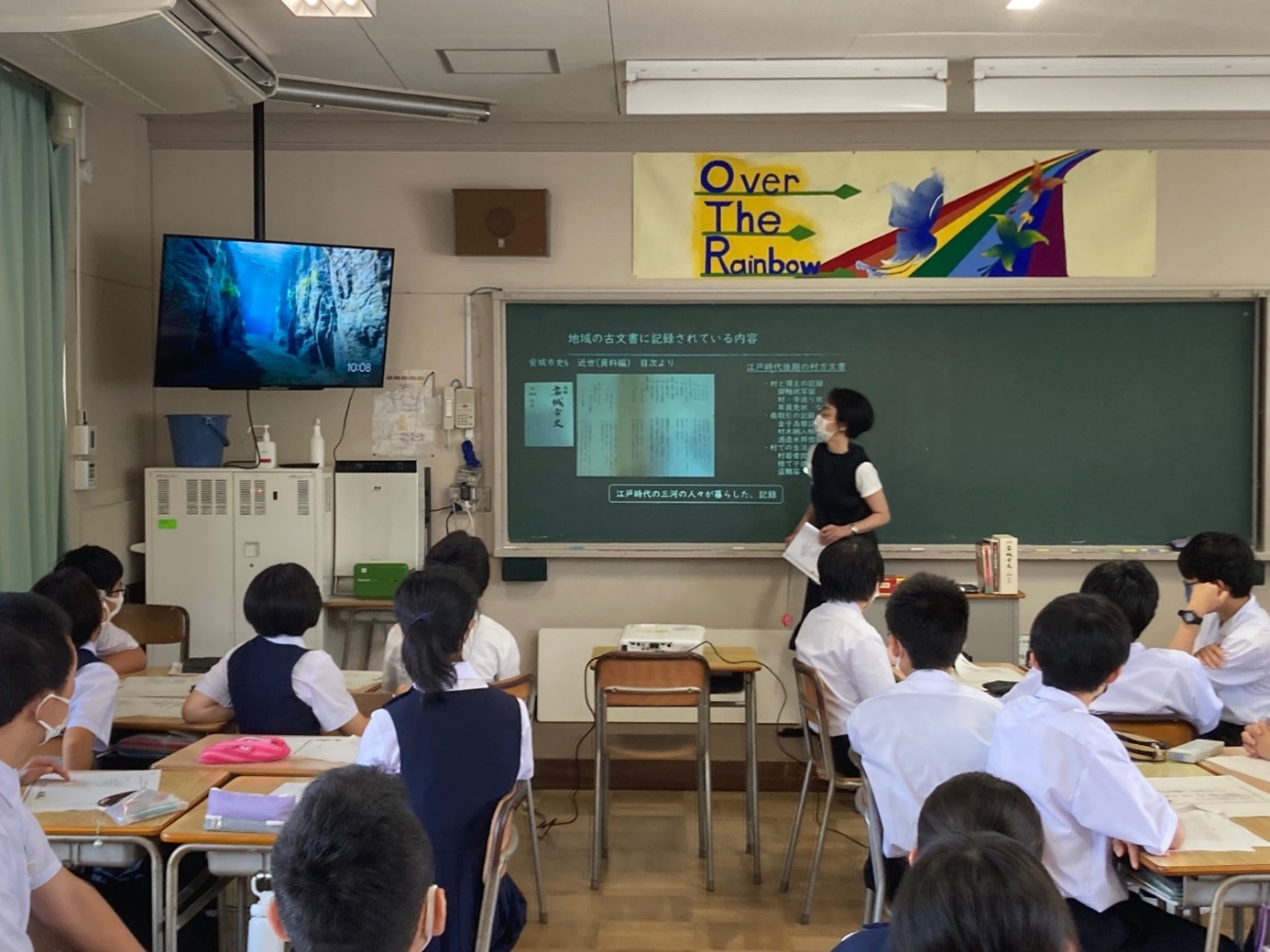
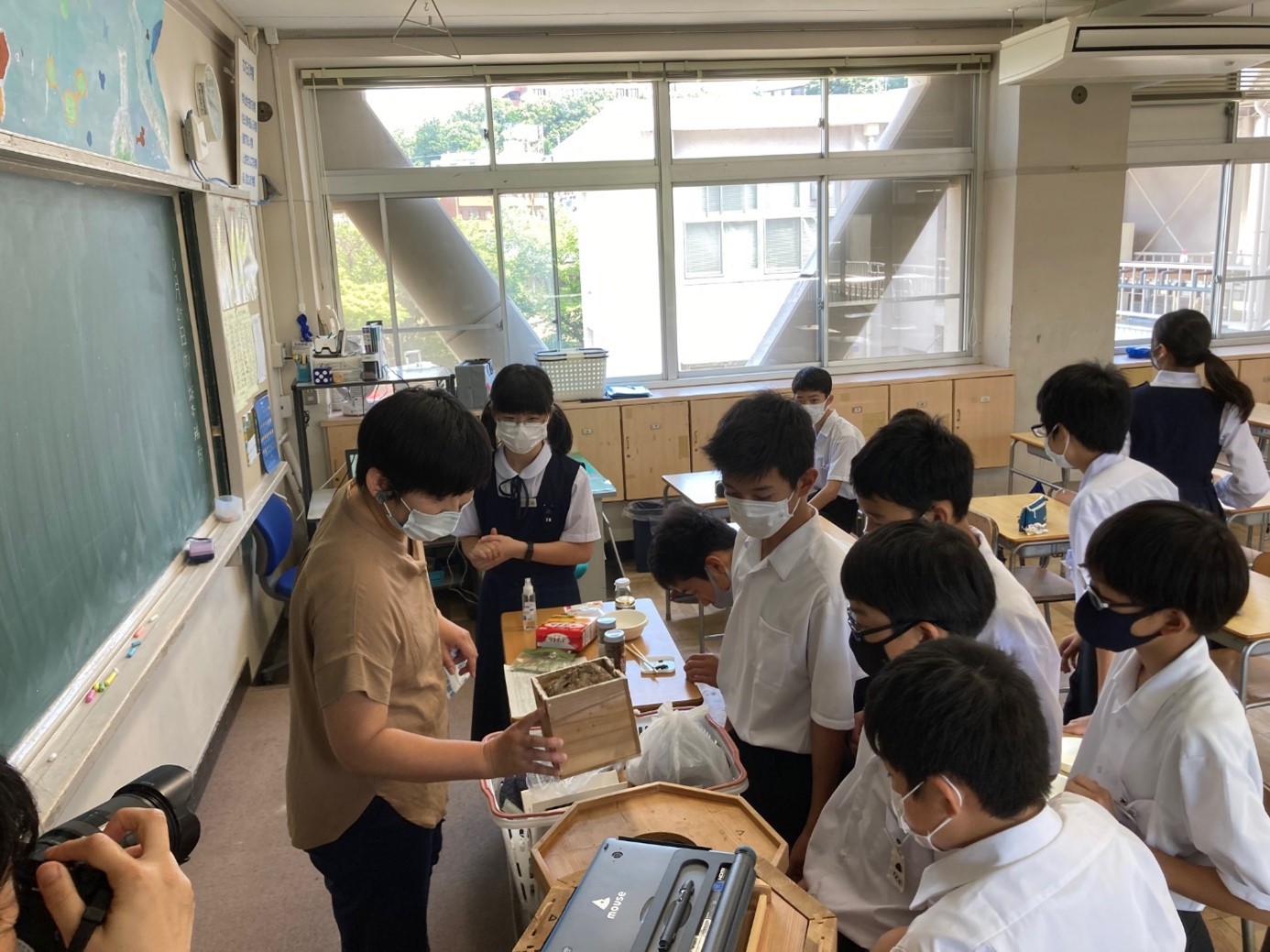
※講師のみなさま全員の写真が掲載できなくて申し訳ありません。
今回の「Pネット講座」では校長先生も講座を開かれていました。
校長先生の講座を受講できる、また、担任の先生の普段とは違う姿(アングラースタイルなど)を見ることができる、これも「Pネット講座」の魅力かもしれません。
講座での校長先生の姿は、保護者のみなさまがきっとイメージするであろう校長先生像とは少し違う姿でした。
もちろん良い意味で!
子どもたちを対象とした講座であり、保護者のみなさまに見ていただけないのは残念ですが、講師を引き受けていただいた方みなさま本当にかっこよかったです!
来年度はさらに多くの方に「Pネットバンク」に登録していただけたらいいなと思います。
PTA会長 舩山 哲
76 「懇親フォトロゲイニング」開催!!
6月28日
皆様こんにちは!
体育部部長の丹羽です。
6月25日に「懇親フォトロゲイニング」を開催しました。
まずは今年のフォトロゲウォーキングの部 優勝 1B-1の皆さんです!

得点は11ポイント
11ポイントは3組ありましたが、捜索時間が1番短かった為、優勝でした。おめでとうございます!
次は記念すべき第1回フォトロゲジョギングの部の皆さんです!

得点は22ポイント
今回は競うことはせず、懇親を目的として走っていただきました。さすが、走り慣れている方ばかりでウォーキングの倍のポイントをゲットしています。
3年ぶりに先生方と活動できることになったためか、ウォーキングとジョギングの部含め140名ほど参加者が集まりました。
予想以上の人数になり、体育部としてはとても嬉しく、地図作りに更に気合が入り今年度は3コース作りました!
更にジョギングの部をつくり、より一層楽しんでいただけるように、万全の体制で臨みました。
しかし、当日は、暑く雷も鳴りそうで、開催に迷うぐらいでした。
外でやることにして決定した後、雨が少し降ってきたりして、どうなるかと思いましたが、皆さん元気に出発しました。
フォトロゲの様子です。









順番にスタートしてゴールするので、待ち時間があります。その間体力測定チャレンジをして待ちます。



みなさん、ゴールした後の顔は、とても笑顔があふれていて、グループの方と和気藹々と話している様子を見て、私もとても嬉しかったです。
表彰式の前には、今泉先生による整理体操!?らしきものをしていただき、とても楽しいものになりました。


集まれる喜びを感じた1日になりました。
PTA体育部長 丹羽由紀子
75 「オススメ本教えてください!」
6月20日
保護者の皆様
いかがお過ごしでしょうか。やっと梅雨入りとなりましたね。
本日、『あなたのオススメ本教えて下さい!』というアンケート用紙を配布させていただきました。昨年度も配布させて頂き、本校の図書室に何冊か入荷させていただきました。中学生にこんな本オススメ!自分は、こんな本を読んで影響を受けた!など教えていただけると幸いです。昨年度も、保護者の方々から回答をいただきまして、とても熱いメッセージに心が温かくなったのを憶えております。オススメ!ですが、必ず読まないといけないではなくて 本も人も出会うべくして出会うのだ!と思います。とても個人的な意見で申し訳ありません。いつ、どんな本に出会うかは、もう運命的です!自分も、今になってやっと出会う本。今後出会うだろう本。様々な本たちにワクワクが止まりません。奇跡の出会いになるかもしれない本をどうぞ、そっと教えていただきたいです。
いつも感じる事ですが、自分が発する言葉は、人にどんな形で残るのだろう。何も残らない事が殆どだろうけれど、知らない間に傷つけてしまっていたり、少し元気を与えていたり。。。本当に、深く考えると、発言は慎重にしないといけないなと 1人反省会の夜を過ごすことも多いです。自分が無力な分、本がそっと寄り添ってくれたり。本よりも、自分が寄り添う事ができているときもあったり。(できているのかな)
子どもたちが、話を聞いてほしい時、認めてほしい時、叱ってほしい時、ほかっておいてほしい時、様々思う場面で うまくやれているかなと考えて、なんだか良い方法がみつからない時に本で読んだ言葉があったなとか。。。頼ってしまう事もあります。そんな心強い存在でもあります。
その時は、悩み解決できなかったとしてもじわじわとあの時の言葉が沁みわたる。そんな発言ができたらな 魔法みたいな事を言っていますが、とにかくいっぱい言葉のシャワーを浴びたなら、少しでもいつかどこかで支えになる!そう思いたいです。
さまざま価値観はありますが、日々考え方や捉え方は変化するし、変化しないと昭和のおばさんの凝り固まった考えだ!と息子にまた言われてしまいます笑 いいんです。変えたくない信念もあり、変化していく価値観もある。何と言われようとも!!
自分がいいな、と感じる事にアンテナを向けて真摯に行動したいと思っています。
話が大分それましたが、様々な年代の方の意見も中学生に知ってもらえるチャンスなのではないかなと思います。配布した用紙でなくても、ご自由に想いを語っていただけたらと思います。保護者の方だけでなく、附中生もどんどん発信してください。
先日、ほんまつりが復活したと聞きました。是非復活させたいと動いてくれた子たち、素晴らしいです。次回は私も呼んで欲しいな(昭和のおばさんオススメ本!あるよ)ほんまつりは、何がよいかというと 参加者が、本当に本が好きだという想いに溢れていて、生き生きしている。そんな姿を間近でみたい。ただそれだけの願望です。推しの本を紹介し合う幸せな時間。いくらあっても時間が足りないですよね 限られた時間の中で濃い内容のひとときが過ごせますように。きっと大人になっても、そのワクワク感は変わらず更に大きくなっていると思います。ぜひ、貴重なオススメ本、ご意見いただきたいと思います。提出は、担任の先生までお願いいたします。 提出に期限は設けていません。今年度いっぱい受け付けます。
PTA図書応援団 芝原
74 新生おやじの会「OYAZY’s会」が始動しました!
6月9日
6月4日(土)
40名以上の保護者の方にご参加いただき、新生おやじの会「OYAZY‘s会」が始動しました。皆様の参加に感謝です。
冒頭の校長先生のお話のように「時代にあわせて変化していく」おやじの会として、保護者男性だけでなく女性にも多数参加いただきました。第一回の活動テーマは「見つける!」です。普段は何気なく通っている附中の通学路や学校のエントランスの様子、校舎内の教室や備品など、「附中生のいない附中の姿」を見る貴重な機会となりました。
◎第一部「地域貢献 地域清掃活動」
「地域があっての附中」の意識を持つべく、日ごろ附中生が通っている学校周辺の道路、ローソンさんの周辺、正門までの上り坂などを学年ごとのチームにわかれて清掃しました。
普段は何気なく見ている道路やバス停など意外に草が生えていたりゴミが落ちています。



正門までの上り坂。周辺道路の清掃を終えたチームがここもきれいにしてくれました。その後は正門のエントランス。附中の顔であるここが意外にも草が生い茂っています。
ビフォーアフターの写真です。とてもきれいにしていただきました。
附中生は気づいたかな?








きれいになるのはとても気持ちがよいですね。参加者同士でお話もでき、地域や学校もきれいになる、まさに清爽活動でした。

◎第二部「校内探索 見つける!」
日頃は附中生であふれている学校内を保護者だけで探索しました。静かな校内は不思議な感覚でしたが、今日は生徒を見るのではなく保護者目線で校内探索をしました。教室や移動中の場所で修繕や清掃できそうなところ、生徒だけでは手のまわらないところを「うつくしく」していくための大人の宝探しのようでした。
クラスごとの連合チームにわかれ各チームにはミッションが。
「クラスの担任の先生の名前(フルネーム)は?」という一見簡単そうなミッションでも、「あの、なんだっけ顔は浮かぶんだけど」といった感じでチームごとに「たのしく」ミッションをクリアしていきました。
ミッションにはチームでの写真撮影も必須。
「かっこよく」写真は撮れましたか?

自然とチーム内の会話も増え、教室・移動中の校内探索も盛り上がってきました。
「ここの板をかえたいよね」「これきれいに塗れるんじゃない?」「高所作業だから大人の出番だね」こんな会話が自然と増え、先生や生徒では気づきにくい修繕や清掃のアイディアが集まりました。



今後は保護者の方からの修繕・清掃などのアイディアを先生方と相談し、次回のOYAZY’s会では「整える!」のテーマで修繕内容や清掃箇所をお示しし、実施していきたいと思います。今回参加していただいた保護者の皆様だけでなく、腕に覚えのある方、もちろん楽しく学校を整えたい方のご参加おまちしております。
今回のOYAZY’s会で保護者の皆様で協力するとこんなにも学校がきれいになり、また様々なアイディアが出るのだととてもうれしく思いました。
次回以降も「PTAをたのしく、かっこよく(うつくしく)」をテーマにすすめていきます。引き続きご協力よろしくお願いいたします。
令和4年度PTA副会長 髙原浩之
73 全附P連第70回総会について(お知らせ)
6月8日
保護者の皆様
本日は、全附P連第70回総会のお知らせです。
愛知教育大学附属岡崎中学校PTAもこの会の会員となっております。
一般社団法人全国国立大学附属学校PTA連合会の総会が以下日程で開催され、その模様がYouTube配信されます。
PTA会員のみなさまで興味のある方は、ぜひご視聴ください。
(一社)全附P連第70回総会
6月11日(土)13:30~16:00
Youtube URL: https://youtu.be/5MYnoKxI8ic

令和4年度PTA会長 舩山 哲
72 PTA活動を楽しく!かっこよく!
6月6日
保護者の皆様
PTA文化部長の、加藤亜紀子です。
6月6日(月)に附中文化セミナー第2日目を開催しました。
ご参加くださった皆さま、お楽しみいただけましたでしょうか。
2日目も、手を動かしつつ、おしゃべりも楽しんでいただきながら、素敵な作品が次々とできあがりました。
ほんの一部ですが、ご覧ください。

他にもアイデアやセンス溢れる作品がたくさんできあがりました。
ぜひ、文化展でご披露いただきたいと思います。
さて、今回は、文化セミナーを通して私が感じたことを少しだけお伝えさせてください。
この2日間の対面開催は、大変有意義なものでした。
大切な目的の一つである、保護者の皆さまの交流の場となったことはもちろん、講師の先生に直接教えていただけることの大切さを実感したからです。
作品作りをしていると、必ず、ちょっとした困り事が出てきます。
どっちの方が合うかな。
ここの微妙なバランスがわからない。
強くってどの位かな。
等々、ちょっとした困り事があったかと思います。
オンライン開催では、やはり限界があり、このちょっとした困り事を解決すべく、歴代の文化部員さんも奮闘されてきました。
本年度はその熱い思いを引き継ぎ、皆さまに楽しんでいただくことを目標に、部員一同で準備をしてまいりました。
今、何を必要としているか、何をすべきか、ご自身で考え行動する。
正しく、PTA活動を楽しく!かっこよく!を体現されています。
そんな部員さんの姿に、講師の村田先生は大変驚かれ、何度もお褒めいただきました。
また、来校される度に「先生方とお母様方がしっかりタッグを組まれていて、本当にすごいですね!」と仰っていました。
お忙しい中、どんな依頼にも、快く対応してくださっている渡邉先生のお姿をご覧になられたからでしょう。
日常を振り返ってみても、私の気付かないところで、たくさんの方が、心を配り、そっと手を差し伸べてくださるお気遣いがたくさんあります。
子どもたちの学びの場が、そんな温かい環境であることに、改めて感謝しております。
また、今回ご都合により残念ながら参加できなかった皆さまにも、ブログを通して、私たちの想いをお伝えできたことに、感謝いたしております。
最後に、村田先生は、コロナ禍でも対面開催をしたいという私たちの思いをご理解くださり、200本以上のひまわりを一点一点手作りしてくださり、ご自身の全ての時間を注いでサポートしてくださいました。
附属中学校の一員になってくださった、村田翠奈先生、本当にありがとうございました。
ご参加くださった皆さま、陰で支えてくださった皆さま、ご協力いただきありがとうございました。
この附中文化セミナーが、皆さまの「暮らしを彩り豊かに」するものとなりましたら幸いです。
令和4年度PTA文化部長 加藤亜紀子
71 附中文化セミナー1日目開催!
6月2日
保護者の皆様
PTA文化部長の、加藤亜紀子です。
6月1日(水)に、文化部セミナー第1日目が行われました。
コロナ禍での対面開催ですので、蜜を避けるため、午前、午後の1日2回、2日間で計4回の開催とさせていただきました。
短期間の募集でしたが、意識の高い保護者の皆さまからたくさんのお申し込みがあり、合計110名の方が参加してくださいます。
1日目は、手島副校長先生、舩山PTA会長もご参加くださり、皆さんと楽しく作品を作っていただきました。
2日目は、山田教頭先生がご参加くださいます。
どんな作品を作ってくださるかとても楽しみです。
本年度は、伝統工芸 つまみ細工を愉しむ〜暮らしを彩り豊かに〜というテーマで、講師の村田翠奈先生をお迎えいたしました。
つまみ細工は、約200年前の江戸時代から続く伝統工芸です。
必死に覚えた、喜多川歌麿さんや葛飾北斎さんも、体験されたのでしょうか。
きっとその時代の方々も、現代の私たちのように、おしゃべりに花を咲かせながら、つまんでいらっしゃったのではと想像してみると、とても身近に感じます。
さて、セミナーでは2時間という短時間で作品を完成させました。
講師の村田先生が、各座席を隈なく回り、丁寧にわかりやすく教えてくださいました。
できあがった作品は、先生がお持ち帰りして見本にしたい!とおっしゃるほど、丁寧に美しく作られていました。
更に、先生も思いつかないような素敵なアレンジをされた作品も見受けられました。
柔軟な発想は、中学生にも負けていませんね。
そして、江戸時代と違うのは、お互いの作品を愛で語り合うだけでなく、ご用意した写真スポットで映え写真を撮影している姿でしょうか。


2日目ご予定のみなさま、ぜひお楽しみに!
今回のセミナーが、皆さまの暮らしを彩り豊かにするものとなりますよう、第2日目も部員一同でサポートさせていただきたいと思います。
令和4年度PTA文化部長 加藤亜紀子
70 PTA活動を楽しみましょう!
5月30日
保護者の皆様
3年学年代表の丹羽です。よろしくお願いします。
5月27日(金)に私学の高校の進路説明会がありました。今回は14の高校の学校行事、部活動、進学先等いろいろな情報がたくさん聞けました。
いよいよ、受験生なんだなっと実感し、あっという間に3年生になってしまったと思いました。
さて、その説明会の前に第2回理事評議委員会がありました。
会の報告を終えて時間がありましたので、所属してる部についての意見と感想をいただくことにしました。
文化部については、6月1日と6日に「つまみ細工」のセミナーが行われます。部会では、その準備で花を作ったり、茎のしまつをしたり参加される方のキッドを作ります。
体育部においては、6月25日(土)に懇親フォトロゲイニングが開催されます。
先日の部会では、学年ごとのグループに分けてコース決めとチェックポイントの写真撮影を終えました。お天気も良く、いつもは車で通りすぎる道も歩いてみるとたくさん発見があり、とても楽しい部会になったと思います。
0から作ることができるので楽しいのですが、やはり「映え」も大切なので、近くで撮ってみたり角度を変えてみたりと一つの写真を撮るのにこだわりました。
感想としては
・お手伝いができることは楽しい
・楽しいので、もっと早くPTA活動に参加すればよかった
・他のクラスの方とも自然と交流ができたのはよかった
・岡崎に住んでいないので、こんなところがあるんだと発見があった
・こんな下準備をしてるのだと評議員になった事で初めて知った
というものがありました。
どちらの部の方にもやってみたら楽しかった。
ということを言っていただけたので、喜んでもらえて嬉しいし、とてもいい雰囲気だと感じました。
PTA活動を楽しく!
を、今年度はモットーとしてますので、保護者の皆様も是非、楽しんで活動していただけると嬉しいです。
令和4年度3年学年代表 丹羽由紀子
69 PTAコーラス部始動!
5月24日
5月20日、音楽室でいよいよPTAコーラス部が始動しました。今日は初顔合わせということで自己紹介がありました。
そこで感じた今年度の意気込みには熱い想いで溢れていました。なぜなら昨年度の練習でリアル開催が少なく、また、文化祭や岡崎市PTAコーラスフェスティバルの発表の場までコロナで中止になったからです。だからこそあの悔しさをばねにリベンジするのだという想いが伝わってきました。また今年度から初参加だけどずっと附属中のコーラス部に入りたかったという新入会員も加わり早くも心はひとつという雰囲気になりました。
私の紹介としては今年度の曲で「手紙~拝啓15の君へ~(アンジェラ・アキ)」の話をしました。実は昔この曲を聞いて私自身が励まされたことがあったからです。そして今度はこの歌で15歳の附中卒業生を励ましたいと伝えました。
「自分の声を信じて歩けばいい」
人はときに迷います。とくに進路などの大きな決断に迫られたときは当たり前ですが、決断したあとも本当にこれでよかったのか何度も自問自答する弱い生き物です。少なくとも自身はそうです。そんなときこそ自分の胸に手をあてて内なる声に耳を傾けてみてください。きっと答えはそこにあるはずです。
また長くなるので紹介はしませんでしたが
「笑顔を見せて今を生きて行こう」も好きな部分です。過去の失敗や未来への不安で前に進めないことは誰でも起こり得ることです。そんなときこそ雑念を振り払い今のことだけに集中すると、心配するほどのことではなかったと思うことがあります。そして今やるべきことを成し遂げると、次に進むべき道が開けることがあります。
さらに眉間のしわを緩め、口角を上げて少し笑顔で絶対に出来るはずだと自信がなくても思い込めば、勝利の女神がほほ笑んでくれることでしょう。
曲についてはそれぐらいにして、スタッフの紹介です。指揮は昨年同様大人気、指導力キレキレの小楠先生。伴奏は癒し系だけど安心で信頼の服部さん。そして最後は元気いっぱいで頼れる代表、千種さん。昨年同様、頼もしいスタッフばかりです。そして忘れてならない、いつも優しく見守る村上主幹教諭。
最後に男性パートについてです。今年度から正式に募集をかけていますが、男性で入会された方は今のところ私を含めてまだ2名と少ないので大募集中です。演奏会は10月21日の文化祭と来年の1月29日の岡崎市PTAコーラスフェスティバルで本番はまだ先となりますが、思い出に残る貴重な経験となるはずです。だから、少しでも興味のある方がみえましたら気軽に代表の千種亜矢さん、または、私、鈴木までお声掛けください。
PTA活動を楽しく。かっこよく。
令和4年度PTA書記 鈴木 友則
68 PTA活動を楽しく、かっこよく、美しく!
5月17日
保護者のみなさま
こんにちは 本年度PTA副会長を務めさせて頂きます、芝原明恵と申します。
どうぞ宜しくお願いいたします。
本年度は、3年ぶりに育朋館にてPTA総会を執り行うことができまして、貴重な経験をさせて頂き感謝しております。時間を短縮しまして、かつ厳かな雰囲気の中 沢山の保護者の方が集まる様子を眺めながら『子どもの通う学校に興味を持ち、真剣に話を聞く姿がすごく素敵だな』そんな事を考えておりました。大切な時期に我が子が、バンバン刺激を受ける場所。その環境を少しでも良くして行こうとする先生方、保護者の方々、こんなに沢山の方に子どもたちは見守られているんだな(当日欠席の方々も同じ想いだと思います)久々に、同じ想いの方々が集まる熱を感じました。
授業参観も学級懇談会も無事に執り行われ、充実した1日になったと思います。ですが、まだまだ交流が欲しいと考えていらっしゃる保護者の方も多いのではないかなと思います。
総会後に配付しました、体育部からのフォトロゲイニングの募集用紙、文化部からの文化セミナーとコーラスクラブの募集用紙、それぞれの部長さんと担当の先生方により試行錯誤されてお便りができました。
現在は、メールでのお便り配信などもありますが、やはり紙ベースのお便りですと、学校長、PTA会長、部長の氏名などが記載され、細部に渡りチェックをして作られた重みがあると感じます。見えないところで色々な人の想いが含まれています。
募集1日目で既に多数の応募があったと聞いております。みなさん、やはり親睦を深めたいという気持ちが大きいのだと思います。その想いに応えるべく、各部の活動でしっかりと準備をして、本番当日を楽しんでいただける様に進めていきたいと考えています。
舩山会長が仰る PTA活動を楽しく、かっこよく!に加えて、美しく! 我々保護者が、楽しんでいたり、かっこよかったり、美しかったり そんな姿を子どもたちは望んでいると思います。憧れる存在!になる事は、永遠のテーマであると思いますが、少しでも、いいな!と感じてもらえるように日々を過ごしていきたいと思います。親も、子どもたちを見て、いいな!すごいな!と感じることが沢山あると嬉しいですよね。
附属中の先生方、附属中の保護者の方々、附中生、お互いが、いいな!すごいな!と認め合えて進んでいける。そんな関係がより深められると素敵だなと思います。
様々なPTA活動が試行錯誤されて楽しいアイデアがたくさん出てきています。御都合にあわせて、無理のない御参加をどうぞ宜しくお願いいたします。
令和4年度PTA副会長 芝原 明恵
67 PTA活動へのご協力をお願いいたします。
5月10日
令和4年度PTA会長を務めさせていただくことになりました舩山と申します。
令和4年5月2日、3年ぶりにリアル開催されたPTA総会には、ゴールデンウィーク期間中であったこと、また、授業参観日であったということもあるかもしれませんが、多くの保護者の皆様にご出席いただき本当にありがとうございました。
残念ながら出席できなかった皆様へ
役員一同、評議員の皆様はじめ保護者の皆様、先生方のお力をお借りしながら、子どもたちの附中生活が充実したものとなるよう、努力してまいります。
1年間よろしくお願い致します。
さて、この場をお借りしてご案内を。
6月1日、6日 附中文化セミナー「伝統工芸つまみ細工を愉しむ」開催
6月25日 懇親フォトロゲイニング開催
すでに文書でもお知らせしておりますが、PTA文化部、体育部の皆様に準備を進めていただいております。
保護者間で交流できる貴重な機会でもあります。
申込みをまだされていない方、ご参加をお待ちしております(※出欠を問わず5/13までに要提出)。
第1回おやじの(OYAZY’s)会も6月4日に計画中。近日中に案内させていただく予定です!
PTA活動を楽しく、かっこよく。
令和4年度PTA会長 舩山 哲
66 ようこそ、附属中学校へ!!
4月8日
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。保護者の皆様におかれましても、お子様の凛々しい姿に慶びもひとしおと存じます。
さて、皆さんのご入学に際し、後藤静香さんの詩をご紹介致します。
『第一歩』
十里の旅の第一歩
百里の旅の第一歩
同じ一歩でも覚悟が違う
三笠山にのぼる第一歩
富士山にのぼる第一歩
同じ一歩でも覚悟が違う
どこまで行くつもりか
どこまで登るつもりか
目標が
その日その日を支配する
富士山は標高3,776mの日本一の山です。同じ山に登るのでも、三笠山と富士山に登るのでは『覚悟』が違うと言っています。高い目標である富士山に登るためにはしっかりとした計画と準備という覚悟が必要なんですね。
簡単に言うと、サンダル履いて、散歩に出掛けて、気が付いたら富士山の頂上に立っていた、何て事はないのです。
ちなみに、附中の先輩、2年生、3年生ならすぐに、三笠山について調べて、三笠山の別名まで知っちゃうんでしょうね。三笠山は奈良県にあり、別名『どら焼き』と言われています。ドラえもんのどら焼きです。横にしたどら焼きのなだらかな膨らみの様な山って事です。
皆さん、三笠山をなめちゃいけないよ。この一週間、まずは三笠山に登る『第一歩』を踏み出して下さい。
私が、皆さんに提案する三笠山、『第一歩』。
その①まずは、来週の金曜日まで、自分の足で時間通りに登校しましょう。
その②忘れ物をせず、提出物は必ず出しましょう。
これが、私から皆さんへ送る、附中生になるための第一歩です。
3年前、ある先生が言いました。
「提出物は、信頼の貯金」
忘れ物をせず、提出物は必ず出す。すると、この子は、しっかりしてるな。頼りになるな。本物のリーダーになれるなって、周りも信頼してくれ、自分自身も、自信を持てる。
この第一歩を来週の金曜日まで是非、踏み出して、続けて下さい。
その先に、皆さんにとっての富士山が見える事でしょう。
教職員の皆様、彼らはダイヤの原石です。
自分自身と友人、そしてこの素晴らしい環境でどんどん磨き上げられ、『変化』を遂げて行きます。
どうか、彼等への教育を宜しくお願い申し上げます。
新入生の皆さん。さあ、附中生活が始まります。はっきりいって、大変です。その代り、めちゃくちゃ楽しいです。思いっきり附中生活を楽しんで下さい。
ようこそ、附属中学校へ!!
令和四年四月八日
愛知教育大学附属岡崎中学校
PTA会長 野中 健史
65、襷
3月31日
2022年3月31日(木)
PTA会長の野中です。
今年度、最後のPTAブログを更新させて頂きます。
皆さんが生まれてから、寄り添ってきた人々。その人々から「聞く言葉」で、皆さんの性格や考え方が育まれてきました。
「○○君、良く出来たね。あなたは本当にお利口さんね。天才だよ。」
常に、大人から褒められてきた人は、「自分は出来るんだ」と自信を植え付けられる。
「○○、お前は本当にダメな奴だ。何をやっても出来ない。」
常に否定され、怒られてきた人は「自分はダメな奴」なんだと、脳内や記憶の奥底に負の財産を重ねてきている。そんなはずはないと頑張れる人がいても、それは極一部。子供の頃から言い続けられたら、自分はダメな奴なんだと思い込んでしまう。皆さんが「聞いた言葉」、「耳に入る言葉」は、それだけ人格にも影響を与えるものです。
では、皆さんが「発する言葉」は、何になるのでしょうか。
皆さんが発する言葉、それは「未来を創る」のです。
新入生が入り、1年生から2年生に、2年生から3年生に進級します。皆さんは「先輩」となります。皆さんの「発する言葉」が新たに入学する附中生の羅針盤となります。附中の未来を、もっと言うと社会の未来を創っていくのです。
私達は3年間のPTA活動を通じて、皆さんが過ごす学園の環境を感じ取り、先生方の協力を得ながら親同士で附中の状況を共有することで皆さんを影ながら支えて参りました。
そして先日、卒業生を送り出しました。
次は皆さんの活躍の時です。附中生が附中生たる所以を常に意識し、行動して下さい。自由とは何か、規律とは何か。東岡崎や岡崎駅、街中で附中生を見掛けた時、輝いている皆さんを見つけられる事を楽しみにしています。
準備は出来ているね。
襷を託します。
卒業生を含む在校生の皆さん、保護者の皆様、そして子供達だけでなく私達の活動を支援して頂いた教職員の皆様に心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。
令和3年度PTA会長 野中 健史
副会長 北村 恭子
副会長 水越 健夫
体育部長3年学年代表 大河内 彩
64、躍動する先輩に学ぶ「誰もが幸せを実感できる未来を目指して」
3月3日
この冬、私は、教育講演会で講演をしてくださった矢野慶汰さんが住む、山形県酒田市へ行ってきました。百五十以上の国を訪れた矢野さんが、どうして山形県で仕事をしているのか、とても興味があったからです。
酒田市に到着すると矢野さんは、シベリアから越冬する一万羽の白鳥がいる最上川スワンパークを案内してくれました。次に、美味しいお米やお酒を紹介してくれました。そこで、鳥海山の美しさや荒れ狂う冬の日本海の怖さを語ってくれました。
そんな時間を過ごしてしている中で、徐々に矢野さんの心の中にある一つの思いが見えてきました。
それは「私たちに与えられた美しい地球をずっと大切にしたい」という思いです。矢野さんは、そのために「この自然が美しい山形県の魅力を多くの人に発信することが大事」「世界各国で経験したことを多くの人に伝えたい」と考えて、旅館を経営しながら、今を全力で生きていることが伝わりました。
この附属岡崎中学校の卒業生である先輩が、多くの世界をその目で見て、自分のすべきことを明確にし、世の中に発信し続けている姿を見て、何か嬉しくなりました。この学校の先輩である矢野さんが、社会の中で主体となり、問題を見つけ、解決のために奔走している。まさにこの学校の授業や行事をとおして学んだことが礎となり、世の中を変えようとしているからです。
矢野さんがこの学校に通われていた当時と変わらず、脈々と受け継がれていく授業や行事へ全力になって取り組んだ皆さんがどんな人になっていくのか、今からとてもわくわくします。
先の見えない世の中を生きていく卒業生の皆さん。この附属中学校で過ごしてきた経験をもとに、これから更に広い視野をもち、「こんなことしたい」という自分探しの旅を思い切り楽しんでください。この三河の地で、ずっと応援しています。
教頭 馬場 健介
63、更なる変化をして『成人式で会おう!!』
3月3日
祝 辞
卒業式開催に際し、ご尽力頂きました全ての皆様に心より感謝し、PTAを代表しましてお祝いとはなむけの言葉を申し上げます。
三年前、この育朋館からスタートした皆さんの附中生活。体育大会、コーラスコンクール、ライフワーク、そして研究授業など、目の前に立ちはだかる壁や課題を一つ一つ乗り越え、達成感を味わった経験は、これからの皆さんの人生の糧となるでしょう。
また、ST、LT、給食・掃除の時間、登下校の時間。これらのほんのちょっとした時間も大切にしてきた友人がいることを忘れないで下さい。皆さんにとってキラキラと輝く大切な思い出として下さい。
『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一、生き残るのは“変化できる者”である。』
進化論を提唱した、ダーウィンの言葉です。
そう。皆さんはこの三年間で変化した。成長した。この場にいらっしゃる保護者の皆様、教職員の皆様も自信を持って言ってくれるでしょう。皆さんは、大きく変化し、成長したと。
今の時代は十代、二十代でも会社を起こして社会に貢献したり、その道の先駆者となっている方が大勢います。皆さんはまさにその十代です。
更なる変化を恐れるな。この三年間の経験を活かして前に進んで下さい。
大丈夫だよ。君達の未来は明るい。
私が附中を卒業して三十年。未だに年に二、三回は附中の友人と集まっています。附中の友人は会うたびに色んな経験の話しをしてくれます。刺激を与えてくれるんですよ。でもね、時には、気分的に今日は附中の集まりに行きたくないなと思う時もあります。それでも、私は行くんです。
「こいつらに負けてらんねぇ」「やったる」。そう自分を奮い立たせるために会いに行くんです。そう思わせてくれる仲間なんだよね。附中の仲間は一生の宝物です。
きっと、皆さんにとっても一生の宝物になります。
皆さんも卒業後、事あるごとに集まる機会があると思います。オフィシャルでは五年後の成人式でしょうか。その時、今、自分はこれに夢中になって頑張っているんだって、皆で胸を張って会おう。更に変化した皆さんに会えるのを楽しみにしています。
教職員の皆様。子供達に、新しい発見をする機会と、ほっと、安心できる場所を与えて下さり、誠にありがとうございました。深く深く感謝を申し上げます。
これからの人生、彼らが大きな壁に直面した時には、恩師として、また、人生の先輩として、どうか彼らの声に耳を傾け、手を差し伸べて頂きますようお願い申し上げます。
保護者の皆様、三年間PTA活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございました。我々の子供達、立派になりました。
最後になりましたが、思いっきり伝えさせて下さい。
卒業生の皆さん。君達と共に歩んだ三年間。最高に楽しかった。ありがとう。そして、卒業おめでとう。
附属中学校 第七四回卒業生 一四五名の輝かしい未来を祈念いたしまして、お祝いの言葉に代えさせて頂きます。
令和四年三月二日
愛知教育大学附属岡崎中学校 PTA会長 野中 健史
62、みんなで集まって練習できる幸せを味わったコーラスクラブ
2月22日
毎年コーラスクラブは、附中祭で先生方と一緒に歌わせていただき、1月に開催される岡崎市PTAコーラスフェスティバルに参加しています。
6月に顔合わせ会は開催できましたが、音楽室で歌う人数を減らしてオンラインでも練習参加という昨年度と違い、今年度は学校で歌えず、全員オンライン個人レッスンが7月から始まりました。Zoomを使い、1人約10分ずつ3年生保護者の小楠先生のレッスンです。最初は個人レッスンが恥ずかしかった方が殆どだったと思いますが、全体練習では指摘してもらえない個別のアドバイスや練習方法を教えてもらえて、とても贅沢な時間でした。
10月に入り、ようやく音楽室での練習が始まり、「ここで合ってるかな?」と不安そうに音楽室を覗くメンバー、「久しぶりーー!!」と元気いっぱいに入室するメンバーなど、オンラインではなく直接会えた時、嬉しすぎてみんな一気にテンションが上がりました。
体操をして発声練習、素敵なピアノ伴奏に合わせて歌の練習。みんなで集まって練習できること…2年前までは当たり前だったことですが、練習後の爽快感と幸せな気持ち、これがコーラスクラブだと久しぶりに感じることができました。
岡崎市PTAコーラスフェスティバルは2年連続中止となり、附中祭は全体練習が足りないため『いつかこの涙が』を1番だけアカペラで先生方と歌いました。このまま三送会で先生方と『Oh Happy Day』を、男性メンバーも練習に参加して下さって『いつかこの涙が』を3年生に贈りたいと思い練習をしてきましたが、またコロナ感染拡大のため、オンライン練習も中止となり、突然今年度の練習終了となりました。
中止を決断してからも、コロナ禍2年目なので、もっと対策を考えられたのではないか…、ここまでみんなで練習してきたのに本番を迎えることができなくて申し訳ない…。今後の活動を何も考えられない状況になっていました。でも、こんな情けない部長なのに、皆さんからの温かい言葉を沢山いただけて、附中保護者の皆さんの優しさを感じ、部長って役得?と密かに思っています。

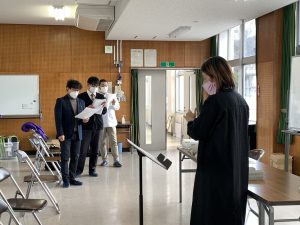


学年やクラスを越えた保護者と出会えて交流できたこと
個人レッスンで個々のレベルアップできたこと
コロナ禍なのに附中祭で歌えたこと
男性メンバーと練習できたこと
今年度も大きく一歩前進できました!!
1年間ずっと前向きに協力してくださった先生方、活動の機会をくださった役員の皆様、本当にありがとうございました。
PTAコーラス部 部長 鈴木 千香
61、男性部員、コーラス部の練習に参加
1月20日
1月14日に第1回目となる練習が音楽室で始まりました。
女性コーラス部16人に対して男性は3人と少なめです。しかも楽譜を見るのが初めてという有様なので大丈夫かという感じでしたがいざ歌い出したら指揮者の熱意と勢いで最後まで歌いきることが出来ました。しかし全員で歌うと各パートの音程が違うのでどうしても女性パートにつられてしまい合格には程遠い状況でした。点数をつけるなら今のところ30点といったところでしょうか。次回の練習までには80点を目標に頑張ります。
それはさておき、今回歌う曲「いつかこの涙が」ですが歌詞がとても響きました。だから一部紹介したいと思います。
まず「想像できる未来には興味などなくてずっと熱い目で夢を見てた。」
この部分は私が昔そう思っていて最近忘れていたことを思い出させてくれました。
若い時は何でもできる気がして可能性に満ちあふれていたな。
学生のころ自身の可能性を発見するために世界を旅したな。
いや、今からでも遅くない、挑戦してみようという気持ちにさせてくれました。
そしてもう一つ「いつかこの涙がこの仲間と出会えて信じ合えた日々が勲章に変わる。」です。
この箇所も私が学生だったあの頃のことを思い出させてくれますが、我が息子の今の状況にピッタリです。時間が限られた中で生徒会の企画書がなかなか通らず悩み、それでも仲間の支えを信じて一歩でも先へ進み何とか結果を出したいと毎晩奮闘しています。
ひとつの目標を達成するために共に苦労をした仲間は一生の友となることでしょう。また、この経験はきっと大人になって懐かしく思える日が来ることでしょう。そして頑張った分だけ自身の勲章となるはずです。このような素晴らしい曲に出会えたこと、歌う機会を与えて頂いたコーラス部長に感謝です!
最後にコロナ禍が収束に向かい、コーラスが開催され男性部員、女性コーラス部員そして先生方と一緒に歌えることが出来ることを願っています。

PTA書記 鈴木友則
60、来年も、一人一人の思いを大切に…
12月24日
野中会長より、「今年度最後にPTAのブログはいかがですか」と依頼を受けました。PTAのゾーンに私が入っても大丈夫かと思いつつ、野中会長のお誘いなので、今年一年を振り返りながらブログを書こうと思います。
今年を振り返って思うことは、昨年以上にできることを模索し、工夫して、実現できたことが多い一年だったということ。コロナ禍の前と全く同じ形ではないですが、むしろ、それまでと昨年一年間の取り組みを振り返りながら、今年できる一番よい方法は何か?ということを、それぞれの箇所でよく考えた一年だったと思っています。
学校行事で言えば、内容や日程を変えながらも、各学年のテーマが実現できるように計画した宿泊行事。(一年生は泊を伴いませんでしたが、予定していたプログラムをすべて実施することができました)また、コロナによる分散登校等の影響で厳しい日程となった夏休み明け。内容を工夫しながら、子どもたちがやりきった体育大会・文化祭。さらに、制限のある中でも可能な方法で取り組んだ追究授業。12月の終業式ギリギリまで単元に取り組みました。
PTAの行事では、オンライン文化セミナー&文化展、懇親フォトロゲイニング、PTAコーラスやおやじの会。それぞれのチーフになる方が「みんなが楽しみ、そしてつながることができる空間をつくりたい」という強い思いをもち、その思いを実現させようと周りからさまざまなアイデアが生まれ、一つ一つ実現することができました。「やらなきゃいけない」という思いだけでなく、一つ一つの活動の根幹にある「何をつないでいくべきなのか」について考えさせられる、そんな一年だったように思います。
決して一人の力だけではできない。そんな言葉がひときわ際立った今年。そこに関わる人が自分の思いを大切にして、また周りの人の思いも大切にして…。こういった一人一人の思いを大切にする附中が私はとても大好きです。
話は変わり、私事になってしまいますが…
そもそもの私が教師になりたいと思ったのは、中学生の時、一人一人のことを大切にしてくれるO先生と出会いがきっかけでした。印象的だったのは、私が駅伝部に所属していたときのことです。大会に出場する選手を決める大切な時期に、私は生徒会活動で駅伝の練習に行くことができませんでした。「何として選手になり、大会に出場したい!」と思っていた私は、一日も練習を休まず、タイムを伸ばすことばかり考えていました。生徒会の仕事も、自分がやると決めたのだからやるしかないと思いつつも、このときばかりは、気持ちは駅伝のことばかりでした。しかし、その日の生徒会活動が一区切りついたのは下校時刻直前。あたりは薄暗くなっていましたが、急いで練習場所に駆けつけると、仲間は計測を終え、下校しようとしていました。「はぁ。間に合わなかったか」と思い、渋々仲間と一緒に下校をしようとした時に、私の思いを察したO先生が、「ばばけん(当時の私のあだ名)!一本計測していくか?」と声をかけてくれました。声をかけられたときはただただ「練習ができる」という嬉しい思いだけだったのですが、真っ暗闇の中、アップを一緒につき合ってくれ、私一人のために計測につき合って檄をとばしてくれるO先生の思いが心に沁み、気づくと涙を流しながら走っていました。そのとき、記録が伸びていれば劇的な終わりだったのですが、タイムは全く伸びなかったことは鮮明に憶えています(笑)でも、O先生の思いがとても嬉しくて、このときのことを忘れたことはありません。自分のことをいつもそっと見ていてくれる人の存在がいることのうれしさ・心強さを感じた瞬間でした。
一人一人がもっている「こうなりたい」「やりたい」という思いを全力でサポートできる、そんな先生になりたいと思ったことが、私の原点になっていると思います。今、自分はそんなO先生のように毎日を過ごせているだろうかと自問すると、忙しさに負けておろそかにしていることも多く、まだまだだなと先生に言われそうです。
この時のやりとりを思い出していると、この附中と共通していることがとても多いと感じるのです。それはみんなが一人一人を大切にしているところ。附中では、子ども、保護者、教師のみんながそれぞれの思いを大切にし、お互い尊重しながら過ごしています。だから附中を卒業していく子どもをはじめとする卒業生は附中のことがずっと大好きだし、一緒に過ごした仲間を大切にしているのだと思います。
来年も、この附中がさらに発展するように、そして子どもたちの夢が叶うように、一人一人をしっかりと支えていきたいと思います。
皆様、素敵な一年間を本当にありがとうございました。よいお年をお迎えください。
馬場 健介
59、引き継がれてきた思い、ずっと大切に…
12月14日
皆様こんにちは。先週の文化展では、個人懇談会もあるお忙しい中、足を運んでいただきましてありがとうございました。私もゆっくりと作品を観ることができまして、良い時間を過ごさせていただきました。
お子様と一緒に観に来られた方、美術部の子かしらと思われる子、じっくりと作品を眺める方、様々な方々がいらして そんな様子を見てはありがたく感じておりました。


肩を寄せ合い、会話をしながら見てまわる後ろ姿がなんだか微笑ましく思いました。(勝手にすみません)
準備の時点で、会場となる食堂2階がまずどこなのか!?何年もお世話になっているにも関わらず、一人で辿り着けない。そんな事にも気づきました。今年度入学された保護者の方々も迷う方がいらっしゃるのではと思い、改めて、八木先生に会場へ辿り着ける地図の作成を依頼しました。運動場から2ルートの表示を要所にさせていただきました。分かりやすい地図に皆さん感嘆の声!(コーラス部の練習場所にもなりましたので、そちらでも活用させていただきました。)迷われる方が減ったのでは!八木先生、すぐに対応してくださりありがとうございました。
来校する機会がぐっと少なくなると、この様な事もあるのかと改めて気付きました。(半分は自分の方向音痴のせい)音楽室は、コーラス部に所属してやっとここ最近、すいすい辿り着ける様になりました。
文化部に携わらせていただき、文化展の準備を進めていくと、様々な備品を目にする機会がありました。備品の保存の仕方がとても丁寧で、歴代の文化部の皆さま方の愛情を感じました。備品の一つ一つに細やかな説明など書かれており、こうやって毎年毎年きちんと部の行事を行なって来てくださったのだなと改めて感謝する事ばかりでした。
いままで文化展では、参観のみしかしたことがなく、参観後に優雅にお茶やお菓子を戴いておりました。その裏準備では細々した事が沢山あったのだろうなと。遅いのですが、気づきを得られて本当によかったです。体育部さんの懇親会でも、1テーブルごとの準備もきちんとされていたのだろうと備品をちらりと見て感じました。
文化部も体育部も長年こうして保護者の皆さまが支えて、引き継いできてくださり今があると思うと、簡単に形をかえて開催など。。。なんだか申し訳なく思いましたが、きちんと想いは受け止めておりますので、その気持ちをずっと今後も引き継げるように、片付けひとつですがしっかりしようと思いました。
物から感じとる想いなどを、今後はもっと注意深く受け取る様になりたいと思いました。沢山考え、歴代の方々のその想いに沿えているかどうかは分かりませんが、少しでも近づく努力をしたいなと思いました。
人の想いは、本当のところは本人にしか分からない事だと思います。人間なので、考えを巡らすことは、した分だけ無限にできると思います。しなかったらそこで終わってしまいます。考えて、考えて行われてきた毎年の附中の行事。素晴らしいはずです。
至らない点が今年度、沢山あったかと思いますが、考え抜いて来たのでどうぞ許してくださいませ。甘いなと思いますが… 申し訳ありません。なんだか話がそれましたが、とにかく文化部、体育部の歴史はすごいという発見ができた文化展でありました。
講師の先生のコーナーを紹介しておりませんでした。すみません、遅くなりましたが…しめ縄だけでなく、ドライフラワーのリースや、コサージュやアロマオイルを垂らした置物など 様々な作品を産み出していらっしゃいます。素敵です。

後日、作品を作りにあすか先生のご自宅へ行ってきます。ご興味のある方は、またお声かけくださいませ。
無事に文化展を終えまして、お子様を通じて作品を返却させていただきます。しばらくおまちくださいませ。美術部の作品もお借りできまして、さらに会場が華やかになりました。本当にありがとうございました。
PTA文化部部長 芝原 明恵
58、たくさん想いがつまった文化展。本日より開催!
12月7日
皆様こんにちは。文化部長の芝原です。昨日、小雨の降るなか、今年度最後の文化部会を行いました。
去る9月10日、17日に文化セミナーをオンラインにて開催させていただきました。例年ですと、その後に文化セミナーで作成していただいた作品や、附特の方々、先生方、保護者の方々から大切な作品をお預かりしまして武道場にて文化展を開催しておりました。
今年度はコロナ禍で、文化展の開催もどの様にできるのか未定でしたが、大切な作品の回収や保管、返却も困難な事から、写真のデータを集めましてなんとか開催の方向で、写真展にする事にしました。
12月にどの様な状況になっているかも予想が出来ずに不安はありましたが、本日、短時間ではありますが直接部員の皆様のお力添えをいただき、会場準備が整いました。





部会ではお休みの方も見えましたが、部員さんの生の声を聞けて本当によかったです。文化セミナーや部会も開催できてよかったというお声が多く聞けて、これまでやって来て本当によかったなと思うとともに、学校側や先生方にもこの様な場を与えていただき本当に感謝しております。やはりマスク越しではありますが、お会いして話をして、触れ合って、すごく貴重で、良い時間だなぁと感じました。
写真展の準備は、学年ごとに副部長さんにお任せしまして センスあふれる展示場ができました。どの学年も素敵に仕上げていただき感激です。皆さんの美的センスが素晴らしすぎて、私は、見て回り「素敵〜素敵〜」となっていただけで、何にもお仕事していませんでした…すみません、本当にありがとうございました。短時間で一気に食堂が華やかになり、びっくりしました。終わり頃には給食の良い匂いがただよいましたが…。
部員の皆様のパワーに感激です!!ありがとうございました。


12月7日(火)から10日(金)まで、
食堂2階にて文化展を開催いたします。

保護者の皆様、是非とも現場にいらして素敵な雰囲気を味わってくださいませ。BGMは…八木先生チョイスの素敵な曲などを流す予定でおります。私も、少し選曲させていただきました。
きっと、少しの間、現実から離れた心地よい空間が待っていると思います!お時間ありましたら寄っていただけるとうれしいです。
今回、文化祭の時に育朋館に展示してあった作品や美術部の生徒の作品も少しお借りしております。文化祭に来校いただけなかった保護者の皆さまも是非、力作を見て頂く機会になるとよいなと思います。
沢山の皆さまのお力添えがあり、このように形を変えながらも文化展が開催できることを本当に感謝いたします。ありがとうございました。
PTA文化部部長 芝原 明恵
57、晴天の下、フォトロゲイニング開催!
11月25日
皆さま、こんにちは。体育部長の大河内です。
お待たせいたしました!本日は、11月17日に開催されました「懇親フォトロゲイニング」のご紹介をさせて頂きます。
当日は校長先生からのご挨拶、そして野中PTA会長の
“ エイエイオー ” の掛け声で参加者気合を入れ、いざ出陣!

ところで、皆さまは「フォトロゲイニング」という言葉をご存じでしょうか?フォトロゲイニングとは、地図をもとに時間内にチェックポイントを回り、見本と同じ写真を撮り、得点を集めるスポーツです。
今回は、附中、東岡崎駅、さくらの城橋、籠田公園、リブラ、岡崎公園と六つにエリアを分けて、その中にチェックポイントを合計22か所つくりました。


事前に下見をし、簡単なポイントから見つけるのが難しいスポット、懇親を深めつつゆったりとまわれる時間配分をし、当日を迎えましたが・・・
参加者皆さま本気!本気!!本気!!!
パーフェクトで全チームゴールしました。(簡単すぎてゴメンナサイ)
さらに、2時間半しっかりと懇親を深めてきてくれました。


そして最後、ゴール地点では、撮ってきた写真のチェックがありました。参加者皆さまの予想以上に素晴らしい活躍に、写真のチェックをかなり厳しくし得点の差をつけることとなり・・・(出発前の説明で必ず同じ構図の写真を撮ってきてくださいと二回伝えてはいましたが・・・)
写真チェックの厳しさに、あの手この手で得点をゲットしようと頑張ってくれたチームも多数
チェックポイントとは関係なく撮ってきた楽しい写真を見せてくれたり、私を褒めてくれたり、等々



最後は流れ解散でしたが、少し汗をかきつつ皆さまが笑顔で帰られる姿を見ることができ嬉しく思います。
今年度は9月に予定していた「スポーツウォークラリーin附中」が実施間近で中止となり、見通しの立たない状況ではありましたが、子供たちの学校行事を無事に終えた後に、何とかスポーツ懇親会を繋いでいきたいと思い、今回の企画を考えました。皆様へのご案内から開催日まで一か月と短い中、ご参加くださいました方々には大変感謝しております。来年度もどのような状況下にあるのかわかりませんが、この附中のスポーツ懇親会がどんな形であれ引き継がれていくことを願っております。
体育部部長 大河内 彩
56、先輩の姿から、何を想う?
11月18日
PTA教育文化講演会のあとがき
文化祭に組込んで頂いた教育文化講演会も無事終了致しました。ご協力頂いた皆様、ありがとうございました。附中の卒業生である矢野慶汰さんをお招きした今回の講演会。会場の異様な盛り上がりを思い出しつつ、あとがきと裏話を少々したためたいと思います。


この2年間、時間があれば講師の候補者を考えてきました。世界を知っている人。肌で感じている人。その経験を、未来を生きる生徒の皆さんに伝えてくれる人。誰だろう。どんなテーマだろう。候補者①アメリカの大学を卒業後、世界150カ国以上を旅し、世界の現状を知る旅のスペシャリスト 候補者②世界№1コンサルタント会社のセルフマネジメント 候補者③アメリカ、カナダで武者修行したスーパー外科医 候補者④アメリカ・シカゴで出版社・飲食業を展開する実業家 候補者⑤世界に認められた日本のアニメ、ジャンプの編集者。ちなみにこの5人の御仁は皆さん附中サッカー部出身です(サッカー部推しでスミマセン)。ある候補者と再会した際、講演会の話をしたところ、「まずは、みーくん(矢野さんのあだ名)じゃないかな。僕はその次の候補で」との返答。その場にいた同級生も、「やっぱり、みーくんかな」。彼らの言葉も私の決断を後押ししてくれました。そして「育朋」や当ブログ「㊶ 決断の時に備えて・・・」に繋がっていったのです。
矢野さんに、正式に講演を依頼した際、「とにかく多くの写真を、現場を見せてくれないか」と要望を出しました。すると、矢野さんはパワーポイントのスライドを170ページも送ってきたのです。「情報量が多いと、生徒達の『脳』は勝手に情報を取捨選択するモードに入るよ。附中生は普通にそれができるんじゃないかな」とさらり。それでも流石に170ページは多いでしょとたしなめ、ようやく落ち着いて130ページになったのが生徒の皆さんが見たスライドです。矢野さんは、アメリカで社会学を研究されてきました。社会学者といえば最近では古市憲寿さんの様に広く、浅く話題が豊富なイメージです。私が講演会に期待したものも、その話題の豊富さでした。
社会人である私も仕事上で講演会や講習会に参加します。その際に、気をつけている事は一つの講演会につき「キーワードとして5つ以上にまとめ、自分に刻み込む事」です。今回の講演会では
・一つでも多くの国を、自分の目で確かめなさい。
・地元の人が食べられないスーパーフード、矛盾
・VUCA
・自己肯定感、Self-esteem
・募金、その行方。
・草食系は結構、怖い。
・早く行きたいなら一人で、遠くに行くなら皆で
・生きるための「5つのビタミン」
でしょうか。
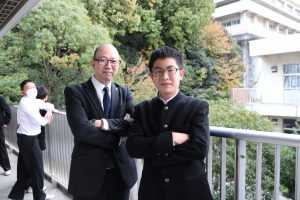





講演会後、矢野さんは懐かしの附中を散歩しました。読書好きの彼がまず向かったのが図書室。山形・酒田にゆかりのある「菜の花の沖」(司馬遼太郎)を見つけ、不思議な縁だなと喜んでいました。2Cでは元Cグループ応援団長として「来年は体育大会優勝するぞ!!」と集合写真。2Dでは令和4年度サッカー部キャプテンとの記念撮影。技術室、給食棟、育朋館、グランド等。各教室からは矢野さんへの拍手。附中生の皆さん、ご協力ありがとうございました。
最後に、酒田に戻った矢野さんから附中生へのメッセージ。
「いつでも酒田へ、若葉旅館へおいで。どんな話しでも聞くからね」
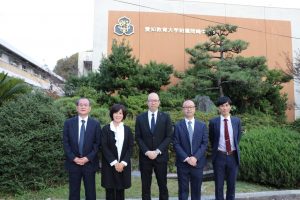
PTA会長 野中 健史
55、秋晴れのもと、懇親フォトロゲイニング開催!
11月17日
【懇親フォトロゲイニング】結果発表!!
皆さん、こんにちは。体育部部長の大河内です。
9月に実施予定でありました″スポーツ懇親会″がコロナウィルスの感染拡大により中止となり、その代替行事として企画いたしました【懇親フォトロゲイニング】を本日無事に開催することができました。
懇親フォトロゲイニング終了と同時に、結果発表はいつですか?というお声を多数いただきましたので、余韻がさめない今日のうちに結果発表致します!!
・・・ ドキドキワクワク ・・・
優勝は、同得点で2チーム、
3B と 3CD チームです!
おめでとうございます!!!
3位は、1Bチームでした。おめでとうございます!
本日の【懇親フォトロゲイニング】のご紹介は次回となります。お楽しみに♪
PTA体育部部長 大河内 彩
54、附中生がだいだいだい大好きだ!(文化祭2日目)
11月12日

皆様こんにちは。
文化祭2日目午前中はコーラスコンクール、午後からは文化講演会に附属中の卒業生であります、矢野慶汰様をお招きして様々な話を聴かせていただきました。
まずは、先生方、附中生の皆さんお疲れ様でした。体育大会、文化祭、大きな行事が無事に終えられた事。本当に素晴らしいと思います。2学期がスタートして短期集中!!気力も体力もよく持ち堪えたなと本当に感心させられました。一旦休息して、また新たな日々を過ごす力を蓄えて欲しいと思います。
午前中のコーラスコンクールでは、審査員に橋本剛先生をお招きしましてご好評いただきました。(今週はじめには、歌の御指導もいただけたようでありがとうございました)
一年生は初めてのコラコン、2年生は先輩の凄さを後輩に見せつけるチャンスのコラコン、3年生は最後のコラコン。それぞれの想いが溢れ出る素敵な時間でした。
特に印象的だったのは、3年生の指揮者の1人が「観ている仲間と、先生方に想いを届けたい。僕たちは、あと113日で卒業だ。」そう発した言葉です。 その通り特に3年生は素晴らしい歌声を聴かせてくれました。1年生も2年生もそれぞれ素晴らしかったです!
審査員の先生も仰っていたように、結果に一喜一憂せず今まで頑張ってきた過程を大切にして過ごして欲しい。まさにその通りだなと思いました。混声合唱から生まれるハーモニーは原始時代から存在するある種の奇跡だ。とも教えてくださいました。今日の歌声は一度きりの奇跡なのです!!本当に全員が素晴らしかったです。
午後の文化講演会は世界の150ヵ国を旅してきた矢野さんのお話でした。附中生は異様に盛り上がりを見せていましたね。とても有意義な時間でした。聴いている子ども達と保護者では立場が違うので、捉え方も考える点も様々あるのではないかなと感じました。
生きるための5つのビタミン ・他人への嫉妬をいだかない。・他人を許す。または忘れる。・自己肯定感を高める。・バーチャルではない、リアルな友人を持つ。・なるようになるという思考を持とう。その様なお話が印象的でした。他にも沢山ありますが、一冊の本の紹介も気になりました。「華麗なるギャッツビー」未読の本ですのでこの機会に読んでみたいと思いました。
また、「旅をすること、本を読むことから今後の人生で一つでも多くの事を発見し続け、生き続けて欲しい。また、他者に手を差し伸べて欲しい。」そんなお言葉も素敵でした。
まだまだ沢山のお言葉をいただきました。後日、野中会長からまた違った視点でお話いただけると思います。お楽しみに!
閉会式では、コーラスコンクールの審査結果や、クラスの出し物の審査結果。お待ちかねの時間でしたね 何回同席させてもらっても、自分もドキドキしてしまうし、その様子に一生懸命取り組んで来たのだなと胸が熱くなる時間でした。
今年は特に、この様なコロナ禍での行事開催。素晴らしいことです。感激です。感謝しきれません。そんな気持ちを、最後の挨拶で、副校長先生が代弁してくださいました。
3年生が歌った合唱曲の歌詞から「だいだいだいすきだ〜大大だいすきだ〜♪」増岡副校長先生の歌声からスタートした最後の挨拶。「自分達のクラスだけでなく、他学年の事も自分達のことの様に喜ぶ子ども達がだいすきだー♪縦割りの繋がりを大切にする姿がだいすきだー♪体育大会、文化祭、全力で頑張る姿がだいすきだー♪そんな、君達、今日までの事に自信を持って過ごして欲しい。今日の様な感激的な時間がこのままずっと続いて欲しい。」まさに、先生方や保護者の方々が想っている気持ちだと思いました。附中生が、だいだいだいすきだー♪!!!副校長先生の言葉を、子ども達ひとりひとりが御守りの様に胸に忍ばせ、ずっとこれからも学校生活を過ごして欲しい。大人になっても忘れないでいて欲しい。大きな自信になった、ちっちゃな自信になった。それぞれ感じるままでいいとおもいます。

(副校長先生に御写真の掲載許可は頂いております。私もウルウルしてしまったのですが、副校長先生もウルウルされてしました。勝手に公表、申し訳ありません。)
生徒会会長挨拶も「アクションを起こす大切さを学んだ」最後にまたいい事いうなぁまたウルウルです。
附中生!!色んな頑張り方があると思うので、自分に合った頑張り方で日々を過ごしていって欲しいと願います。周りの大人達は、いつでもずっと見守ってくれる人ばかりだから、安心してこれからの学校生活を過ごしていって欲しいと思います。
イケメンあんぱんマン、バイキンマンの仕上がりも気になりました。感動的な時間をいただきありがとうございました。


忘れてはいけない!頑張りました!PTAコーラス部!素敵だったでしょ!次回のお披露目まで、またしっかり練習に励みたいと思います。小楠先生!御指導ありがとうございました!


(コラコン前日、先生方との合同練習風景)
PTA文化部部長 芝原 明恵
53、子どもの熱気あふれる文化祭
11月11日
皆様こんにちは。文化部長の芝原です。
本日は文化祭1日目です。子ども達は体育大会を経て、まだ興奮冷めやらぬままに文化祭準備に突入となりました。パワフル過ぎて感心しています。限られた時間の中で、先生方や子ども達が集中して取り組んで来たおかげで、無事に当日を迎えられたと思います。いつも先生方ありがとうございます。
昨日、娘のお迎えに行った際、育朋館の周りでは、それぞれ準備に取り組んでいる姿や合唱練習の歌声、ドラムの演奏、子ども達の笑い声などが入り混じり、熱気を帯びているなぁと車の中からですが感激しておりました。歌声が素晴らしい!どのクラスから聴こえてきたのかは分かりませんが、こんなに離れていてもしっかり響いてくるなんて…。熱が入っている3年生かしら。ゾクゾクっとしました。明日の本番がすごく楽しみです。
本日は、保護者の皆様は参観できませんでしたが、子ども達のみでクラスの出し物、18コン、様々楽しめていたようです。お子様から沢山話を聴いていただき、今晩は想像の文化祭1日目をお楽しみください。明日は実際に歌声を聴き、感動的な1日になることと思います。
コーラス部も、朝一番で発表の場をいただきまして、先生方とも一緒に歌わせて頂きます。この様な時間をいただき本当に感謝しております。前日に先生方と練習をさせていただきました。さすが先生方、日々の朝練のみでバッチリでしたね!広い育朋館に歌声が響き、ワクワクしました。明日は子ども達に想いがしっかり届く様に、リトグリの「いつかこの涙が」を一生懸命歌います。
また当日の為に、部長さん達がコサージュを作成していてくれました。学年毎に色が違い(2年生保護者は、ボラへカラーとの情報もあり楽しみにしています。個人的に好みのカラーで、泣けちゃいそうです。)一つ一つ飾りが異なり、丁寧に作ってくださったとのこと。沢山、大変だったと思います。本当にありがとうございました。


正門には、文化祭の立て看板。その横の黒板には、2年生イケメン男子が描いてくれた、イケメンあんぱんマンが皆様をお迎えいたします。

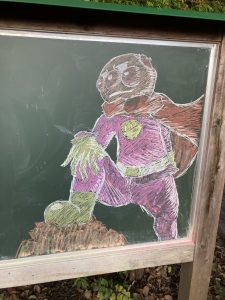
(お写真掲載の許可は本人達から得ております。)
まだ作成途中ですが、余白にはバイキンマンも描かれるそうです。完成した2人の力作もどうぞ本物をご覧くださいませ。
明日はいよいよコーラスコンクールです。素敵な文化祭2日目となります様に!!
PTA文化部部長 芝原 明恵
52、コロナ禍での体育大会開催!
11月8日
皆様、こんにちは。PTA副会長の水越です。
好天の中、コロナ禍における2回目の体育大会。検温から始まり、応援時も密をできるだけ避ける参観。これが令和における体育大会のスタンダードになるのでしょうか。
生徒たちによる競技、応援にも力が入り、いつの間にか密になってしまう保護者たち。午後の部になると実況中継のアナウンスもヒートアップ。白熱したレース展開に「ウマ娘」と言ったとか言わないとか。閉会式後のグループ別反省会での3年生から2年生、1年生へとバトンタッチされる思い。毎回感動を与えてくれます。競技は個人個人の努力に左右されるところもありますが、応援は別。縦割りグループの結束力の賜物です。
さて、応援の制作物ですが、いくつかの班に分かれての作業。
①段ボール…はりぼての画板を作るため、段ボールをタフロープでつないで1枚の大きな板を制作
②はりぼて…段ボール版の上に貼る絵の制作物
③NEO…各グループのモチーフ制作
④やぐら…NEOを乗せる台の組立
⑤入場門…やぐらを飾り付けし、応援団が入退場する門の制作

グループの皆が作った制作物。1日限りのお披露目ではもったいない。グループ別反省会の前に、保護者にも身近に見ることができる機会を設けていただけたらと思いました。また、応援の練習風景、応援物の制作過程等、メイキングでもあったら面白いなとも感じました。
最後に生徒たちが解体した制作物を育朋館へ運ぶ姿を見て、一緒にいたある父親の一言「グループで輪になり、この制作物でキャンプファイヤーのようなことができたらよい思い出になるんじゃないかな」と印象に残る一言でした。
コロナ禍での体育大会の運営、進行。また、大会終了後のやぐらの撤去。遠目に見ていましたが、とても大変なこと。先生方、本当にありがとうございました。
PTA副会長 水越 健夫
51、想いは受け継がれていく
10月28日
10月23日(土)、体育大会を前に、第2回附中おやじの会を開催しました。子どもを合わせて約50名の参加者が集い、地域の清掃活動とグランド整備をしました。


風の強い中でしたが、体育大会の成功を思いながら作業をされる背中がとても素敵でした。




今回のブログは、これまで3年間、附中おやじの会皆勤賞のお二人に執筆していただきました。

はじめまして、3年C組 冨田さくらの父です。
おやじの会3年間皆勤の記念としてこの文書を書く機会をいただきましたが、お恥ずかしいことに幼少期から文章を書くことが大の苦手で・・・ かなり緊張しながら書いています。
普段なかなか行事等、主体的に取り組むことのなかった私ですが、おやじの会は長女が在学していた頃から参加させていただいておりました。お父様方だけでなく、お母様方も参加されており、毎回、皆さんの高い行動力に驚かされるばかりでした。
以前は体育大会準備に精を出す子供たちの姿を垣間見ることもできましたが、最近は子供たちのいない時間に グランド整備、木の剪定、育朋館・教室・地域清掃等といった活動を行っています。今回は子供たちも手伝ってくれて、共にグランド整備を行いました。子供たちの頑張りもあり、きっちりと整えられたグランドを見渡すと、俄然体育大会が待ち遠しく感じられます。
私は今年で卒業になりますが、この素晴らしい活動が今後も引き継がれてゆくことを願います。貴重な経験をさせていただいたこと、PTAの皆さん、そして先生方に感謝いたします。
ありがとうございました。
冨田 浩邦(3C さくら)
3年A組 鈴木哲平の父です。野中会長より皆勤賞のご褒美として仰せつかりました。慣れないブログをここにしたためます。
先週の土曜日、インディゴブルーの空にYOASOBIのワンフレーズが隣の中学から何度も響く中、おやじの会が催されました。皆さんから体育大会の無事開催を祈るような想いが伝わってきそうでした。
父親は学校から呼び出されないかぎり行くものではないと亡き父に言われていた私にはおやじの会とは?という怖いもの見たさがありました。子供達の様子を垣間見られ、且つ希望者には一席設けていただけるということを聞き及び、できる事は何でも協力してやろう、他の親御さんから親としてできることを学ばせていただこうと今日まできました。
活動内容はブログで紹介されている通りです。本年度より、学校の敷地を出て電車通りの清掃を始めました。地域あっての中学生活、地の恩を忘れないようにできればいいですね。
作業中にふとしたことで会話が出来たりします。初見の方と家での過ごし方や思春期にありがちな接し方の変化などは「なる程」と頷いたりします。卒業された兄弟のお話や、ご自身が府中生だった経験談は説得力がありました。父親役は家族に一人ですから、判断に迷ったりします。そんな時の強い味方になっています。
残念ながら、子供たちの課外活動を横目に作業をする機会はありませんでした。ただその分、愚息から聞く折々の出来事の現場確認には絶好の機会となりました。トラック競技ではコーナーが命ですから、念には念を入れてメンテしたつもりです。表層に広がる少し粗目の砂はとても滑りやすいです。体育大会では腰と膝を上手く使って切り抜けて下さいね。
2年前の懇親会で「ここにお集まりのお父さん方は、子供のためならなんでもしてやろうという想いがある」という言葉をよく聞きました。その度に皆さんが一様に同意される様子が懐かしいです。おそらく、最後のご奉公は卒業式前の式場整備だと思うと一抹の寂しさがよぎります。
「子供が生まれた時親も一年生」とはよく言ったもので、子供と共に成長させてもらった気がします。そしてそれが受け継がれやがて今附中の主たちが護り手となって再びこのグランドに戻ってくるなんてちょっとワクワクします。
作業も終盤に入った頃、南門越しに「お疲れ様です。頑張って下さい。」と隣の中学生の声がユニゾンのように校庭に響いてきました。咄嗟のことで声もかけられませんでしたが、坂を下る彼らの背中にちょっと羨ましいかも、といった微かな思いが漂っていたようにみえました。
そう言えば、いつの間にかYOASOBIのトランペットが鳴りやんでいました。
鈴木 恒次(3A 哲平)




㊿失敗を恐れず…、失敗を糧に… 多くの学びを生み出せるチャンス。さあ、いよいよ体育大会・文化祭!
10月23日
私は、学年通信を楽しみにしています。校長は週2回しか附中にいないこともあり、生徒一人ひとりと話をする機会がありません。そんな中、学年通信には、子どもたち一人ひとりの思いが書かれています。教室を見て回る時、名札を確認して、この子はこんな思いがある子だとか、あんなことを頑張っている子だとかが分かります。また、学年通信には、保護者の方々の言葉も掲載されています。附中をよくするための糸口にさせて頂いております。保護者からお子さん向けの言葉に「失敗を恐れず」、「失敗を糧にして」という言葉が多く書かれていることに気づきます。附中生は失敗を許されていることがわかります。附中生がチャレンジ精神旺盛で、諦めること・挫けることが少ないのは、そんな保護者の方々のお考えがあるからでしょう。チャレンジには失敗がつきもの。附中生はいろいろなことにチャレンジしていますが、それは保護者の方々の寛容があってこそ、できていると感じています。一方、先生方も、追究授業・ライフワークでいろいろなチャンスを考えています。職員会議でも先生方の発言に「子どもの動きをまず見ましょう」「子どもの思いは」という発言が多いです。チャンス(chance)とチャレンジ(challenge)と寛容(toleration)の良い循環が附中のよさと思います。
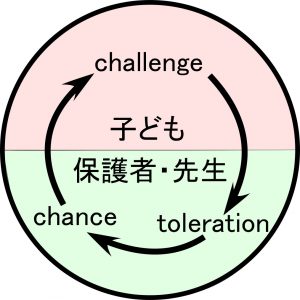
次に、2学期の始業式で、同情と共感について話をしました。同情されるのは、下に見られているようで、自尊心を傷つけられること。一方で、同情する気持ち、他の人を助けてあげたいと思うことは、とても尊いことと話をしました。同情と同じような言葉に共感があります。同情が内向きの心の動きとすれば、共感は外向きの心の動きです。共感とは、字のごとく、感情を共有することです。文化祭・体育大会では、個々が違うパートを担うことになりますが、目指す目標は1つです。文化祭・体育大会を通して、子どもたちには共に笑い、共に泣ける共感し合える仲間を作ってほしいと思っています。附中での共感は、一生残り、長い人生の中で、拠り所になると確信します。
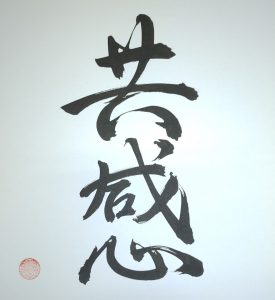
いよいよ迫った体育大会には、個人種目がありません。以前から熱中症対策のために競技を減らす必要からどうしてもしたい競技だけが残ったのでしょうか。附中生らしいですね。個々が頑張りながらもグループの一員として協力し合う姿・やりきる姿を見せたかったのでしょう。
文化祭・体育大会の子どもたちの姿を見に来てください。共に笑うときは全身を使って笑い、共に泣くときは下を向かずしっかり仲間をみて泣く姿があるはずです。文化祭・体育大会は、子どもたちにとって共同作業ゆえに大きな試練であり、そのため飛躍的に成長するタイミングです。体育大会終了後、グループ毎に分かれて円陣を組んで反省会をする時が、共感マックスです。
附属岡崎中学校 校長 戸田 茂
㊾チームでワークする
10月14日
みなさま、こんにちは。PTA副会長の北村です。
スポーツの秋、芸術の秋、到来です。体育大会、文化祭と行事が目白押しで、附中生は多忙を極める日々が続きますね。特に3年生は進路に向けて動きつつ、最後の行事を成功させるために力の限り動いていることでしょう。
前々回、野中会長がチームワークについて触れられていました。私もチームワークについて記そうと思います。
私事で恐縮ですが、私の父、夫、息子たちは野球をしており、気がつけば野球人に囲まれた人生を送っています。沢山のグローブやバットなどに囲まれ、砂だらけのユニフォームの洗濯に勤しみつつ…陸上を続けてきた私にとって、チームスポーツである野球はどこか別世界のものだとずっと感じていました。
リレーや駅伝を除けば陸上は個人競技なので、勝敗は自分自身との戦いです。集中力を高めての一発勝負。そこには、数字という形で結果が出る潔さがあります。駆け引きよりも自分自身と向き合った結果、選手は頑張り次第で皆スタートラインに立つチャンスがあります。(あくまでも私見ですが…)
一方、野球ではチーム内での熾烈なレギュラー争いを経て、それぞれの役割を果たすべく様々な思いを胸に試合に挑みます。攻守のチャンスがある野球は、9回2アウトの最後の一球まで何が起きるか分かりません。自分を犠牲にする犠牲バント(バッターが自分自身をアウトにして走者を先に進めるプレー)や犠牲フライ(バッターが打ち上げたフライを野手が捕球するとアウトになるが、ランナーは野手が捕球後に進塁できるプレー)などを目の当たりにし、私は不思議な感覚にとらわれました。個人でプレーする競技において、自分自身を犠牲にして誰かの為に働くなどあり得ないことですから。
チームワークとは一体何なのか?
夫は言いました。「チームワークとはチームでワークすること。個人がそれぞれの役割、責任を果たすことがチームの能力を高め、チーム全体の底力を引き上げる。野球は社会の縮図そのものだよ」と。
チームワークを助け合いだと捉えていましたが、どうもそれだけではないらしいのです。野球が個々の役割の結集なら、陸上にも通じているかもしれない。
スポーツに限らず、芸術や音楽の世界でも、またこのコロナ禍の色々な場面においてもチームでワークすることが大切なのかもしれない。
チームワーク。みなさまにとって、どのようなものでしょうか?

PTA副会長 北村 恭子
㊽いざ新人戦へ ~繋がり~
10月4日
こんにちは。PTA役員の丹羽です。
9月29日から10月1日まで岡崎の中学の部活動の3大メジャーである「新人戦」が行われました。コロナ禍で5月に行われる総体は緊急事態宣言中で中止でしたから、今回の宣言中の大会も開催できるか心配しておりました。また、台風16号が発生しており、天気もどうなるかとそちらも危惧しいてましたが、1日目は晴天、2日目は時折雨が降りましたがなんとか開催しました。私の子供は、サッカー部に所属しておりましたので、そちらの様子をご報告させていただきます。

まず、保護者の専用の通路から会場に入ります。その入り口で学校から配付された入場許可証に名前や当日の体温、体調について記入したものを提出し、受付の方に体温を測っていただいて、やっと入場できます。
選手やコーチの入口は別にあって、子供にタオルを渡したい保護者の方がいたのですが、入場不可でした。対応がなかなか厳しいとも思いますが、感染症対策としてはバッチリですね。さらに選手たちの控えの場所も保護者の応援席とかなり距離もありました。
今回、サッカー部は1回戦目は勝利。2回戦目は惜しくも敗退でした。保護者席では、「大きな声を出してはいけない」と思いつつも思わず声が出てしまうほど盛り上がりました。
どの団体スポーツもそうなのですが、サッカーは1人の力で勝つことも、負けることもありません。ボールに触っていなくても敵が動けないようブロックしていたり、フェイントをしていたり、指示をしたりと、どの選手も動いています。もちろん、ベンチにいる仲間もフィールドで見にくいところを教えたり励ましたりします。
繋がり
それを感じました。
他にも繋がりを感じたのは、キャプテンマークです。今回、我が子がサッカー部の部長をやらせていただいていたのですが、附中のキャプテンマークをつけさせていただきました。これには代々「繋がり」があります。


これが何本目なのかわからないのですが、このキャプテンマークをみて私も驚き、ジーンとました。我が子は光栄に思うことと同時に責任を感じたと言ってました。今回の試合の結果は先輩たちの思いを背負っての試合だったに違いありません。来年度の大会、更にパワーアップした姿、楽しみにしています。
年代の後に、当時のキャプテンの名前が記されています。(ブログ掲載のため名前は隠させていただきました。)
最後に、新人戦に出た選手達、いつも熱心に指導してくださる先生方、そして、送迎やお手伝いしてくださる保護者の皆様、お疲れ様でした。
PTA役員 丹羽 由紀子
㊼一つの目標を果たすために 其の二
9月24日
ラグビー日本代表監督 故平尾誠二氏が語ったチームワーク
近年、ラグビー日本代表が目覚ましい活躍を見せてくれています。2015年ワールドカップ・イングランド大会では強豪・南アフリカ代表からの勝利。2019年ワールドカップ・日本大会ではベスト8進出。
野球界に「長島」、サッカー界に「カズ」がいるように、ラグビー界にも伝説の人物がいます。1984年から放送されたテレビドラマ『スクール☆ウォーズ』のモデルとなった故平尾誠二さんです。
ラグビーは緻密かつ高度な戦略を理解し、実行する事が求められるスポーツです。攻撃時・守備時・膠着時にフィフティーン(15人の選手)にそれぞれが果たすべき役割が分担されています。いわゆるチームワークのスポーツです。
平尾さんは「チームワーク」をどのように考えていたのでしょうか。
『チームワークという言葉の概念を日本人に訊くと、だいたいの人は「助け合い」ときれいに回答しはるんですね。どっちかというと美しく語る。でも、チームワークというのは、もっと凄まじいものやと思うんです。
いちばん素晴らしいチームワークは、個人が責任を果たすこと。それに尽きるんですよ。そういう意識がないと、本当の意味でのいいチームはできない。もっと言うと、助けられている奴がいるようじゃ、チームは勝てないんです。
助けられている奴がいるってことは、助けている奴がいるわけです。その選手は、もっと自分のことに専念できたら、さらにいい仕事ができるんです。』
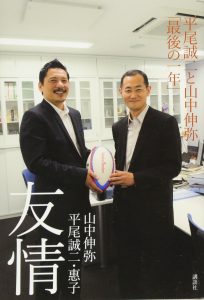
友情 平尾誠二と山中伸弥「最後の約束」 (講談社文庫) より
自分に与えられた重要な役割を、苦しい場面でも100%全うすること。自分の責任を果たすこと。これこそが「チームワーク」と言っています。
はて? 前回、私は比叡山延暦寺の「不滅の法灯」の話をしました。その時は、「役割分担・他人事にせず、我が事として行動する」「油断させない」という内容でした。今回は「自分に与えられた責任を100%全うしよう」と言っています。附中生の皆さん、何だか相反するような気がしますか?私は相反しているとは思えないのです。
この2つの話をもとに、皆さんがどう考え、行動するか楽しみです。
一つの目標を果たすために。
PTA会長 野中 健史
㊻一つの目標を果たすために 其の一
9月24日
比叡山延暦寺『不滅の法灯』
附中生の皆さん、こんにちは。PTA会長の野中です。皆さんは琵琶湖のほとり、比叡山の山中にある延暦寺をご存知ですね?今回は、その比叡山延暦寺にまつわるお話をしたいと思います。
延暦寺は今から約1,200年前に唐に渡り、仏教を学んだ最澄が帰国後に天台宗のお寺として建立しました。その際、最澄自らが薬師如来本尊をお彫りになったそうです。その本尊の前に、3つの法灯が並んでいます。その法灯は1,200年の時を越え、今なお灯され続けています。延暦寺はお寺としては勢力が強く、政略的事変に巻き込まれることが多々ありました。織田信長による「比叡山焼き討ち」などです。しかし、その間においても灯火は守られ続け、いつしか「不滅の法灯」と呼ばれるようになったそうです。


どうやって、1,200年以上も法灯を守り続けられたのでしょうか。それは、僧侶が絶えず火のお世話をしてきたのです。燃え続けるための菜種油を注ぎ、また、火の芯が燃え尽きそうだと新しい芯に取り替える。この地味な作業を1,200年以上も続けてきたのです。
比叡山延暦寺では、「不滅の法灯」を守り続ける係りがいません。担当・役割を決めつけると我が事ではなく「他人事」となってしまいます。その為、階級・役職に関わらず全ての僧侶が常に気を掛け、気づいた人が油を注ぎ、芯を替える。代々、その信念が受け継がれてきたのです。
この、火のお世話。誰かがやってくれるだろうと「他人事」として考えると、「隙」が生まれます。そして油が切れると火は消えてしまいます。これを「油断」と言うようになったそうです。
10月、11月と、附中においても体育大会や文化祭など多くの行事が続きます。優勝目指して各クラス、グループで練習に取り組むことでしょう。そこで、考えてみて下さい。「油断」しないために自分が何をしているのか。そして見つけて下さい。あなたの回りにもきっといます。「油断」しないように地味な作業をそっと続けてくれている友人が。
一つの目標を果たすために。
PTA会長 野中 健史
㊺オンライン文化セミナー2日目 開催!
9月21日
保護者の皆さま こんにちは。先日の文化セミナー2日目も無事に終えることができました。あらためまして感謝申し上げます。2日間で、約140名の参加者が画面を通じてオリジナルしめ縄を作成できました。講師の鶴見明香先生、本当にありがとうございました。
明香先生の優しい雰囲気が、画面を通して皆さまに伝わっていたと思います。それぞれのしめ縄が仕上がっていく過程で、先生に材料を付ける位置を相談したり、試行錯誤しながらだんだん自分の作品に愛着が湧いていったのではないでしょうか。皆さんの作品は画面から見させていただきましたが、それぞれが個性あふれる作品ですごく素敵でした。作業中、全員にお声掛けができなかったことを申し訳なく思いますが、限りある時間の中で参加者の方々も明香先生も癒しの時間であったと思います。
学校の会議室では2台のパソコンと手元を映すカメラを使い、明香先生のお顔と手元を切り替えながら作業をすすめていきました。
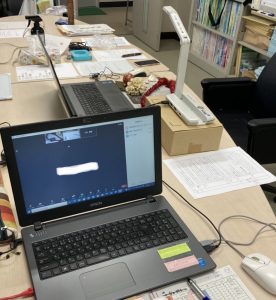
この様なセッティングは全て文化部担当の八木先生が行ってくださり(前日には準備万端)、私たちが朝学校に到着すると完璧な状態でスタートできました。作業中も、グルーガンのボンドが垂れたら、さっとティッシュを差し出してくださる。あれがない、これがないという時も「ありますよ!」と細々した事は全てやっていただき。。。何かあったら八木先生がいらっしゃる!と安心して構えて作業が進められました。

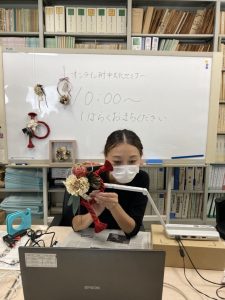

昼食は、新刊が綺麗に並べられた図書室の隅っこでいただきました。(個人的には、本が気になってしまった!附中生の皆さん、新刊リストは手元に届きましたか?どんどん読んでくださいね!)優雅な空間でいただく昼食も、明香先生との会話も、とても癒しでした。短い時間でしたが、実際に逢って言葉を交わすという事ができて、得した気分になりました。やはり、話のなかでは「なかなか逢いたい人に逢えない。」「対面でできたら幸せよね〜やっぱり人恋しいよね〜。」様々ありましたが、結論、「今日、こうしてオンラインで出来ること。様々準備いただいたこと。場所を提供してくださった事。全てがありがたい。当たり前みたいだけど、あらためて感謝だね」と、お腹も心も満たされて、午後の部準備に取り掛かりました!
(私たちが優雅に昼食をいただいている間、八木先生は給食をちゃんと召し上がれたのでしょうか?)
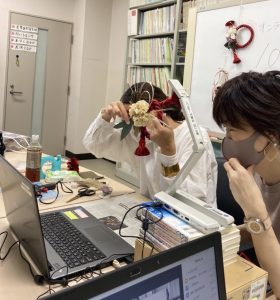

皆さんの作品が出来上がると画面上ですが、集合写真を撮りました。(全員が映れなかったかしら、ごめんなさい。。。)

2日目、作業中は記録用として録画をさせていただいたので、好きな場面でスクリーンショットが撮れるようです。
その後、少人数に分かれての雑談会に、順番に明香先生が周っていきました。


文化部員の皆さま、グループを取り仕切っていただいた方ありがとうございました。急なお願いにも対応していただき感謝いたします。
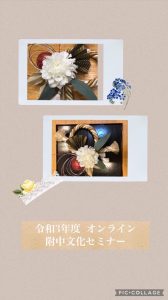
後日、この様に素敵にコラージュされたしめ縄写真をいただきました!土台の黒い板はご自分で準備されたようです。しめ縄がとても映えますね!ありがとうございました。(他にも完成しめ縄を見せていただいた方々ありがとうございました)
この様な状況の中で、文化部員さんはなかなか集まる事ができずに、不安だったと思います。何かあったらお手伝いします。と気にかけていただいた事がとても心強かったです。なかなか集まる機会がありませんでしたが、今後の活動も出来る事を少しでもやれていけたらよいなと思います。12月の文化展も色々、企んでおりますので。。。部会でお逢いできる事を楽しみにしております。今回の文化セミナーでは、様々な経験をさせていただきました。1番は、ありがとうございました!!の感謝の気持ちなのですが、一言では納めきれない程の想いがぐるぐる渦巻いております。今回「お花のある暮らして彩りを」とサブテーマにしてくださった明香先生との御縁も、皆さんとの御縁も今後さらに大切にしていきたいと思います。また、ワークショップやおはなあそびのイベントで明香先生と実際にお逢いできるとよいですね。
10月のLessonは、秋の実物を使った生花アレンジ。黒の花器で大人な感じのアレンジ予定です。
⇒こちらは御自宅にて、10月に糸掛曼荼羅とコラボWS。タイミングが合う方は連絡をください♡
11月には、「御自宅にて、来年度のカレンダ-にドライフラワーでアレンジ」。12月には「御自宅にて、しめ縄作りやキャンドルアレンジ」などなど、魅力的なイベントも予定されているようです。私は、環境が落ち着いたらすぐにでも御自宅レッスンに伺いたいです!本当にありがとうございました。

文化部長 芝原明恵
㊹オンライン文化セミナー1日目 開催!
9月13日
保護者の皆さま こんにちは。文化部長の芝原明恵と申します。
今週から給食も再開した学校生活のスタートです。皆様、子ども達、ともに元気に過ごしていらっしゃいますか。先週10日は、『世界に一つだけのオリジナルしめ縄を作ろう』と称したオンライン文化セミナーが開催されました。当初は対面で行う予定でしたが、急遽オンライン開催に変更させていただきご心配をお掛けしました。先生方、保護者の方々が寛容に受け止めてくださり無事に1日目を終えることができたと思います。あらためて皆さまに感謝申し上げます。
野中会長のご挨拶も、急遽画面越しとなりましたが 温かい言葉とともにセミナーがスタートしました。午前の部、午後の部、それぞれ35名程ご参加いただきまして楽しい時間を過ごすことができました。直接、講師の鶴見明香先生とはお会いできなかった講習ですが、講師の先生は、画面を通じて参加者の皆さんと交流が持てた事を大変喜んでおられました。
セミナー中は、画面越しにペットちゃんが出現したり、分散登校前の子どもたちや帰宅後の子どもたちの姿も見る事ができました。直接参加者の皆さんと会う事ができなかったのですが、画面を通じて同じ時間を共有出来たことがとても嬉しかったです。
セミナー中は、グルーガンの使い方に苦戦する方、1メートル程ある水引きの形成に苦戦された方、講師の先生が可愛くて癒されたと仰る方、しめ縄をプレッツェルの様に縛ってみた方、それぞれの場所で様々な経験をされたのではないでしょうか。また、直接お会いできた時には、貴重なエピソードを伺いたいです。
セミナー後は、少人数グループに分かれて雑談会を設ける事ができました。(ブレイクアウトルームと言うそうです。無知ですみません。)それぞれのグループに短時間ですが、講師の先生も参加してまわり、交流を持つ事ができました。
午前の部、午後の部、誰一人同じしめ縄はなく、形も色も全てオリジナルの作品がとても素晴らしかったです。講師の先生が丁寧に進めてくださり、作り方の図案も用意してくださったおかげで、時間内には皆さん作品を仕上げる事ができました。2日目に参加予定の皆様、どうぞご安心ください!
一点気をつけていただきたい事は、グルーガンの先が思った以上に熱くなります。火傷には充分ご注意ください。初めてグルーガンの操作をする方は意外と苦戦をするようです。ボンドは速乾性がありますが、熱い!量が適度でない!などなど。もし、お時間ありましたら、セミナー迄に一度操作をしてみるとよいかと思います。グルーガン操作に苦戦していたら出遅れてしまった!という方も見えたようです。が、ちゃんと確実に作品は完成しますのでご安心下さい。何か困った事がありましたら、たくさん声に出していただきたいと思います。
あとは、参加者のお洋服の色目!さすがお花を取り扱う先生ですね。赤の洋服を着ていらした保護者の方を見て、即イイ!と仰ってみえました。赤い服を着て参加しなきゃ とは思わずに(笑)原色のお洋服ですと、画面中の多数の中からすぐに見つけてもらえるメリットがあるかもしれません!?すみません、参加時の服装は自由です!!
17日の開催がとても楽しみです。皆さまが楽しい時間を過ごせます様に。当日を心待ちにしております。
PTA文化部長 芝原 明恵
㊸「地域貢献・連携」の大切さ
Google MeetでのオンラインSTが始まりました。急な家庭学習への変更にもかかわらず、先生方にもスムーズに対応いただき、子供たちも日常のインフラのようにオンラインSTに取り組めており、ありがたい限りです。
夜に配信された学校からの自宅学習決定の情報が、瞬時にクラス中の皆で共有されるなど、附中生のイザという時の行動力とITスキルの高さを実感し、とても頼もしく思いました。
さて、先日、東海附連 実践活動協議会が開催されました。この会議は東海地区の附属学校の情報交換の場であり、今年度はオンライン開催です。名古屋大学減災連携研究センター長の飛田先生の基調講演「防災の面から見た 地域貢献・連携」を皮切りに、午前は講演会、午後は東海地区附属PTAの方たちとオンラインで意見交換を行いました。私たち附属岡崎中PTAが次回の実践活動協議会の主幹校ということもあり、先生方の参加だけでなくPTA役員7名も勉強のため参加させていただきました。
会議テーマは「地域貢献・連携」。附中PTAは「学校や生徒」のために活動していましたが、そこに「地域貢献」の考えを+αしていこうとのことです。他地区の附属学校PTAの事例紹介を聞く中で、印象深かったのは、
「普段から地域と連携していないと、イザ災害が起こった時に、地域の人たちは助けてくれないよ。」
「附属学校は地元の子供が少ないから、よそ者扱いされるよ」
という声でした。確かに、私も同じ助けるなら、顔見知りや地元の人を優先してしまうかもしれません。また、遠方から通う子供たちも多いので、災害時にすぐに保護者が迎えに来られないことも考えられます。
「地域貢献・連携」は、まわりまわって附属中学校生徒の災害時リスク低減につながるのだと再認識させられました。
前回の附中おやじの会では、この地域貢献を意識し、学校の周りの清掃も行いました。少しずつですが地域からも応援されるような附中PTA活動をすすめていきたいと思います。

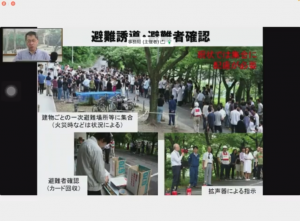
「地域貢献・連携」の大切さにあらためて気づかされた実践活動協議会2021の参加でした。
PTA会計 髙原 浩之
㊷東海附連に関するお知らせ
皆様こんにちは。PTA会長の野中です。
今回は「全国国立大学附属学校連盟東海地区会」、いわゆる「東海地区附属学校連盟」、通称「東海附連」をご紹介致します。(通称までが長いですね)
当連盟は、愛知・岐阜・三重・静岡県下の国立教育大学・教育学部附属学校で構成されており、附属学校の使命達成を図り、もって我が国の教育振興に寄与することを目的としています。具体的な活動として東海附連では毎年、東海地区研究協議会・実践活動協議会を幹事校の地域で開催し、基調講演会、教員の方々の研究発表、PTA活動報告会を行っております。残念ながら昨年はコロナ禍により中止となりましたが、今年はオンラインで開催される運びとなりました。例年ですと現地に赴く方は教員の皆様と役員会から数名をお送りするのですが、今年はオンライン開催のため、基調講演会を広く開放するとの事です。
開催日時およびテーマは
2021年8月20日(金) 11:00~12:30
「防災の面からみた地域貢献・連携」
講師:名古屋大学減災連携研究センター
センター長 飛田 潤 教授
当校のPTA活動における地域貢献・連携活動のヒント・参考になることも多いと思われます。皆様も是非、ご参加下さい。
(東海附連講演会に関する案内をアップします。参加される方は、案内の中にあるURLから入ってください)
PTA会長 野中 健史
㊶決断の時に備えて・・・
7月21日
「決断と心友」
「ああ、弟よ、君を泣く、君死にたまふ事なかれ。末に生まれし君なれば、親の情けは勝りしも、親は刃を握らせて、人を殺せと教えしや、人を殺して死ねよとて、廿四までを育てしや。」
与謝野晶子の詩です。NHK連続テレビ小説「おしん」というドラマの中で、おしんにこの詩を教えたのは、反戦を志し日本軍から脱走した俊作あんちゃんでした。あれは、山形の雪深い冬と春の出来事。しかし、私は夏になるとこの詩を思い出しては口ずさんでしまいます。原爆投下、終戦・敗戦の時期だからでしょう。詩の中での「親」は子供に何を願ったのでしょうか。生きていてほしい、生きて戦争から帰ってきてほしい。ただ、それだけだったのではないかと思います。今、自分が「親」となり、子供達に願う事は「命」を大切に幸せな人生を歩んでほしいという事ですが、日本における平和のおかげでしょうか、時に親である私も贅沢になり、「親の心子知らず」と腹を立ててしまいます。
人生とは決断の連続。サボる事も、頑張る事も全ては皆さんの決断の結果です。納得のいく決断をしていって下さい。
皆さんは「ハンカチ理論」をご存知ですか?ハンカチの真ん中あたりをゆっくりつまみ上げると、そのあと四隅がついてきて、全体が一緒に上がってきます。大好きなことが見つかってそれに熱中していると、それにつられて、それ以外のモノも引っ張り上げられるという考えです。この夏休み、決断の時に備えてハンカチの真ん中をもっともっとつまみ上げてみませんか?
冒頭で、「おしん」の山形の話をしました。中学時代を共に過ごした私の心友が山形で活躍しています。お互いの決断を共に見守ってきた仲です。彼も得意の英語と持前のひょうきんさで、ハンカチの真ん中をつまみ上げた一人です。この寄稿の筆をおいたら彼に連絡してみようか。限られた中学3年間。皆さんが自分の特技に磨きをかけ、また、心友ができる事を祈っています。
PTA会長 野中 健史
㊵この夏、素敵な本との出会いを!
7月12日
雨が続いておりますが、皆さま日々いかがお過ごしでしょうか。先日、PTAから配付させていただきました図書アンケートでは、色々な方よりご意見をいただきまして本当に感謝しております。少しご紹介させていただきたいと思います。(勝手に載せて申し訳ありません。)


・コロナ禍だからこそ実際には出掛けることの出来ないところへ、妄想旅行しましょう。何年か後に、実際に行くことができることを夢見て… 国内外の旅行関係の本をオススメ!
・読むための本も大切だけど、なかなか自分では購入しないような写真集や画集なども気軽に手に取れる図書室で出会って欲しい。気分転換にも!!
・13歳前後に出会った本です。今回、30年程前の記憶が蘇り、とても懐かしく、嬉しく思いました。現代の中学生が読んでくれたら、どのように感じてくれるのでしょうか。多感な時期にたくさんの本を読み、こころを豊かにしてもらいたいです。
・母親に読んでもらった本は今でも覚えていて忘れてはいません。by.B先生
心温まるご意見とともにオススメ本をたくさん書いて頂きました。他にもビジネス本、哲学本、絵本、芸能人が出した本、様々な本をご紹介いただきました。
特に期限は設けておりませんので、ふっと思いついた時にまた保護者の皆様のオススメ本をお知らせくださいませ。おじいちゃん、おばあちゃんからのオススメ本!も知りたいです。この機会にご家庭の中で、本についての話題があがるきっかけになったら嬉しいです。用紙が無くても、お好きな紙にご意見を書いていただき担任の先生へお渡しくださっても大丈夫です。
今回、お寄せ頂いたオススメ本を 君達に贈る物語と題して一覧表にしてはどうでしょうか。と野中会長よりアドバイスを頂きました。素敵な言葉も添えて。。。
人は、それを求めている時に自然とその本を手にしているものだ。それを本棚に戻すのか、開いてみるのかで君達の人生は変わる。 By 北杜夫
本を読むと新たな発見や感情が残り、いつまでも自分の中に漂っているものだと思います。無くなることなく少しづつ自分に蓄積していく感じがとでも好きです。夏休みに突入します。子ども達の心に素敵な本がたくさん残っていきますように。そんな想いを細々と、またこのPTAブログでお伝えできたらよいなと思っています。
PTA図書応援団
㊴リアルにつながる ~「第1回附中おやじの会」~
6月26日
皆さん、こんにちは。今年度、2年学年代表・書記の鈴木です。
緊急事態宣言が解除され「おやじの会」が開催されました。突然の開催だったにもかかわらず保護者約50名のご参加となりました。とくに会社を午前中だけ休んで来て頂けた方や、駐車場が少ないことに配慮して公共交通機関で来られていた方々など本当にご苦労様でした。そして、これほどの人数が集まったのは、やはりリアルな人とのつながりを求めている表れかもしれませんね。
さて、今回は野中会長の発案で「地域貢献隊」と「グランド整備隊」の2班に分かれて清掃活動が行われました。先ず前者は附中正門前の歩道で北の歩道橋から南はローソン周辺までに捨てられている空き缶やペットボトルを拾い集めました。日頃、通学でご迷惑をおかけしている附中近隣住民の方への感謝をカタチにしたとても良い計画だと思いました。


そのあと後者のグループと合流。後者はグランド整備と南側出入口のブロック敷きです。グランド整備は大変蒸し暑い日にもかかわらず、トンボを使って固いグランドの凹凸ならしと草取りをしました。皆さん、額に汗をかきながら無心になって作業をしてました。



ブロック敷きはグランドの南側に舗装用として約200個ほど並べるのですが、1つ並べるのに先ず試し置きをしてから足で安定性を確認し、少しでもぐらつきがあればまた取り外しを2~3回繰り返すという、もはや職人と言ってもよい根気のいる作業でした。戸田校長先生も一緒に汗を流しながらブロック敷を作業されていて頭が下がる思いでした。



休憩時間になるとあちらこちらで小グループをつくり自然に会話と笑いが生まれていました。子供のクラスがわかる名札をつけていたので、同じクラスでつながったのではないでしょうか。



そして今回改めて気づかされたことは、今まで当たり前だと思っていた人と人がリアルで出会うことの大切さです。決してオンラインはまた別の良さはありますが、やはりリアルの方がより思いもつかない様な建設的な意見が生まれると思います。
例えば今後の方向として地域貢献隊としての活動を更に発展させ、お揃いのポロシャツを着て清掃活動をし、その写真を新聞等のマスコミにPRしたり、お隣の竜海中学校とコラボして一緒に活動出来ないかという話し合いが出来ました。実現出来れば駐車場不足の解消にもなるとてもいいアイディアだと思いました。
人は人によって磨かれ、成長してゆく。リアルにつながることで一人では不可能と思うことでも限界を乗り越えていける。そんな可能性がリアル開催にはあるのではないでしょうか。
今後、おやじの会が更に進化を遂げて新しいことに挑戦していく会になってほしいものです。
PTA書記 鈴木 友則
㊳世界に一つだけの附中PTA文化部の活動に!
6月22日
皆様こんにちは。
今年度、文化部部長を務めて参ります。芝原 明恵と申します。どうぞ一年間よろしくお願いいたします。先日、コーラス部の初顔合わせがありました。㊲では「PTAコーラス部始動!」と題し、コーラス部の三役さんからのことばも紹介させていただきます。
文化部につきまして本年度は、『世界に一つだけのオリジナルしめ縄を作ろう!』というテーマの元、講師に鶴見明香先生をお呼びして講座を開く予定で進めております。数日中には募集おたよりを配付させていただきます。同時に体育部スポーツ懇親会募集おたよりも配付予定です。
保護者の方々とお話する機会に『今年は、オンラインですか?対面ですか?』と尋ねられる事があります。『前年度はzoom開催でよかったよね。今年は対面で考えています。』とニヤニヤして答える自分がいます。
前年度は、コロナ禍でも講師の先生や本校の先生方、PTA役員の方々と試行錯誤しながらzoomによる文化セミナーの開催が出来ました。簡単な様にみえますが経過は様々大変であったと思います。(自分は本当に微力でした。。。)誰一人、zoomでできる?無理じゃない?という言葉、想いはなく ただただ成功させようと前向きでしかありませんでした。そんなzoomによる文化セミナーは本校の歴史に残る行事だと思っています。
本年度は、対面で講師の先生と参加者の皆様と作品作りが出来ることに今からワクワクしております。講師の鶴見先生から『参加される保護者の方々にワクワクを沢山感じて欲しい!』この様な想いを教えていただき大変嬉しく思っております。鶴見先生のご希望に最大限添える様に、文化部部員一同がんばります!
情報社会の中、『見えない人とつながること』、『情報を沢山持ち語る事が出来ること』がなんとなくすごいのかなと感じられる世の中もよいですが、目を見て言葉をかわし、表情を感じる、ことばの温かさを感じる。 コーラス部の練習も、文化セミナーもそんな大切で、温かな時間になったらいいなと思っています。
保護者の皆様、ぜひワクワク感を求めて様々な行事にご参加くださると嬉しいです。
PTA文化部長 芝原 明恵
㊲PTAコーラス部始動!
6月22日
皆さん、こんにちは。コーラスクラブです。P T Aブログをちょっとお借りして、活動の紹介と宣伝をさせていただきます。
突然ですが、子どもが中学生になると、親子の関係も変わり、少し距離を感じたりもしますよね。自立の過程と思えば頼もしくもあり、頼られないことが寂しくもあり。悩んだり、苦しんだりしているときは、いつも一番近くで見ているよ、と励ましてあげたくなります。でも、直接言うのは、ちょっと気恥ずかしい。そんなときでも、歌でなら伝えられます。ありったけの気持ちを込めて歌っても大丈夫。聞いている人の心を打つハーモニーになります。
誰よりも転んで 誰よりも泣いて
誰よりも君は 立ち上がってきた
僕は知ってるよ
誰よりも君が一番輝いてる瞬間を
夢を追う君へ
思い出して くじけそうなら
いつだって物語の主人公が立ち上がる限り
物語は続くんだ sekai no owari『サザンカ』より
いや、それでもこのコロナ禍で、どうやってコーラスの練習をするの?なんだか大変そう。
そんな心配をしていらっしゃる方もいるでしょう。
ご安心ください。みんなで一つのハーモニーをつくることは、諦めるにはもったいないくらい素敵なことだと私たちは思っています。ですから、できる方法を工夫して考えます。皆さんが安心して楽しめること。いつか一緒に歌えるときを常にイメージし続けること。附中のコーラスクラブですから、一味もふた味も違います。
蔓延防止等重点措置が取られている間はオンラインにて先生と一対一でのレッスンを行います。(スマホ、タブレット、パソコンなどがあれば特別な機材などは必要ありません)夏休み中は、楽譜、CDを使いそれぞれが個人練を重ねます。
二学期以降は状況を見ながら活動を行い、文化祭では先生方とコラボ発表を目指します。さらに練習を重ね、年明けには岡崎市PTAコーラス連盟フェスティバルに参加予定です。
はじめよう やってみよう
誰でも最初は 初心者なんだから
やったことないことも やってみよう
苦手な相手とも 話してみよう
知らなかったこと 見たことないもの あたらしい 楽しい (Try Try)
WANIMA 『やってみよう』より
先日顔合わせ会を行いましたが、まだまだ引き続き部員募集中です!





コーラスがやってみたい方はもちろん、「新しいことをやってみたい」
「お友達を作りたい」「先輩お母様方から情報をゲットしたい」
「学校に行く機会がないので行ってみたい」
どんな理由でも大歓迎です。楽譜が読めなくても全然問題ありません!
素晴らしい先生のご指導のもと、私たちと一緒に楽しく活動してみませんか?気になった方は、以下の添付資料に掲載するコーラス専用のアドレスに直接ご連絡いただいてもよいですし、お手元に用紙があれば提出していただいても結構です。
新しい仲間にお会いできることを楽しみにしています!
PTAコーラス部
㊱コロナ禍の中だからこそ見えてくるもの
6月14日
こんにちは、野中です。
PTA役員として、先生方と連絡を取る事が多くなっています。そんな中、とある先生から、この様な熱いメッセージを頂きました。PTAの皆様だけでなく、生徒の皆さんにもご紹介したく先生ご本人の許可をようやく得て、投稿させて頂きます。
『3度目の緊急事態宣言が発令されることとなり、
昨日、(4月)19日から始まる
2年生の自然体験活動を「延期」と判断しました。
現段階では修学旅行と同時期に行く予定で、
日程の調整を進めております。
自然の前に、人の力ではどうにもならないこともあります。
でも、「延期」の話をした時の2年生も、
「準備の時間ができたと思えば良い」と前向きな発言をする
附中生もおり、たくましさすら感じました。
1年生のオリエンテーション合宿も、
宿泊をなしとした形で、
昨日から予定していたプログラムを開始しました。
金曜日には悔しさを担任の先生にぶつけていたようですが、
週明けには次に気持ちを切り替えて、活動にも熱中していました。
私が思うに、入学からの短い期間で、
1・2年生は、コロナ禍でもできる方法を考え、実行する
3年生の姿を見て、もうすでに学んでいるのだと思います。
先輩が下を向いている学校であれば、
きっと後輩もそれがベースになりますよね。
そういった意味で3年生の魅力や、
もっと言うとこの附中の伝統が素晴らしいのだなと
改めて感じる1日でした。
長々と書いてしまいました。
また私たち教員も、「コロナがこうやってくるなら、
この角度から攻めてやる」という強い気持ちをもち、
学びをたくさん生み出していきたいと思います。』
先生の様な生徒想いの熱い教員がいらっしゃるのも、附中の伝統ですね、馬場教頭先生。
PTA会長 野中 健史
㉟PTA体育部会の活動が始動!
6月7日
皆さん、こんにちは。
今年度、3年学年代表・体育部部長を務めさせていただきます大河内です。
1年間よろしくお願いいたします。
今回は、体育部のビッグイベントである「スポーツ懇親会」に向けてのお話をさせて頂きます。まだまだ見通しの立たない環境が続いておりますが、先日1年ぶりに体育部会を開くことができました。スポーツ懇親会は附中PTAで引き継がれている大変意義のある行事の一つです。『今だからこそ出来ること』を念頭に掲げ取り組んでいきたいと思っております。
今年度のテーマは【スポーツウォークラリーin附中】です。
各グループに分かれて先生方や保護者の方々と懇親を深めつつ、三つの競技を楽しく競ってもらいます。競技種目は、玉入れ、ボール運び、そして体力測定です。先日の体育部会では、これらの競技を実際に体験することでよりよいものへとつくり上げていくことができました。私たち保護者もこのような経験を通して、附中の子どもたちのように、横のつながりだけでなく、縦のつながりも広げていくことができる素晴らしさを体感しました。
それでは、各競技について少し説明したいと思います。
◎玉入れ
皆さんの想像する玉入れではなく、附中体育大会の障害物リレーで行う玉入れです。簡単そうにみえますが、精神力とチャレンジ魂が試される競技です。


◎ボール運び
バドミントンのラケットにテニスボールを乗せて決められたコースを疾走?する競技です。

◎体力測定
懐かしの体力測定です。今回は、握力、垂直とび、反復横跳びの測定をします。本来反復横跳びは20秒での測定ですが、私たちの年齢と体力を考慮し10秒としました。

例年通りの競技とはいきませんが、感染対策を考慮しつつ、楽しくスポーツ懇親ができる時間にしたいと思っております。皆様のご参加をお待ちしております。
なお、スポーツ懇親会の参加希望調査票は6月下旬に配布予定です。
体育部長・3年学年代表 大河内 彩
㉞『部活にかける熱い思い、悔しさの狭間で』
5月19日(水)
今年度、PTA副会長を務めさせていただきます北村恭子です。
1年間どうぞよろしくお願いいたします。今なお、目に見えないものに世の中は振り回されています。PTA活動において、昨年度から「今だからこそ出来ること」を考え動いています。
その一つがこのPTAブログ。バトンは引き続き受け継がれています。
今回、野中会長からいただいたお題は「総体について」でした。しかし、岡崎市中学校総体は中止。サッカー部の息子は、その事実を知ったとき大層悔しがっていました。数少ない試合のひとつが無くなってしまう…と。
附属中は他校よりも部活にかける時間が少ないですが、その中でも工夫しながら活動しているのを傍でずっと見てきました。試合結果が送られてくる学校からのメールに「惜敗」と流れてくることがあります。
その中に色々な「惜敗」が含まれていることをご存知でしょうか?
サッカー部でいえば、4月に開催された大会では、結果0-0、PK戦0-1で惜敗。他の部活においても同じようなことがあります。
惜敗の言葉の裏側には、様々な熱い思いや悔しい思いがあふれています。
ライフワーク、体育大会、文化祭、宿泊行事などの主要イベントに隠れがちですが、部活動も大切なひとつです。仲間とともに悩み、練習し、協力し、目標に向かっていく姿は清々しいものがあります。
3年生にとっては、残りわずかな部活動。
先輩方から受け継いだ部内の伝統を後輩達に引継いで、近い将来「勝利」のメールが流される日がくることを願っています。
PTA副会長 北村 恭子
㉝新入生の皆さん、ご入学おめでとう!! 在校生、見せてやれ『底力』!!
5月7日(金)
令和3年度PTA会長を務めさせて頂きます野中と申します。
新入生の皆さん及び保護者の皆様、ご入学おめでとうございます。附中生活が始まり1カ月が経ちました。西三河・東三河の各小学校から集まった皆さん。これも、ご縁ですね。既に自分の意見を発信し、リーダーシップを発揮している人もいるでしょう。どんどん続けて下さい。また、積極的な仲間に圧倒されて驚いている人もいるでしょう。どうか安心して下さい。今は手を挙げられなかったり、意見を言えなかったりしているかもしれません。でも、皆さんが刺激を受けて考えていることこそが、皆さんの成長であり、附中全体の成長となっています。じっくり考えて、いつの日か皆さんが自分の意見を発信できる時がきっときます。1/36が経過しましたが、この1/36の経験を生かして一歩ずつ階段を登っていきましょう。
話は変わりますが、GW中、妻に薦められてYouTubeで『カ○リーメイト』のCMを見ました。人生の夢であった夏の甲子園をコロナの影響で予選すら参加できず、大学受験に突入する高校生。野球部の監督兼担任の先生とのやり取りが描かれています。
「きついッスね」
『そうだな』
「やれることやるしかないッスよね」
『だな』
『うまくいかない時に、それでも続ける努力を底力っていうんだよ、うん。』
「見えないものと闘った一年は、見えないものに支えられた一年だと思う。」
『見せてやれ、底力』
今年度も授業、研究活動、学校行事、PTA活動は昨年度に続き、今まで通りとはいかないでしょう。でも、後退せずに形を変えて、実現していきましょう。生徒の皆さん、PTAは皆さんにとって『見えるもの』でもあり『見えないもの』でもあります。いつも、皆さんの成長を見守り、支えている大人がいることを信じて下さい。そして、『見せてやれ、底力』
保護者の皆様、附属中学校に来る機会も制限され、お子様の環境をご自身の目で確認できず、不安な事もあろうかと思います。今年度もこのブログを通じて、少しでも附属中学校の様子や他のPTAの想いをお伝えできたらと思います。時には皆様方にも投稿をお願いする事もあろうかと思います。また、「伝えたい」とお考えの事がございましたら、是非、連絡をお待ちしております。
令和3年度もどうぞ、宜しくお願い申しあげます。
PTA会長 野中 健史
㉜ みなさんに感謝、そして附中生の活躍の時がきた!
3月31日(水)
PTA会長の齋藤です。
今年度最後の更新をさせていただきます
<卒業生業生の皆さん>
卒業式から約1か月が過ぎ、もうすぐ新しいステージになりますね。
不安もあり楽しみもあり、という心境でしょうか。
皆さんは気がついていないと思いますが、今皆さんには附属中での学びが体に染みついていると思います。
これは、次のステージに行くとわかります。
附属中の授業、先生、仲間がいかに積極的であったか。
ひょっとしたら最初は附中ロスでつまらなくなるかもしれませんが、そこは切り替えて皆さん自身が次のステージを積極的に盛り上げていってください。
卒業式の祝辞でもお話をしましたが、君たちがいたから、私たちは成長を見守る喜びを得ることができましたし、沢山の感動がありました。ありがとう。
人間が人間に贈る最大の贈り物、それは『よい思い出』です。
立派な品物でもいつかは壊れたり色褪せたりします。
でも、よい思い出は一生変わることはありません。
壊れることもなければ色褪せることもない。一生続きます。
私たちは君たちから『よい思い出』をもらいました。
そして、君たちは仲間や先生にも『よい思い出』を贈りました。ありがとう。
<卒業生を含む在校生の皆さん>
今日の日本経済新聞にこんな記事がありました。
2022年度からの高校の教科書に「知識を用いて実践や議論に取り込む『探求型学習』」が多く取り入れられたとのことです。
「『主体的・対話的で深い学び』によって思考力や表現力の育成を目指す」、「現代社会の諸課題から主題や問いを設定し、追及したり探求したりする学習の展開」との記載がありました。
これらは、まさに君たちが附属中で学んだこと(学んでいること)ですね。
いよいよ附中生の更なる活躍の時がきました。
今までの附属中での学びを生かして、益々の成長を期待しています。
<教職員の皆様>
例年どおりのリアル総会ではなく、書面決議での総会。
体育大会と文化祭を凝縮して行った附中祭。
育朋館は3年生と保護者と先生方のみ、1、2年生は教室で映像を視聴。
自宅でも保護者がWEBで視聴できる卒業式。
もちろんこれらだけではありません。
コロナ渦の中でも学校運営のため、生徒たちのために試行錯誤し、あるいは生徒たちに試行錯誤させ、最善の方法で行事を行っていただけました。
さすが元気のいい附中の生徒たちを指導する附中の先生方はすばらしいなあと敬意を表します。
そして、追究や日々の授業の中で子供たちに自ら考える力、生きる力をつけてくださったこと心より感謝申し上げます。
<保護者の皆様>
コロナ渦の中、家庭での時間が増え、子どもと親のかかわりが増えた1年でした。
附属中の保護者の皆様は子どもへの愛情がとても深いと感じています。
子どもたちのストレスが溜まる自宅学習期時期でも、保護者の愛情のおかげで子どもたちは健やかに成長できたのではないかと思います。
この保護者の子どもへの愛情が、子どもたちの心を落ち着かせ、学校でのびのびとした活動につながり、これが附属中全体の活動によい影響をもたらしていると思います。
附属学校園の特徴でもあり、学校の発展のベースでもあります。
ありがとうございます。
PTA活動は、例年とは異なる形になりましたが、「オンライン文化セミナー」、「懇親ウォーキング」等に参加いただいた皆様、ありがとうございました。
さすが附属中の生徒の保護者ですね。
WEBセミナーでも問題なく楽しんでいただけました。
「おやじの会」は2回開催し、子どもたちの活動を支えていただきました。
ありがとうございました。
懇親会ができなかったことは残念でした。
いろいろな方と子どものことを語り合いながらお酒を飲みたかったです。
附属中では、生徒自身のがんばりはもちろんのこと、すばらしい先生方、そして愛情深い保護者、この三者のよい関係のおかげで、現在の附属中があると思います。
本当に感謝です。
PTA会長 齋藤登
㉛ そうならねばならぬのなら~3年生の卒業に寄せて~
2月26日(金)
『さようなら、とこの国の人々が別れにさいして口にのぼせる言葉は、もともと「そうならねばならぬのなら」という意味だとそのときわたしは教えられた。「そうならねばならぬのなら」。なんという美しいあきらめの表現だろう。西洋の伝統のなかでは、多かれ少なかれ、神が別れの周辺にいて人々を守っている。英語のグットバイは、神がなんじとともにあれ、だろうし、フランス語のアディユも、神のみもとでの再会を期している。それなのに、この国の人々は、別れにのぞんで、そうならねばならぬのなら、とあきらめの言葉を口にするのだ』
(須賀敦子 『遠い朝の本たち』より)
大好きな須賀敦子さんのエッセイの中で、たしか日本語の「さようなら」についてふれた部分があったはず・・・。
その部分がとても印象に残っていたのだけど、どのエッセイだったか思い出せず、久しぶりに全集版を引っ張り出して探しました。
読み返してみると、この部分は須賀さんの文章ではなく、須賀さんが中学生の頃に読んだ世界文学全集の中の、アン・モロウ・リンドバーグの文章の一節でした。
(アン・リンドバーグは、太平洋単独横断飛行を初めて成し遂げた、あのリンドバーグの奥さんです。アン自身も女性飛行士として活躍していたのですが、上の一節は、夫婦でテスト飛行中に、日本の北海道に不時着し、日本人に救出されたときに書いたものだそうです。)
戦時中、中学生だった須賀さんはこの文章にふれ、「日本語だけ」の世界から解き放たれた、と書いています。
わたしが初めてこの文章を読んだときも、日本語の「さようなら」に、母国語でない人はそんな響きを感じ取るのか、と思い、驚いたと同時に聴き慣れた日本語をより美しく、新しいもののように感じました。
同時に、同じ別れを告げる言葉ではあるけれど、さようなら=グッドバイ、ではなく、=アディユ、でもなく、別れに際してその国の人がそれぞれに深い思いを込めているんだなとも感じ、翻訳って面白いと思いました。
去り難いけれど、名残惜しいけれど、まだ語り足りないことがあるけれど、もう行かなければ、先へ進まなければ。
そうならねばならぬのなら・・・。
言葉の後の空白の中に、言葉にならない、たくさんの思いが詰まっています。
それまでは、「さようなら」ってなんだかお別れ感が強くて、すこし他人行儀な、冷たい言葉のように感じて、「またね」「じゃあね」ですませていたけれど、本当はこんなに、いろいろな思いを込められる豊かな言葉だったんだと気づきました。
来週はいよいよ三年生は卒業の日を迎えますね。
そして、三年生の皆さんはそれぞれに新しい踏み跡をつけながら進んでいきます。
楽しかった附中は去り難いけれど。
友達や先生と別れるのは寂しいけれど。
「そうならねばならぬのなら・・・」。
余白の中にある、言葉にならない無数の思いが込められたたくさんの「さようなら」が行き交うことだろうと思います。
別れがたい気持ちをあきらめながら進んでゆく皆さんの姿をずっと見守っています。
そして、子どもたちに他ではできない学びを与えてくださった学校と職員の皆様方に、深く感謝いたします。
答えのない問いに対して考え続け、友達と議論を交わし、先生以外の大人の意見を聞きに行く追究の授業では、教科書を書き写すことではわからない問題解決の方法にふれることができたと思います。
この先、子どもたちが生きていくにあたって、必ず実をむすぶ学びになることでしょう。
ここでは語り尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。
保護者にとっても、3年間の附中生保護者生活から卒業する、お別れの季節です。
そうは言っても、なかなかあきらめの言葉を口にするには躊躇ってしまいます。
・・・卒業の日まで、あきらめ悪く粘ろうと思います。
中嶋あかね
㉚ われらの学園~「第2回附中おやじの会」~
2月22日(月)
皆さまこんにちは。
PTA副会長の杉田と申します。
日頃はPTA活動に対しまして、ご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。
さて、2月20日(土)に、恒例の「おやじの会」を開催いたしました。
当日ご参加いただきました父兄の方、先生方たいへんおつかれさまでした。
昨年度、一昨年度と、卒業式の前に、主に育朋館の掃除を行いましたが、本年度は、3年生の教室を中心に、エアコン、蛍光灯掃除、ロッカーの補修などを行いました。



私は3Cの担当で、奇しくも35年前に、私は3Cの17番のロッカーを使用していました。
35年が経った今でも綺麗に使ってありまして、「さすが歴代の附中生だ」と感慨無量でした。
おやじの会の目的は、日頃子どもがどのような環境で学校生活を送っているか知ることや父兄同士の交流・親睦、子どもが通っている学校へ感謝などを含めた奉仕活動をするものです。
本年度は新型コロナの影響で開催が危ぶまれる中、清掃活動後の親睦会は残念ながら開催できませんでしたが、奉仕活動は何とか2回開催することができました。
これもひとえにPTA会員の父兄の皆様、教職員の皆様のおかげだと思います。
文書で失礼いたしますがお礼申し上げます。
今後新型コロナウィルスが終息いたしまして、来年度以降も附中伝統のおやじの会を開催できますことを祈念申し上げます。
㉙ 附中ならではのPTA~1年生理事・評議員会~
2月12日(金)
皆さん、こんにちは。前回、名乗り忘れました中嶋です。
三学期も残り少なくなり、このブログも終わりに近づいてきました(たぶん)。
「ブログ、読んでますよ」「楽しみにしています」というお声も(たまに)いただき、大変ありがたく、嬉しく思っています。(一の声を千ぐらいに受け取っている)
皆さんに直接お会いしてお話しする機会がなかなかなもてないなかで、PTAの発信の場としてブログの活用をご提案いただいた森先生に、改めて感謝いたします。(想定以上にやりたい放題になっていないか若干心配ですが…)
従来通りの活動はしばらく難しいかもしれません。
しかし、来年度以降も、職員の皆様とともに、子どもたちを見守り、サポートしながら、自分たちも新しい試みに踏み出しチャレンジできるような「附中ならではのPTA」であるだろうと思っています。
このブログも誰かが引き継いでくれるはず!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
さて、例年通りであれば、3学期は1、2学年の保護者会・評議員会が開かれ、来年度に向けての生徒たちの取り組みを見たり、授業参観、講演などが行われたりしておりました。
今年度は、2年生は1/14に保護者会を行うことができましたが、1年生は緊急事態宣言の発令もあり、理事・評議員会のみ、2/10に行うかたちになりました。
ご多用中、またこのような状況の中、参加いただきました皆様、ありがとうございました。
昨年の4月、臨時休校からの始業という不安定な状況の中で、評議員をお受けいただいた皆様には、大変感謝しております。
役員個人として考えますと、保護者の皆様の「何か学校のためになることを」「子どもたちの助けになることを」というお気持ちを十分に活かすような活動をご提案できなかったこと、また、その結果、一部の役員の方々に大きな負担があったのではないかということをとても反省しています。
「もっとこうすればよかったのに」「あれをやりたかったのに」というご意見、アイデアをぜひ、来年度以降の活動に生かしていっていただけたらありがたく思います。よろしくお願いいたします。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
ところで、今日のモリモリ書店で紹介されている『おもろい以外いらんねん』の大前粟生さんですが、偶然(この言葉が大好きです。前号参照)、同じ著者の前作『ぬいぐるみとしゃべる人はやさしい』を読み終わったところでしたので、ご紹介して終わりたいと思います。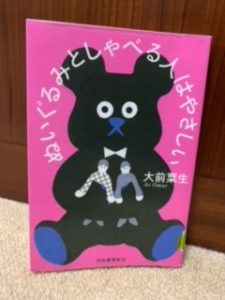
「ぬいしゃべ」は短編集ですが、表題作は、京都のある大学で「ぬいぐるみサークル(通称ぬいサー)」に入っている男女のお話です。
「ぬいサー」は、ぬいぐるみに向かって、誰にも言えないような秘密や愚痴、自分の気持ちなどを打ち明ける、という不思議なサークル。本当にあるのかなあ。興味深いです。
女性であるというだけで、性的な暴力の対象になってしまうこと。
男性であるというだけで、自分が女性から恐怖の対象になり得ること。
ただ、自分がそのように生まれてきたというだけで、誰かを傷つけたり、傷つけられたりし得るということに怯えて、あらゆる関係に踏み込めない繊細な若者たちの姿を描いています。
もしかしたら、この「はっきりしなさ」にイライラするという人もいるかもしれませんが、私は、「傷つきやすさ」「弱さ」を否定的に描いていない感じがとてもよいなと思います。
何かが「よい」とも「悪い」とも決めきれないけれども、お互いの心地よさを関係の中で探り合いながら生きていくというのが大事かなと思います。
そうそう、ちなみにこの短編集には、弟が、ユウキという相方とお笑いコンビをつくっているという女の子の話が出てきます。
弟たちが暴力的な表現で笑いを取っていることに傷ついてしまい、恋人ともうまくいかなくなってしまいます。
『おもろい以外いらんねん』と一緒に読むと、面白そうですね。
ずいぶんおまけが長くなりましたが、これが本題という噂もちらほら…。
㉘ 「正しい道」も「失敗」もない~3年生へのメッセージ~
2月5日(金)
皆さん、こんにちは。
三年生の皆さんは三日間にわたる私立高校の入試が終わりました。
その前に、私立の推薦などで、すでに4月からの進学先が決まった人もいるかもしれませんね。
あるいは、3月の公立高校の入試を第一の目標にして、これから一層受験勉強をがんばっていこうと思っている人もたくさんいるでしょう。
「いま自分の前に、何本かの分かれ道があって、どの道を進むかによって、この先の自分の未来が決まる。」
もしかしたら、皆さんはこんなふうに感じているかもしれません。
「人生の岐路」なんて言葉もありますよね。
だから、いまがんばって、正しい道を進まないといけない。
私も、受験生のときは、そんなふうに感じていたような気がします(実はよく覚えていませんが)。
しかし、最近、そうじゃないんだな〜ということに私は気づきました。
気づいたというか、いろいろ考えたところ、今はそういう結論になったという感じです。
それは、「道なんか、どこにもない」ということ。
自分が、一歩踏み出すと、その先に無数の選択が分岐するだけ。
その踏み出す一歩は、自分でコントロールできても(例えば「目標に向かって勉強する」とか「病気を予防する」とかそういう試み)、それが結局どうなるかは「未知数」で、行ってみなけりゃ、やってみなけりゃわからない。
どんなに確率が高くても、低くても、「そうなるか、そうならないか」のどちらかしかない。
そして、どうしてそうなったのかは、結局のところ偶然で、私たちは、無数の偶然を積み重ねて、自分の道をつくっているんだな、ということ。
だとしたら、その偶然を楽しんで、噛み締めて、「深い深い踏み跡」をつけながら、歩いていきたいなと思うのです。
「道なんて最初からない」ので、「正しい道」もないし「失敗」もない。
目指すところに100%たどり着ける方法もないし、近道もない。
よい学校に行ったからよい人間になれるわけでもないし、
優秀な先生の指導を受けたから優秀になれるわけじゃない。
あなたの人生は、あなたが生きて、踏み跡をつけない限り、どこにもないのです。
だから、恐れずに。
ゆっくり行きたい人は焦らずに。
いますぐに報われなくても、あなたは損したわけじゃない。
何もまだ決まっていない世界を、じっくり引き受けて楽しんでください。
そんなふうに思いながら、皆さんを応援しています。
私も自分の世界をまだまだ楽しんでいこうと思います。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
ところで、皆さん。
戸田校長先生のお話の中でも出てきた、「P波」と「S波」のこと、覚えていますか?
「S波は横波で、液体中は伝わらない」んでしたね。
地球の知らせるその二つの振動に誰よりも耳を澄ませて、「地球の真ん中は固体である」という発見をした地震学者がいました。
デンマークのインゲ・レーマンという女性です。
それは当時の学説とは違い、大変大胆な仮説でした。
そのことをモチーフにした『八月の銀の雪』(著/伊与原新)という本を最近読んで、とっても面白かったので皆さんに紹介して終わりたいと思います。
その本の中で、レーマンに憧れ、地震について勉強するため日本に来たベトナム人留学生の女の子が言います。
「でもわたし、逆に訊きたいです。みんな、なんで自分たち住む星の中のこと、知りたくならないのか。内側がどうなってるか、気にならないのか。表面だけ見てても、何もわからないのに。」
世界にはまだまだ誰も聴いたことのない秘密がたくさん隠されていそうです。
『八月の銀の雪』は短編集なので、他にも素敵な秘密がたくさん見つかるかもしれません。
本屋大賞にもノミネートされていますので、ぜひ読んでみてくださいね。
㉗ みんなで生きる~PTA教育文化講演会~
1月21日(水)
皆さん、お久しぶりですね。中嶋です。
そして、またもや、緊急事態宣言下のブログ更新です。
もはや皆さんも動揺することはないですね。
大事なことは、『忍耐と記憶』(byジーコ)・・・じゃなくって(なんのこと?と思った方は、乗代雄介さん『旅する練習』参照←惜しくも今回芥川賞受賞は逃しましたが、今一番注目の作家さんの新刊です。おすすめ)、
- 誰かのせいにしない
- 起こったこと、感じたことを忘れない
だと私は言いました。
付け加えるとするなら、「みんなで生きる」ということでしょうか。
「自分は大丈夫」とか「自分だけよければいい」とか考えずに、困難のある人も含めて、いろいろな人たちとともに生きているということを忘れないようにしようと思います。
なんだか話が壮大に、というか偉そうになってしまいました。
これは自戒も込めて。
日々の状況を自分の目でしっかり見極めながら、出来る限りの感染予防をし、かつ欲張って毎日を楽しむことも忘れずに、過ごしていきましょう。
・・ところで、今週の月曜日。
お楽しみの「PTA教育文化講演会」が開催されました。
緊急事態宣言下ということもあり、オンラインでの配信を用意していただきました。
生徒の皆さんは各教室で、保護者の皆様もご自宅での視聴も可能となり、安心してお話を楽しむことができました。
みんなが楽しみにしていた講演(私はめちゃくちゃ楽しみにしていました)を、延期などすることなく、このような形で準備・手配してくださり、本当に嬉しく思います。
当日も含め、さまざまな調整に走ってくださった職員の皆様。
そして、みんなの期待に120%応えてくださった校長先生。
本当にありがとうございました。
正直もっともっとお話を伺いたかったので、第二弾・第三弾とあったらいいのにな・・・と思ってしまいました。
というのも、予想通りというか予想以上というか、zoomでのやり取りというハンデがあったのにもかかわらず、生徒の皆さんの質問が途切れることなく、質疑応答の時間があっさりと終了してしまったからです。
「私だって・・・、いろいろ聞きたかった・・・」
きっとそんなふうに思った保護者の方々もいらっしゃることでしょう。(私だけか)
・・・ちなみに私は、講演終了後、ひとつだけ質問をすることができました。
それは、「南極観測隊(特に、越冬隊)に、女性はいますか?」ということです。
2か月お風呂に入れないくらいなら慣れれば平気かも。
と思ったのですが、トイレや体力的なことなど、さすがに過酷かな、と思うこともたくさんあります。
私は寒いのが苦手なのでそれも辛いだろうし、あとは船旅も相当にキツそう・・・。
閉鎖的な環境で長時間生活するのに、人間力というか、協調性も必要で、それもちょっと自信ないかなあ・・・。
まあ私の話はともかく、上の質問に対する先生の答えは、「います!」とのことでした。
先生が参加された四回の観測隊。
毎回隊員として女性の方はいらしたそうですよ。
皆さん、非常に熱い学問的情熱を持って参加されているので、私がぐちぐちと気にしているような些事には心を乱されることはないそうです。
逆に、「一緒に観測をすることになる男性の隊員の方が気にするくらいです」と先生はおっしゃっていました。
というわけで、女子の皆さんも、「女性だから」と自分の夢を諦めることなく、チャレンジしていってほしいなと思います。
それから、音楽や美術、文学といった芸術分野で南極に行った人はまだいないそうなので、これから狙い目かもしれませんね。
研究者以外にも料理人や事務方など、文系の方でも観測隊に入るチャンスはあるので、ぜひともいろいろな道を探ってみてください。
ちなみにこういうお話を聞いたり、本を読んだりするたびに、「文系の学問の役割ってなんだろう」と考えてしまうのですが、実は、最近ようやくその答えを見つけつつあります。
その話は長くなりそうなのでまたいずれ(もしくは個人的に)。
※講演後、女性役員に詰め寄られる(?)戸田校長先生
㉖ 「その子の今を一緒に味わう」~2学期を振り返って~
12月14日(月)
皆さんこんにちは。中嶋です。
2学期も残すところあと数日になりました。
2学期中は、「オンライン文化セミナー」、「懇親ウォーキング」、「おやじの会清掃活動」、「コーラスクラブ」などのPTA活動にご参加、ご協力いただき、本当にありがとうございました。
変化する状況にどう対応するかを考えることで、これまでの活動を見直すよい機会ともなりました。ご参加いただいた皆様からは、貴重なご意見もたくさん頂戴しました。ありがとうございました。今後の活動に生かしていきたいと思います。
先週には(PTA活動ではありませんが)「冬のほんまつり」にも参加させていただき、とっても楽しいひとときを過ごしました。
附中祭の期間中にも強く感じたことですが、自分の思っていること、感じたことを誰かに「伝える」「表現する」ということがとても大切なことだと思います。
思った通りには伝わらなかったり、うまく言えなくて悔しい気持ちになったり。
それでも、一人ひとりが、自分の感じた「好き」や「面白い」を一生懸命伝えようとする姿はとても素敵だなと思います。心打たれます。
自分が発信するだけでなく、他の人の話を聞くことで、「ああそうなんだ!」「ああやって言えばいいんだ!」という発見もあるかもしれないし、「自分はそうは思わなかったけど、そんな考え方もあるのか」と改めて自分の気持ちを問い直すきっかけにもなるかもしれません。
自分と、他の人の考え方・感じ方が違うからこそ、「知りたい・わかりたい」という気持ちが生まれ、自分を客観的に見つめることもできるようになるのだと思います。
さまざまな制約のある今、皆さんの話を直接聞ける機会が持てたのはとても嬉しいことでした。企画していただいた森先生、ありがとうございました。
附中日記にもありましたが、今後生徒の皆さん発信で、新しい試みが生まれてくると楽しいですね!(もしも図書部、ビブリオバトル部発足の計画がありましたら、保護者枠特別部員制度など設けていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。雑用係でも可)
さて、ほんまつりのとき、自分がどんな本を紹介するか散々悩んで、結局『読むってどんなこと』(高橋源一郎著 NHK出版)を選んだわけですが(プレゼンの自己採点は35点くらい)、用意していた候補の中からもう一冊、保護者の皆さんにおすすめしたい本を紹介します。
それは『おやときどきこども』(ナナロク社刊)という本です。
福岡で学習塾を開いている鳥羽和久さんという方が、たくさんの子どもたちとその保護者の方々との関わりや葛藤を通して、おとなはどう子どもと関わっていくべきかを語りかけてくれます。
この中に描写される親子の葛藤のリアルな事例は、とても胸が痛くなるようなものもあり、我が身を省みてハッとさせられます。例えば。
「今がんばらないと将来困るわよ」「努力が足りない」「このままだと行ける学校がなくなるぞ」などなど・・・。
このような呪いの言葉を、子どもたちにかけたことはないでしょうか。
こういった呪いは、子どもの将来を心配するが故と言いながらも実は、「ちゃんとした親でありたい」という親の自己防衛から生まれたものではないかと、鳥羽さんは言います。
とっても痛烈です。
自分の子どもであっても、一人の人間として違う世界を見て違う文法を生きている。
自分の望んだ通りにならなくても、その子の今を一緒に味わって生きていきたいと思います。
受験期の子どもを持つ親としては、そうは言っても落ち着かずに右往左往したくなりますが、個々面で普段と全然違う顔を見せている我が子を観察しながら、この本のことを思い出して、「我が子ながらよくわからない。面白いなあ・・・」と思っていたのでした。
冬休みの読書にいかがですか?
(ノンフィクションばかりですいません。↓小説のおすすめは個人的に聞いてください)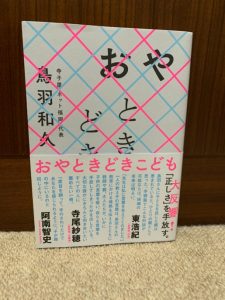
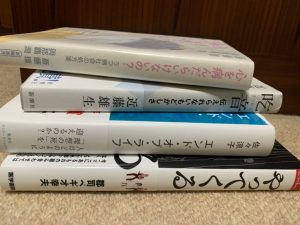
(『おやときどきこども』は本当にすばらしく、身につまされる1冊です。じっくり考えたくなることがたくさんでてきて、全親におすすめです。個人的には、子どもにもおすすめですが…。by.モリモリ書店 店長)
それから、予告からずいぶん経って、皆さんの期待が最高潮に高まっている校長先生を講師として迎える「PTA教育文化講演会」ですが、三学期に開催する見込みとなっております。詳細が決まり次第皆さんにご案内しますので、もう少し、楽しみにお待ちくださいね。
それでは、それぞれ感染予防・体調管理に努めながら、いろいろあった今年を振り返りつつ、よいお年をお迎えください。
㉕ 「われらの学園」をつくるために~続・1年生保護者会~
11月20日(金)
皆さん、こんにちは、中嶋です。
今日は、1年生保護者会の続きのお話をさせていただきます。
「タイヤ事件」(前回ブログ参照)のせいで、保護者会に参加できなかった私を不憫に思ったのでしょうか、芝原さんが保護者会で聞いた素敵なエピソードを教えてくださいました。
それは、ある日の1年D組のLTでの出来事です。
ある生徒さんが、みんなの前で、こんなお話をしたのだそうです。
少し長いですが引用します。
「係からの連絡ではないのですが、思うことがあるので話をさせてください。
附中は『自由と規律』を重んじると言っているけれど、現実はどうでしょうか。「規律」の部分が守られていない子がいます。例えば、授業の開始や給食のいただきますの時間が守れていません。
校章・クラス章・名札が正しくつけられなかったり制服を正しく着られなかったりする子がいます。
みんなのおかげで楽しく過ごさせてもらっていますが、「規律」の部分がおろそかになってしまっていては、「われらの学園」だと自信をもって言えないと思います。自由は自由でいいのだけれど、このままだと、自由をはきちがえて、附中生が附中生らしくなくなっていくんじゃないかと思っています。
後期が始まるので、もう一度気を引き締めていきましょう。」
担任の大野先生が、ちょうど同じような話を学級の生徒にしようかなと思っていた矢先に、先回りをするかのようにみんなに注意を促してくれたこと、言いにくいことをはっきりと伝えてくれたことに、先生もとても感心されていました。
勇気のいる発言ですよね。すばらしいです。
そして、このお話に感銘を受けた芝原さんから、「中嶋さん、是非ブログでこのお話を紹介してください!」と依頼を受けたのでした。
う〜ん、でも、芝原さん、人選間違えてる…。
というのは、私が中学生の時は、100%「守れない側」の人だったからです。
まず、時間が守れない。(とりわけ私は偏食が多く食べるのが遅かったので、給食の時間は苦痛以外の何物でもなく、おそらく時間内に完食できたことは1日たりともないと思います、自慢じゃないですけど…)
学校に着くのも大体ギリギリ。
忘れ物、なくし物も多く、整理整頓も苦手。
生徒手帳や定期券、傘はよっぽど気をつけていないとすぐ存在を忘れてしまう。
授業もぼんやりしていて全然聞いてない。
そんな私が、偉そうに言えることは何もない…。
言い訳をするわけではないけれど、それは決して「規律を破ってみんなに迷惑をかけてやろう」とか、「先生や大人を困らせてやろう」とか、「ルールなんてくそくらえだぜ、オレ様は好きに生きるんだ!」とか思っていたわけではないのです。
気をつけているつもりでも、ときどき、守るべきルールが本当にすっぽりと頭から抜けてしまうのです。
他に気になることがあると、優先順位がよくわからなくなってしまうのです。
みんなができていることができずに、ダメ人間だな…と落ち込むこともしばしばでした。
きちんとした友人たちから見れば、本当に腹立たしく苛立つヤツだったろうと思います。今更ながら謝ります、ごめんなさい。
だから、守れない人間代表としてのお願いをします。
(私のような子はいないと思いますが)もしも、「規律」が大事なことはわかっているのに守れない子がいたとしたら、得意な人が、少し助けてあげてほしいのです。
少し前に時間を知らせてあげるとか、ときどきルールを確認したりとか、ちょっとしたことでよいのです。
もちろん、決まりを守るのが苦手な子は、苦手だからと開き直ることなく、がんばって守れるように努力してください。
みんなが、目標に少しずつ近づくイメージです。
世の中にはいろんな人がいて、一人一人の人間の中にもいろんな顔があります。
デコボコを抱えたままで、みんなで生きていく。
そんな素敵な「われらの学園」であるといいなと思います。
㉔ 自分ってすごいんだな~1年生授業参観・保護者会~
11月13日(金)
皆さん、こんにちは。
お久しぶりです。中嶋です。
今日は、水曜日に行われた一年生の保護者会の様子について、学年代表の芝原さんがお知らせくださいます。
・・・いや、私も本当ならいたはずなんですけどね。
実はあの日、学校に到着したら、用務員さんにトントンと窓を叩かれ、「パンクしてますよ!」と。
そうです、あの日グランドにJAFのトラックを呼んだのは私。
本当にお騒がせしました。
JAFの整備士さんが「僕の中では、保護者会って結構大事な行事ですよ。スペア貸しますから、出席してから、タイヤ屋さんに直しに行ったらどうですか?」と大変親切にアドバイスしてくださったのですが、その日は三年生の修学旅行のお迎えもあり、なんとしても帰着時間までには修理しなければいけなかったので、泣く泣く保護者会を諦めたのでした。
授業参観もJAF到着までの5分ほどチラ見しただけでした・・・。無念。
そんなわけで、芝原さんのご報告を読んで、私も「そうか〜、そんな感じだったのか〜」と参加した気になりたいと思います。では、どうぞ。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
皆様、先日は、「1年生の学年保護者会」にご参加いただきましてありがとうございました。
第1回保護者会から約4か月後の今回は、授業参観も開催していただき、本当にありがたく感じました。
クラス毎の授業参観の様子を花井先生が附中日記にて早速紹介して下さっています。
(写真も沢山撮って下さりありがとうございました。)
子ども達の様子を間近で見ることができたり、先生方からのお話を聞く事ができたりして、現状を必死に考えながら生活しているなということを感じました。
コロナ禍で、入学してすぐに行われるオリエンテーション合宿に行けなかったことをバネに、1年生の子どもは、2年生で行われる「自然体験活動」に向けてすでに動き出していました。
実行委員の皆を中心に現在決定していることの発表があり、とても感心しました。
代表の子の最後の挨拶では、「ここにいる実行委員だけでなく、学年全員で考えていきたい」というような言葉もあり、「全員でやり遂げたい」と言う気持ちが凄く伝わってきました。
ここからは、保護者会に参加してあらためて感じた思いです!
がんばれ附中生!!
現在のクラスで過ごせる時間も残り5か月程となりました。
時が経つのは早いものです。
すばらしく成長してきたこの時期に、あらためて入学当時に感じていたワクワク感、緊張感、なりたい自分像を思い出してほしいなと思いました。
なりたい自分と、現在の自分。
自分はこんな性格だから、これ苦手なんだよね。
などと、結構自分で自分を決めつけてしまっている所がありませんか?
(大人になっても私はそうです)
自分はこんなふうだからと思っていても、人間は自分の能力の殆どを使っていない。
発揮できてない(潜在能力!?がある)と聞いたことがあります。
現在の自分が居心地よくて、新しい事に、新しい自分に足を突っ込む事が面倒に感じてしまうようです。
「自分ってものすごい能力を持っているんだ!」とちょっとだけ自負してもよいのかなと思います。
みんながちょっとずつ、「自分ってすごいんだな」と、自分で思えるようになったらいいなと思いました。
オギャーと産まれて約13年、この世に生まれてきたことが奇跡!
一人一人が何にも変えられない大事な存在です。
以前の学年だよりで、保護者の方が「娘の笑い声が私達にとっての薬です」と書いてくださっていました。とても共感できる言葉でした。
私たち保護者も先生方も、みんなのことが本当に大好きで大切な存在なのです。
大切な人だから期待するし、小言も言いたくなる。
でも、いちばんは幸せに過ごしてほしいと強く願っていると思います。
保護者会で育朋館の椅子に座って周りを見渡すと、いつも「あぁこんなにたくさんの親がいる。皆、毎日、がんばっているんだろうなぁ。すごい集団だなぁ」と感じてしまいます(変な人です。)
がんばって、自分はすごいんだって思ってみよう!
「すごいわけないよ」と思ってしまっても、そう思ったのは自分。
自分にもちょっとすごい!と言ってみて!
すごいところ、褒めてほしい子は芝原がいくらでも褒めてあげるので、申し出てほしいくらいです。遠慮なくどうぞ!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
芝原さん、ありがとうございました。
芝原さんのあたたかな視線に本当に励まされますね。
私が最近知った、いちばんのお気に入りの言葉は「発達デコボコ」です。
精神科医の齋藤環さんが使っている言葉です。
発達が遅い早いではなくて、デコボコしているだけなんだよ、という考え方。
人間は、もともとデコボコしていて、全てができる人もいないし、何もできない人もいない、ただ、今の社会で評価されやすい分野と、役に立たない、無駄な能力と思われてしまう分野があるだけなのかなと思います。
平均値の人がたくさんいるよりも、それぞれ違うところがでっぱっている人が集まって協力すれば、すごいことができるんじゃないでしょうか。
足りないところは、得意な人に補ってもらえばいいし、困っている人がいれば助けてあげればいい。
(例えば車のことなど全くわからない私は、JAFさんが華麗にタイヤを付け替える様子がヒーローに見えました。輝いていました。)
みんなが自分の凸を伸ばしていけばよい。
同じものさしでなくてよい。
同じゴールを目指さなくてもいい。
1年生のみんながそれぞれに輝いているところが今度こそは見たいです・・・。
息子の修学旅行のお土産話を遮り、「それより今日母に起こった悲劇を聞いてよ!」とパンク事件の顛末を話して聞かせた中嶋でした。
㉓ その全ては誇れる経験~附中祭2日目「体育大会」~
11月4日(水)
皆様こんにちは。
PTA役員の舩山です。
絶好の天気と、杭ひとつないグラウンドコンディションに恵まれた附中祭(体育大会)。競技や応援の様子はお子様から十分に聞かれていると思います。
今回は、閉会式終了後の「グループ別反省会」の様子を少し。
グループ別反省会では、以下のようなメッセージがありました。
・思いを形にすること
・今年の3年生のやり方を分析すること
・みんなで考えること
・楽しむこと (以上、ごく一部抜粋。)
文字にすると安っぽくなってしまいますが、解散前の最後のグループ会議において、感謝の気持ちとともに、自分の感情と戦いながらも冷静に言葉を選び、経験をもとに2年生、1年生に思いを伝えようとする3年生の姿に心が動かされました。



そして、自分自身はそれと重ね合わせて、自分が3年C組に在籍していた時のことを思い出していました。
仲の良かった友人が、体育大会のグループ長にまさかの立候補。
えっ?なんで?
当時(今も?)冷めていた自分の中に衝撃が走りました。
自分同様に冷めたヤツだと思っていたため、グループ長に立候補するなんて思ってもいませんでした。裏切られたとすら思っていました。
しかし、Cグループは幸いなことに総合優勝。
体育大会が終わったグラウンド上で、その友人がとても大きな存在に見えました。
自分自身、2年時までよりも、目的をもって体育大会に取り組むことができ、達成感を味わうことができました(先輩方申し訳ありません。)。
何より、今でも一番印象に残っているのは、グループ長を務めあげ、体育大会を機に大きく成長して行った友人の姿でした。
注)ちなみにグループ長を務めた友人は、後にプロの社交ダンサーになり、再び衝撃を受けることに。実は単に、自分に見る目がなかっただけなのかもしれません…。
バチバチの競技と華のある応援、製作物。
勝者と敗者がいて、3年生から2年生、1年生へ経験と思いが引き継がれる。
時間の経過とともに、演舞の内容や競技種目は変わったものの、体育大会の光景は今も昔も変わりません。
しかし、今年は、開催自体が危ぶまれる事態となり、異例ずくめの「附中祭」となりました。
だからこそ、今年の「附中祭」に対する考え方、取り組み方は人それぞれであったと思います。
グループの取りまとめ、応援団、製作、競技、運営…。
自分自身の役割を全うする中で考えたこと、気づいたこと、チャレンジできたこと、達成できたこと…。
些細であってもその全てが誇れる経験だと思います。
演舞を間違えてしまったこと、バトンをうまく渡せなかったこと、転んでしまったこと、手を抜いてしまったこと…。心残りもあるかもしれませんが、それも経験。
「附中祭」での経験を糧として、これからも進化し続けてほしいと思います。
全てが終わり、正門に戻ってきたこどもたちが、友人同士で写真を撮ったり、笑いながら話をしたりしていました。
先ほどまでの引き締まった姿とは異なる清々しい姿。
これも附中生。
附中生ってやっぱりいいな。
素直にそう思いました。
最後になりますが、感染症拡大下での「附中祭」開催の決断と準備。
先生方、本当にありがとうございました。
保護者の皆様、グラウンド整備だけではなく、当日までの健康管理、そして当日の気遣いある行動をありがとうございました。
※自分自身は応援マナーを反省しております…。
<追伸>
こどもたちの姿に影響を受け、「忙しい」、「疲れた」を理由に中断していたジョギングを再開することに。
気持ちの高ぶりからか序盤はよいペースだったのですが、調子良く走れたのは始めの1㎞だけ。
すぐに失速し、実質ウォーキング。
こどもたちのようには走れない…。でも楽しめた!
次は呼吸とリズムに気を配ることにしよう!
いつも自分がこどもたちに偉そうに伝えている内容を忘れていた…(笑)
㉒ 健闘を祈る!~「附中おやじの会」によるグランド整備~
10月24日(土)
皆様、こんにちは。PTA副会長の野中です。
バトンをいただきました。
中嶋さんより「附中祭」開催に向けた「附中おやじの会」によるグランド整備の様子をブログに寄稿してね(笑顔)と依頼があり、二つ返事で了解したものの、あれっ?!来週の30日、31日が本番。「附中祭」が終わった後にブログに載せてもらう訳にはいかない・・・。
じゃあ、原稿はすぐ書かないと。
夜な夜なPCと向き合っている状況です。
まずは、グランド整備にご協力頂いた皆様、本当にありがとうございました。
このおやじは手も足もプルプルしています。
今年の文化祭と体育大会は、新たな「伝説」の始まりです。
10月26日(月)から10月31日(土)を「附中WEEK」と称し、文化祭および体育大会を連日開催する「附中祭」となります。
おそらく附中史上初の試みとなるのではないでしょうか。
生徒達は伝統を受け継ぎつつ、「伝説」を創っているわけです。
「附中祭」の各行事に向け制作活動・練習に取り組むハードな一週間になるだろうなと子どもの体調に気をかけつつも、大人になって、同級生で集まった時に、ああだったこうだったと「伝説」を楽しく振り返る時がきっと来るよと見守っているおやじです。
さて、本日は1年生17名、2年生10名、3年生14名のPTAの皆様と戸田校長先生、増岡副校長先生、森教頭先生、校務主任の山田先生の総勢45名でグランド整備を行いました。また、同時に、グランドのポイントどりをしていた体育部の先生もおつかれさまでした。
「附中おやじの会」と言えば、胸に名前シール(ちょっと応急処置的な)を貼り、お父さんがたの交流を促していましたが、今年は違います。
学年ごとに色分けされたゼッケンを安全ピンで堂々と胸に貼り付け、一目で自分の子どもと同級生の親御さんを見つけられるという工夫が。
これも今年からご参加頂いているお母さんがたのアイデアでしょうか。
(実は、PTA会長齋藤さんのアイデアです…。by.森)
大変わかりやすかったです。
ちなみに一昔前では名前シールもなかった様です。
年々バージョンアップ。成長し続ける軍団。すごいぞ、おやじの会。
そして、全員でトンボを使ってグランドをがしがし。
地味だけど、なかなかハードな作業。
昨年までは、グランド整備後の懇親会での「渾身の一杯」に向けて、水分補給を敢えて控えていた不埒なおやじも今年は大人しく水分補給。
普段はあまり気にならない小石も、生徒達が素足で踏みつけたら大変だとせっせと拾います。
トンボを動かしているとガチンと金属音。
鉄の頭が見えます。
何だろうと掘り続けると、昔の体育大会で使用された鉄杭やペグが埋もれています。
結構な頻度でぶち当たります。手こずりながらも皆で協力して鉄杭がざっくざく。
「出る杭は打たれる」でも、今日の杭は抜かれてしまったなぁ。
子ども達への土産話としては、もっと前向きな話がよいな。
確か「しっかりと伸びた竹はどんな風にも負けない」そんな諺が海外にあったんじゃないかと頭を巡らせての作業。
その場でググってみたものの、見当たりませんでした。
ご存知の方が見えましたら教えてくださいませ。
小石、杭、水たまり、へこみ、一つ一つを退治するたびに、生徒達の笑顔が増える。
そんな気持ちで一時間強の作業を終えました。
最後は先生方からのご厚意で冷えたアイスを皆でほおばり、スッキリ。
約30年前、かく云うおやじも附中生。
当時の体育大会・応援団のイメージや下馬評は、
A:「華麗なる蝶の舞」、
B:「手堅くも格好良い」、
C:絶対的な「陸の王者」(Aとの早慶戦)、
D:「何をやってもダメ、ダメ、ドベ・・・」。
しかし、体育大会の実際の結果は…、
Dの総合優勝、応援・制作部門優勝でした。
今年は何が起きるのか、何を起こすのか。
健闘を祈る!!
最後に、グランド整備にご協力頂いた戸田校長先生。
本格的ながらも最近のアウトドアブームに乗ったファッショナブルないで立ち。
それもそのはず、南極観測隊にご参加された時の装備だったとのこと。
本格的ではなく「本物」でした。
11月以降開催予定の「教育講演会」は戸田校長先生より南極観測隊のお話をたまわる予定です。そちらも今から楽しみです。
㉑ いつも自分を開いていたい~懇親ウォーキング結果発表~
10月20日(火)
皆さん、こんにちは。中嶋です。
寒いのが苦手です。
暑いですねと言っていたのがついこの前のことのよう。
先週の「懇親ウォーキング」は、暑くもなく、寒くもなく、まさに奇跡のタイミングで開催できたのだなあと思います。
月末に控えている「附中祭」もきっといろんな奇跡が起こることでしょう。楽しみです
さて・・・お待たせしました。
今日は、いよいよ、結果発表です。ドキドキ。
写真・俳句については、選考を先生方にお手伝いいただきました。
(本当は参加していただきたかった・・・)
すばらしい秋の空と、皆さんの力作をみていたら、詩心が湧いてきたので私も一句詠んでみました。お粗末。
それは置いといて。
歩くことで、いままで気づかなかったものがみえてくる、そんな経験ができたらいいなと思ったのもこの企画を立てた理由のひとつです。
世界は前と変わらないのに、見る目が変われば、自分が変われば、新しい世界になる。
いつも自分を開いていたいなあと思うのです。
それでは坂田さん、お願いします!
☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆
こんにちは。体育部の坂田です。
ウォーキングの日の天気が羨ましく思うほど、ここ数日は寒いですね。
参加された皆さんは気になって仕方がないと思われる、写真と俳句の結果を発表したいと思います。
が、その前にゴール後のシークレット問題を紹介しましょう。
問題:コマ図②のウナギのマークのお店には大きなオブジェがありますが、何だったでしょう?
という問題でした。
即答するグループ、悩んでしまったグループ。
いろいろありましたが、車で通っても分かりますので、確認してみて下さいね。
東岡崎駅周辺を通るお子さんには簡単ですね。
それから、設定時間も発表しましょう。
今年附中は73周年ですよね。
ということで、1時間73分=2時間13分にしていました。
ピタリのグループはなかったですが、1分違いのチームがありました(拍手)。
近い順に7点から1点まで点数が加算され、優勝チームが決まりました!
優勝は……、
『チーム岡崎城』 でした。
そして、先生方に審査して頂いていた写真賞。
「森先生賞」と「馬場先生賞」ということで、2作品を選出していただきました。
森先生賞は……、『チーム桜』。
作品名は、「チューチュートレイン 家康」。
気になる作品は、こちら↓
馬場先生賞は……、『チーム家康』。
作品名は、「附中の家康とじゃじゃ馬娘」。
気になる作品は、こちら↓
そして、俳句賞は……、『チーム乙川』 でした。
それぞれのチームの方々、おめでとうございます(祝)
景品が用意してあります。
お子様を通じてお手元に届くようにいたしますので、楽しみにお待ちいただければと思います。
それでは、「俳句」の全作品を紹介したいと思います。
俳句1
俳句2
参加された皆さん、本当にありがとうございました。
⑳ 一緒にその空間を共有できることのありがたさ~懇親ウォーキング 10.15~
10月16日(金)
こんにちは。体育部長の坂田です。
昨日、秋晴れのもと、『懇親ウォーキング』を開催することができました。初めての企画で、不安もありましたが、想像以上の参加人数に後押しされて当日を迎えることができました。
お天気も良く、歩くには絶好の日になりました。
(きっと晴れ男か晴れ女がいらっしゃったのでしょう)
残念ながら当日欠席された方もいらっしゃいましたが、校長先生と副校長先生が教員代表として参加してくださいました。
先生のグループはくじ引きで・・・。
先生と一緒のグループの方は、興味深いお話が聞けたのではないでしょうか?

(↑出発前に、記念写真をパチリ!)
途中、審査対象ミッションの写真が続々と送られて来て、楽しげに歩いている事が伺えました。
下見の時は、だいたい2時間弱で戻ってこれたのでそれくらいの時間を予想していたのですが‥。
ミッションに苦戦したのか、はたまたグループトークが盛り上がったのか、予想よりもちょっとゆっくりめな時間で続々と皆さんが帰ってくるのをお迎えしました。
楽しそうにお話しながら門を入ってくる皆さん。
でも、すぐには帰しません!シークレット問題に答えていただき、やっとゴールです。
お疲れ様でした。皆さん、爽やかなお顔をされていましたよ。
順次解散してもらったのですが、名残惜しそうにグループの方々とお話ししている姿も見られました。皆さんが直接お会いしての会話を待っていたんだなと改めて感じました。
そう言った事も含めて『懇親』という役割も果たせたのではないかと思っております。
帰り際、「楽しかったです。ありがとうございました」って言ってくださる方もいて体育部一同にも、充実感があふれました。
現在、写真と俳句は先生方に審査していただいています。
発表までしばらくお待ちくださいませ。
(結果発表時に皆さんの力作を一挙掲載させていただきます)
また、残念ながら欠席された方や、これを読んで楽しそう!と思った方のために、問題文と中嶋副会長渾身の力作!コマ図を掲載いたします。
(コマ図、正直言ってめちゃめちゃ大変でした…が、途中から楽しくなってきてしまい、むきになって出来ばえを追求しています。特に注目して欲しいのは赤い橋の質感と、石垣の石垣っぽさです。何かの他の機会に使いたい方いらっしゃいましたらご一報ください。by中嶋)。
ウォーキング問題
コマ図
是非、時間のある時に解いてみてください。
答えは・・・。実際に歩いて確かめてみてくださいね!
私達の思いを汲み取り、調べる事をせず、全力で問題を解いてくださったこと、感謝いたします。
素敵なウォーキングウェアに着替えてご参加して下さった校長先生と副校長先生、私達の無茶振りに答えてくださった佐藤先生、審査に協力いただいた先生方、そして参加してくださった皆さんに、この場をお借りしてお礼申し上げます。
ありがとうございました。
⑲ 新しい価値観で動き出す~オンライン文化セミナー~
10月12日(月)
こんにちは。文化部長の北村です。
先日、無事に、「オンライン文化セミナー」を終えました。
詳細は、附中日記『かける』(10月11日号)をご覧下さい!
…あ、これで終わってしまうと、中嶋副会長から優しく突っ込まれるのが想像できますので、違う角度から当日の模様をお伝えします。
(当日、唯一心配だったのが学校のインターネット環境。実際二台目のパソコンがなかなか接続できず、開始直前まで村上先生が走り回って大活躍してくださり、なんとかなりました。最終的に村上先生が何らかの特殊能力を使って回線を安定させてくれたんだ、と信じています。ありがとうございました。by中嶋)
↓村上先生のハンドパワー↓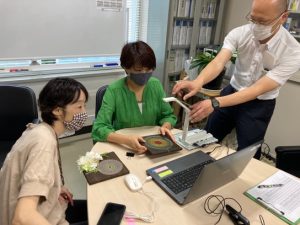
では、当日の様子です。
台風接近のニュースが流れる雨模様の中、10月9日(金)、附属岡崎中学校の会議室にて、初のオンラインPTA文化セミナーを発信しました。
悪天候でも参加者の皆さまには外出せずにセミナーを受けていただけるということで、早速、リモートの長所を感じるところから始まりました。
午前の部、開始。
42名の参加者の方々へ、PTA齋藤会長からご挨拶をいただきました。
「今年度、保護者の皆様へ顔を出してのご挨拶は初めてです。」とのお言葉に、この7か月間の世の中の移り変わりを思い出しました。
当初の予定では学校に集まってもらい、直接の講習を計画していました。
しかし、コロナ禍。開催自体を躊躇しましたが、講師の稲葉法恵先生にオンラインでの講習をご相談したときのこと-。
「やるなら楽しくやりましょう!一緒に成功させましょう!」
と前向きに言っていただいたお陰で当日を迎えることができました。
稲葉先生、本当にありがとうございました。
Zoomに慣れておられた山田あやこ先生とのコンビネーションはすばらしく、参加者の方と会話しながら、徐々に画面の向こう側では色とりどりの素敵な作品が完成していきました。
午後の部。
17名の参加。ランチ後の「ゆったりまったり」な雰囲気で始まりました。
午前・午後ともに参加してくださった方、画面の背景をかわいらしくアレンジして参加の方、職場から休憩時間に参加してくださった方など、新しいチャレンジを一緒に楽しんでもらえた様子がこちらにも伝わり、お陰で私たちもパワーをいただけました。
ご参加いただいた多くの皆さま、この場を借りて感謝申し上げます。
そして感じたこと。
「今はないものについて 考える時ではない。今あるもので、なにができるかを考える時だ。」 小説『老人と海』(ヘミングウェイ)
誰一人として「オンラインセミナー、無理です」の言葉を発することなく、どうすればできるのかを一緒に考えて下さった方々。
やっぱり直接会ってコミュニケーションをとりたかったと改めて感じた方。
どれも正しいです。
これからの未来は、新しい価値観で動き出しています。
☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆
さて突然ですが、ツッコミ係の中嶋です。
北村さん、お疲れさまでした。
…昨年度文化部長だった私は、11月の反省会で、
『「今まで通り何も変えずにそのままやろう」と、「面倒だから全部やめてしまおう」は、何も考えていないという点では同じこと』だと申し上げました。
全国的にみてもPTA組織自体が再考の時期に来ており、本校のPTAも数年かけて縮小化、簡素化を進めている最中でしたが、その中でも安易に不要論に走るのではなく、何が必要なのか、なぜ必要なのかをみんなで考えて欲しい、という思いを込めたつもりの発言でした。
そのときは、まさかこのような事態になるとは思ってもいなかったのですが…。
このコロナ禍の中で、「何もしない」選択をした学校も多かったのではないでしょうか。
そして、そのままたくさんのことが「なくてもよいもの」化してしまったかもしれません。
そのような中で、
今後に「つなぐ」ために勇気ある選択をされた北村部長、
私たちの背中を押してくださり、開催までお手伝いいただいた村上先生はじめ職員の皆さま、
ご自身も初めての試みにチャレンジしてくださった講師の稲葉先生、
そしてセミナーに参加してくださった本当にたくさんの保護者の皆さま、
この場をお借りして、心より御礼申し上げます。本当にありがとうございました。
「あってもなくてもよいもの」は、「なくてもよい」けれど「あってもよい」ものであり、きっと最初は「あったらよい」から始まったものです。
参加してくださった皆さまが、「楽しかった」「参加してよかった」と思ってくださったなら、「あったらよい」のスタートに戻れたのではないか、そう感じています。
さて木曜日はウォーキング!
台風さえもUターンさせる坂田部長率いる体育部のイベント、楽しみですね!
⑱ 「つなぐ」ことの大切さ~オンライン文化セミナーに向けて~
9月29日(火)
こんにちは。文化部長の北村です。
3回目のバトンが回って来ました。
リレーといえば、谷川俊太郎さんの詩。
『朝のリレー』を思い出します。
カムチャッカの若者が
きりんの夢をみているとき
メキシコの娘は
朝もやの中でバスを待っている
ニューヨークの少女が
ほほえみながら寝返りをうつとき
ローマの少年は
柱頭を染める朝陽にウインクする
この地球では
いつもどこかで朝がはじまっている
ぼくらは朝をリレーするのだ。
経度から経度へと
そうしていわば交替で地球を守る
眠る前のひととき耳をすますと
どこか遠くで目覚時計のベルが鳴っている
それはあなたの送った朝を
誰かがしっかりと受けとめた証拠なのだ
(『朝のリレー』 著/谷川俊太郎)
朝をリレーする・・・素敵な響きです。
日常が非日常となった今、諦めるのではなく方法を考えて「つなぐ」ことの大切さが身に染みます。(今回、詩で行数を稼いでいるような、いないような…)
「つなぐ」文化セミナー。
10月9日開催に向けて、先日、オンラインテストを実施しました。
講師の稲葉法恵先生にもお越しいただき、当日を想定しての打ち合わせ。
テストをしながらキットを組んで、今週、お子様を通じて参加者の皆様にお配りしております。
私たちの予想を大きく超える約60名の参加者の方々と一緒に、新しいチャレンジが始まろうとしています。
ご参加の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
※セミナーの前に、お使いになる端末の音量設定をご確認ください。(音声が聞こえるようにお願いいたします。)
☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆
こんにちは、中嶋です。
今日は文化部長の北村さんが、ご本人にぴったりの爽やかな詩とともに文化セミナーの準備の様子を知らせてくださいました。
夏休み前に、全くの白紙状態から「やっちゃう?」と始まったオンライン文化セミナー。
「え、やるの?」と思った方もたくさんいることでしょう。
やっても、やらなくてもよいものだったら、やってみたい。と、私は思いました。
なぜなら、やってもやらなくてもよいものや、あってもなくてもよいものでこの世の中は溢れていて、そういうものがちょっとずつ世界を楽しく、豊かにしているということを、思い知ったからです。
・・・とはいえ、現実にいろいろと準備を整え、先生と打ち合わせをし、当日まで気が抜けずにいらっしゃるのは部長の北村さんです。
細かなことまで気を配り、綿密な準備を整えていただき、本当にありがとうございます。きっと、楽しい会になると思います。
参加者の皆さんと一緒に、楽しみましょう。
⑰ 町並みの空気や彩りを感じながら~「懇親ウォーキング」下見~
9月25日(金)
皆さん、こんにちは。中嶋です。
今日は心地よい疲れを感じながらこれを書いています。
スマホの歩数計に刻まれた「12,648歩」の文字を見ながら、満足感に浸っています。
いつもの朝のウォーキング(ちゃんとやってますよ)は、せいぜい4,000〜5,000歩なので、この数字は普段徒歩で移動することの少ないわたしにとってはなかなかの数字。
そして、曇りだと思い込み、あまりにも無防備に出かけてしまったので非常に日焼けしました。
私は普段から無頓着に肌を痛めつけて娘に怒られているのですが、皆さんは十分お気をつけてくださいね。
なぜそんなに歩いたかというと、今日はPTA体育部で企画している「懇親ウォーキング」の下見に行ってきたからなのです。
(ちなみに今朝のウォーキングはサボりました)
「懇親ウォーキング」当日はウォークラリー形式を想定しています。
数人でチームになり、ルート中に設けられたいくつかのチェックポイントでミッションを遂行しつつ、ゴールを目指していただきます。
体育部有志一同で考えた、チームワークとちょっとした遊び心が必要なミッションをたくさん用意しています。
参加者の皆さんには、きっと楽しい時間を過ごしていただけると思いますよ。
わたしも、とっても楽しみです。
では、下見ウォーキングの様子を坂田さんに報告していただきますね。
☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆
こんにちは。体育部長の坂田です。
今日、学校に着いたとき、体育大会活動が行われていました。
運動場では応援団の練習をそれぞれのクラスが行っていました。
「がんばれー」と心の中で叫んで通り過ぎました。
学校に行った理由は、懇親ウォーキングの下見をするためでした。
台風の接近で雨予報だったので心配していましたが、お日様も出て汗ばむくらいの陽気になって気持ちよかったです。
きっと当日はもっと気持ちいいだろうなぁと話しながら出発しました。
ミッションは当日まで秘密にするので、詳しくは書けませんが、いつもは車で通り過ぎて気づかなかったことも多く、たまには歩くのも悪くないなぁと思いました。
ミッション作成のため、気になったものを写真に撮ったりしながら、早くもなく遅くもないスピードで歩いて、2時間くらいかかりました。
およそ6km、程よい距離と運動量ではないかと思います。
(道中、階段も結構ありました)
そういえば、岡崎城を歩いている時、結婚式の前撮りをしている新郎新婦さんに遭遇しました。
花嫁さん、お綺麗でしたし、私達も幸せな気持ちになりました。
岡崎葵武将隊の方とも遭遇したりしたので、そんな瞬間も楽しむ要素になるかなぁと思いました。
「懇親ウォーキング」の申込締め切りは本日25日までとなっております。
私の拙い文章で少しでも参加してみようかなと思った方がいらしたら、お子様のクラスと参加される方のお名前を書いて今月中に担任の先生にお渡しください。
よろしくお願いいたします。
☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆
坂田さん、ありがとうございます。
岡崎に住んでいる私でも、今まで気づかなかった新しい発見があり、楽しい一日でした。そうそう、中嶋からの○○オタク特別ミッションもあるとかないとか?
ぜひ参加して確かめてくださいね。
・・・ちょうど、読んでいた本から「輸送」と「徒歩旅行」について書いた部分がありました。
輸送とは、「出発地点と到着地点を直線で連結し、荷物(乗客)に変化を加えないよう横断させる」行為。
たとえば、車や電車の移動にあたります。
一方、徒歩旅行は、「街並みの空気や彩りを感じながら、そこを通り抜け、その先に何があるのだろうという、ちょっとした冒険の気分に胸を高鳴らせながら、私を取り巻く街並みとともにラインを描く」行為。
皆さん、ともにラインを描き、踏み跡を刻みませんか?
(引用『急に具合が悪くなる』著/宮野真生子・磯野真穂 晶文社刊)
⑯ 「前例がない」を楽しむ。
9月18日(金)
皆さん、こんにちは。中嶋です。
私たちは、毎日いろいろなものを見たり聞いたりして、いろいろなことを感じたり、考えたりしています。そして、それを誰かに伝えたいと思ったら、その気持ちに、ぴったりくる言葉を考えます。自分の気持ちにぴったりくる言葉がうまく見つかって、誰かに、うまく気持ちを伝えられたら、嬉しいですよね。
私は、この作業がとても好きなんです。
自分の気持ちに、ぴったりくる言葉を、一生懸命探すことが。
それは単に語彙力を高めるということではなくて(それも大事ですが)、今感じているこの世界、この気持ちをできるだけ豊かなままで捉えておくこと、貧しい言葉の型に嵌めないように気をつけるということかなと思います。
本を読むことも、書いてあることをぐるぐると考えることも、だから好きなのだろうと思っています。言葉って大事ですよね。
世界にはたくさんの言語があり、みんなそれぞれ別の言葉を使って気持ちを伝え合っている。でも、生きている世界は同じです。もしも、相手の言葉がわかれば、きっと共感することがたくさんあるだろう、そんなふうに思い、たくさんの言語を操る人に憧れます。
皆さんの中にもいらっしゃるでしょうね!素敵です。
何の話をしてるんだ??と思いましたね。
これがどう、PTAに関係ある話になるんだ??と。
・・・一学期に、Pネット講座の登録依頼のご案内をしました。
(残念ながら今年はいろいろな予定変更があり、まだ開催できてはいません)
その際、Pネットの一講座として、「手話教室をやってほしい」と、ある保護者の方にご依頼しました。
私自身は全くの初心者で、挨拶程度の手話しか話せません。
ただ、興味だけは人一倍ある。
そして、ぜひ生徒の皆さんにも、ろう者の豊かな世界にふれてもらいたい。
手話をひとつの言葉だと知り、世界を広げてほしい。
はっきり言って勢いだけのかなり唐突で迷惑なお願いをしてしまいました。
それでも、そのかたは一緒にやってくださると引き受けてくださりました。
(一緒にというか、私は教えてもらうだけの人ですが)
とはいえ、今のところ、Pネット開催の見通しは立っていないため、どうしたものかと思い、困ったときの森先生にご相談させていただきました。これが今週の話。
そして、とりあえず、何か「Pネット」に変わるものを・・・ということで、先生に多大なるご協力をいただき、いきなりの「絵本手話読み聞かせ動画撮影」に挑んでみました(私は本を持っているだけの係)。
今頃、先生が素敵な編集を施してくださっていることと思います。
(現時点であまりはかどってはいませんが…。すみません by.森)
そして、完成したら、第二弾、第三弾も懲りずに準備しちゃう予定。
生徒の皆さんにいつ、どんな形で届けられるかわかりませんが、きっといろいろなことが伝わると信じています。
(限られた授業・学習の時間や行事の活動時間を削ることのないよう配慮いたします)
また、この件に関わってご意見、ご興味ある保護者のかた、一緒に活動してみたいというかたがいらっしゃいましたら、ぜひお声がけいただければと思います(「手話」に限った話ではなくても結構です)。
二学期に入り、P T A活動も活発になってきています。
オンライン文化セミナーまではあと1か月を切り、体育部の懇親ウォーキングもこれからどんどん準備を進めていきます。
コーラスクラブもオンラインをうまく使って活動を始めました(これは画期的です。一見の価値あり)。
「前例がない」を都合よく楽しんでないかって?
これが「附中精神」ですよね!
⑮ PTA体育部の新しい取り組み!
9月8日(火)
皆さん、こんにちは。中嶋です。
突然ですが、最近、早朝ウォーキングを再開しました。
休業中は、子どもたちの運動不足を心配してみんなで朝散歩をしていたのですが、学校が始まり、子どもたちが45分くらいかけて歩いて学校に行くようになると、朝散歩習慣は暑さと共に自然消滅。
そしてふと気づいたのです。いま運動が不足しているのは家族内で私だけでは…?
そんなわけで、日の出前(でももう明るいです)に起き出し、近所の川沿いを三キロほど歩いています(実は数年前まで早朝ランニングをしていたのですが、試しに走ってみたら3分くらいで吐きそうになったので断念)。
すると、歩いていなければ目に入らなかったであろうもの、気づかなかったであろうことにたくさん出会います。
サギが魚を飲み込む瞬間。
飛び立つときの、バッサバッサという翼の音。
飛び立って初めて気づくカワセミの鮮やかさ。
日によって増えたり減ったりするカメ。
エアラジオ体操をするおじさん…。
それに、歩くペースはあれこれ考え事するのにも最適。
最近読んだ本の内容を整理したり、献立を考えたり。
ああ、歩くっていい!
そんなわけで(強引すぎる前振り)、P T A体育部有志の皆さんが、素敵なイベントを考えてくださいました。
ちょっとした運動不足解消。参加者同士の交流。岡崎の町探検。
短い時間で、いろいろなことができそうです。
皆さんに楽しんでいただけるよう、これから一層内容を詰めていく予定ですが、ちょっとだけ、坂田さんからお知らせしていただきます。
一緒に面白がっていただける方、大募集です!では、坂田さん、どうぞ!
☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆
こんにちは。体育部の坂田です。
PTA体育部よりお知らせです。
前回のブログでチラッと告知しましたが、スポーツ懇親会に替わる行事として、『懇親ウォーキング』を企画いたしました!
簡単にいうと、「附中を発着点とし、各ポイント地点での課題をクリアしながら歩いていただこうというもの」です。
いくつかのグループに分けて行い、課題も簡単にクリアできるものにする予定です(課題は当日までのお楽しみです)。
なるべくクラス単位、学年単位のグループにするので、楽しくお話ししながら、歩いていただきたいと思います。
近日中に案内を配付していただく予定ですが、日程は下記のとおりです。
<日時> 10月15日(木)
9時より受付(育朋館ピロティ)
9時半スタート
12時半までにゴール
平日の午前中ではありますが、多くのかたのご参加をお待ちしております。
はじめての試みで不安もありますが、皆さんに楽しんでいただけるよう準備を重ねてまいります。
☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆☆★☆★☆
再び、中嶋です。
子どもたちも、現在、「新しい体育大会・文化祭」に向けて、準備をはじめているようです。
私たちも負けないように、躓いたり転んだりしても歩みを止めず、考えるのをやめず、進んでいきたいと思います。
ご協力、よろしくお願いいたします。
あ、コーラスクラブもいよいよ今週から活動を始めるようですよ。楽しみですね。
⑭ 夢が見つかるきっかけ
8月28日(金)
皆さん、こんにちは。中嶋です。
いつもより少し短い夏休み、どのように過ごされたでしょうか。
梅雨明けしてからは酷暑が続き、一体地球はどうなってしまうんだろう、なんて思っていましたが、夏休み終了とともに、朝夕には秋の気配を感じるくらい爽やかな空気になりました。(昼間はまだまだとんでもなく暑いですが)
私たちがあたふたしていようと、ぼんやりしていようと季節は変わるんだな、ツクツクボウシはすごいな、とそんなことを思っています。
さて、以前ここで宣言したように、私はおやすみの間、エアコンの効いた涼しい部屋でたくさん本を読みました。いろいろ読んだ中からひとつ、紹介したいと思います。
タイトルはズバリ、『南極で心臓の音は聞こえるか』(著/山田恭平、出版/光文社新書)という本です。だって、涼しそうでしょ。南極。
これは、気象の研究をするために第59次の南極観測隊に加わった若き研究者の記録です。と言っても、専門的な気象のことが書いてあるわけではなくて、南極観測隊が何をするのか、南極の生活、特に南極で越冬するというのはどんなことなのか、とっても面白く解説してくれています。
雪に埋もれた雪上車や観測拠点をひたすら掘り出したり。
ブリザードに封じ込められて雪上車生活を送ったり。
コンクリートを練って、観測棟を建てるのも自分たちでやる!
それから、飽きるほどのペンギン・・・
(読んでいるだけなら)すごく楽しそう!
そんな楽しい(けれど過酷な)研究生活を山田さんはなぜ目ざしたのでしょうか。
それは、山田さんが高校生のとき、高校O Bで南極観測隊になった人の講演を聞いたのがきっかけでした。
「南極ではあまりに静かすぎて己の心臓の音が、血管を血液が流れる音が聞こえる」
そう聞いた山田さんは、「なんとしてもそれを自分で確かめたい!南極に行きたい!」と思うようになったんだそうです。
そして、その講演の中で、
「南極に行くには金持ちになるか、観測隊に入るしかない」
「観測隊に入るには、研究者になるのが一番手っ取り早い」
ということも知り、それなら、と研究者になったんだそうです。(前澤さんとか堀江さんは、自分の夢を叶えるのに「金持ちになる」を選んだんだなと思いました)
夢が見つかるきっかけは、どこにあるかわからないものですね。
ところで皆さん、「南極」といえば、何か思い出しませんか。
そう、我らが戸田茂校長先生。(先生は59次の観測隊にも参加されていますよね。ひょっとして上記の山田さんもご存知かも)
戸田先生は、なんと4回も南極観測隊に選ばれている、もはや南極のエキスパート、南極人と言っても過言ではありません。
そんな先生は、きっと面白い話をたくさんご存知に違いない。どうしても聞いてみたい。そう考えた人はたくさんいるはずです。
PTA役員一同も、ぜひ先生のお話を伺ってみたい、子どもたちにも南極のお話、研究のお話をぜひ聞かせてあげたいと考えました。未来の、南極観測隊員が生まれるかもしれないのだから・・・。
PTAでは、例年、「教育講演会」というものを企画・実施しています。
講師の方をお招きして、生徒全員と希望する保護者の皆さんの前でお話をしていただいています。
ところが、今年度は、コロナ禍のため、遠方から講師の方をお招きすること、大勢でお話を聞くことが難しくなっています。
ですが、身近にこのように魅力的な講師の先生がいらっしゃるのだから、お願いしない手はない、と私たちは考えました。
そして、戸田先生には講演のご依頼を申し上げ、ご快諾いただいております。
まだ日程、どのような形態で行うかなど、詳しいことは決定しておりませんが、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。
ところで前述の山田さんは、自分の心臓の音を聞けたのでしょうか?
それは、ぜひ、皆さんが南極観測隊(あるいは大金持ち)になって確かめてくださいね。
余談ですが、実は私が中学生のときの校長先生も南極観測隊のかたでした。
そして、その年体育大会のA組応援歌は、校長先生にアピールすべく観測船?の歌の替え歌にして、見事、優勝旗を手に入れたのでした。その手は何度も使えないというので、その年一年きりの応援歌でしたが。
優勝のためには、伝統の応援歌は思い切って捨てる、目的を達成したらもう次を目ざす、そんな先輩の姿がとてつもなくかっこよく、輝いて見えたものでした。
予定していたとおりの体育大会ではなくても、今年は、何か新しい、スペシャルなものが生まれそうな気がします。楽しみにしています。
⑬ 1学期の終わりに思うこと
8月7日(金)
こんにちは。中嶋です。
例外だらけの一学期が終わります。
長い梅雨は終わり、熱い熱い夏がやってきたものの、世の中の状況は残念ながら未だに好転はせず、愛知県はまた緊急事態に逆戻りしてしまいました。
正直、ちょっと、へこんじゃいますね。
しかし、「人生は続く」です。
体育大会についても、当初の予定どおりには行えないかもしれない、というアナウンスがありました。
生徒の皆さんは、春からたくさんのイベントが中止になり、きっと残念で悔しかったでしょう。それなのに誰のせいにもせず、制限のある毎日のなかでどうやって活動をしてゆくのか、自分たちで考え、工夫して乗り切ってきましたね。素晴らしかったです。
体育大会についても、競技や応援の仕方など、どうしたら安全に行えるのか、何度も真剣に話し合ってきたのですね。
なんとかして、その思いを叶えてあげたい。
保護者の皆さんも、先生方も、誰もがそう願っています。
あなたたちの思いを簡単に叶えてあげる力がなくて、魔法のような秘策もなくて、おとなとして本当に情けなく思います。ごめんなさい。
全て自分たちで責任をもって考え、話し合って決めてきたのに、肝心な最後の決定権はないというのが、なんと残酷なことだろうと思います。
…ただ、どうにもならないことってあるんです。
自分たちの努力や、工夫や知恵が及ばないことが、残念だけど世の中にはあります。
こんなふうにとびきりの、世界中がいっぺんに手も足も出ない、みたいな事態はそうそうないとは思いますが、そんなときは、どうしたらいいんでしょうか。
私の考える大事なことは、ふたつです。
ひとつめは「誰かのせいにしないこと」です。
誰かのせいにするのは簡単で、なんとなくそれですっきりするような気がしますが、実は何にも解決しないのです。
もちろん自分のせいでもないです。
附中の皆さんは、それが最初から当たり前のようにできてますよね。
本当に素敵だなと思います。世界中に胸をはってよいと思います。
ふたつめは「忘れないこと」です。
『コロナの時代の僕ら』という本にも書いてありましたね。
世の中の動きだけでなく、自分の悔しい気持ち、悲しい気持ち、みんなが、自分がどう感じて、どう振る舞ったか、覚えておくこと。
そして、もしも、似たようなことがまた起きたときに、前より少し、上手く対処できるように、考え続けること。
まあ、そう言っている私は何でもすぐに忘れてしまうので、自分も心がけようと思っています。
今年の夏休みは、いつもより少し短いですが、きっとうちの中で考える時間がたくさんあるでしょう。
先生も、私たち保護者も、一生懸命考えます。
(そして私は本をたくさん読もうと思います!ほんまつり、いつでも来い!という感じ)
密は少し我慢して、また休み明けに元気にお会いできるのを楽しみにしています。
PTA文化セミナー、コーラスクラブ、附中おやじの会の申し込みの締め切りは、休み明けの24日となっております。附中おやじの会の文書については、本日配付となります。
(全て感染予防の対策をとった上での開催となります)
わたしたちも試行錯誤しながら進みます。
皆さんのご参加を心よりお待ちしております。
⑫ 『project shibahara』とは何か
8月4日(火)
こんにちは。芝原です。
先週の初Zoomクラス懇談会では、色々ありましたが皆様のおかげで楽しい時間を過ごす事が出来ました。本当にありがとうございました。次回の開催も、どうぞ楽しみにお待ち下さい!
前回、中嶋さんよりご紹介いただきました『project shibahara』(素敵な名前を付けて頂き恐縮です。)について少しお話させていただきます。
現在、学校では、コロナ禍で給食の時間に楽しくおしゃべりをしながらではなく、前を向いて静かに音楽を聞いたり動画をみたりして過ごしている、と言うことを少し前に知りました。
それならば、その時間を少し分けてもらえたなら、保護者による読み聞かせや、ジャンルを問わないお話、楽器の演奏、漫才!?などなど・・・、子どもたちに向けて、保護者の届けたい想いを少しでも知ってもらえる機会ができるのでは!と考えたことがきっかけです。
私は、娘達が小学生の頃は「図書クラブ」に所属しており、’’小学校低学年では読み聞かせが身近な存在であったのに、学年が上がるにつれ、まして中学生にもなるとその機会が減っていくのは寂しい”と常々思っておりました。
回数は少なくても細々と読み聞かせができないものかと・・・。
そんな親のエゴを叶えてしまおうと、図々しくも動画を撮りました。
(森先生が快く動画を受け取ってくださいました!ありがとうございました!)
また、読み聞かせの講習会の中で、「便利な世の中になりSNSで簡単に話ができる時代ですが、子どもたちにはとにかくたくさんの肉声を聞かせてあげてください。肉声には温もりがあり抱きしめる効果もあります。」というお話を何度も聴いてきました。
(反抗期の息子を肉声でハグすることができる!?)
そんな魅力的な読み聞かせが私は好きなのです。
(個人的なことですみません。でも大好きなのです。)
近年、YouTubeやTikTokにはさまざまな動画があり、子どもたちは自分の好みの動画を選んで見ることができます。親が見てほしいなと思う動画とは全く違うものかも知れません。
今は、直接子どもたちとふれ合い、反応を見たり、感じたりすることがまだできない状況ですが、想いを動画にして届ける!そんな素敵なボランティア活動に参加しませんか!
保護者の皆様で、ご興味のある方は是非、お声がけ下さい。
(こちらからお声かけさせて頂くかもしれません!)
最後に、附中生の皆さんへ(手紙っぽく・・・)。
親が準備する動画は、好みに合わない事もあるかも知れないけれど、きっと想いが伝わって来るでしょう。動画再生数を狙っている訳でなく、たださまざまなことを知るきっかけになったらいいなと思う親の愛情だと感じてほしいです。
行動も自粛が続いていますが、想像は無限です。
今すぐにでも世界旅行もできてしまいます。
小さな携帯画面に目を向ける時間を、少し減らしてデジタルデトックスの時間を増やしてみませんか?
「ちょっと今、自分でカッコイイ事言ったと思ってるでしょ、お母さん!」とよく子ども達に言われます。(顔に出てるのか!?)文面だけですので、皆さんのご想像にお任せします。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
突然ですが中嶋です。
どうですか皆さん。芝原さんの熱い思いが伝わってきましたね。
私は、「本を読む」というのは、基本的に自分ひとりのものだと思っています。
「自分と作者との対話」と言ってもいいかも知れません。
「読み聞かせ」は、そのひとりの時間を共有することができる、とても素敵な試みだと思います。
同じ物語を聞いている人、読んでいる人、それぞれの心の中で、それぞれの思いが生まれますよね。
自分では、手に取ることのなかった物語に出会うチャンスかも知れません。
本も人も、出会いだよなあ、と思う今日この頃なのです。
芝原さんの熱い思いから始まったこのプロジェクトですが、これこそ今だからこそできること、今しかできないこと、だなあと思います。
皆さんも、ぜひこの波に乗ってみませんか?
絵本の読み聞かせだけでなく、皆さんの得意技や才能やアイディアを生かして、いろいろ面白いこと、やってみませんか?
まずは、やってみる、精神で。
⑪ 1年生オンライン懇談会を開催して
7月31日(金)
こんにちは。中嶋です。
「附中日記」の「手紙・テスト対策シリーズ」も怒涛の最終回を迎え、定期テストも終わりましたが、附中生の皆さん、手応えはどうでしたか?
あ、まずおすすめの漫画を紹介するんですよね。(?)
わたしはなぜか漫画を読むのがあまり得意ではなく、気になるものがあってもなかなか手が出ず、先生方が挙げてくださった数々の名作も、ほとんど読まずに生きてきてしまいました(世代も違う説あり)。
ですので、今回紹介するのもいくらかマイナーかもしれません。
わたしのお勧めは、高野文子さんの「ドミトリーともきんす」です。
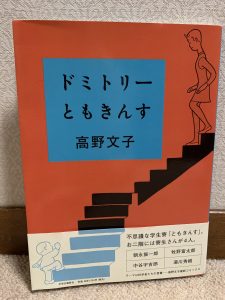
ともきんす、という架空の学生寮に、日本を代表する科学者、朝永振一郎、牧野富太郎、中谷宇吉郎、湯川秀樹が住んでいたとしたら・・・という設定で、科学者たちの「言葉」を少しずつ紹介する、というものです。
(ちなみに「ともきんす」というおかしな名前も、ジョージ・ガモフという物理学者の「トムキンスの冒険」という本のタイトルから取っています)
前にも少しお話ししたように、わたしは理系科目は苦手ではありますが、科学者の本を読むのは大好きです(この本に出てくる自然科学者たちも素晴らしい随筆などをたくさん残しており、中には子ども向けのものもあっておすすめです)。
この中に紹介されている湯川秀樹の詩にもあるように、「最先端の物理や科学と、詩や文学は、全く異なるように見えて、出発点は同じではないか」と思うのです。
(個人的には、目指すものも近いのではないか・・・と思ったりします)
つまり、どちらも「自然をよく観察し、それを美しいと思ったり不思議だと思ったりする心」から始まるものだということ。
もしかしたら子どもの頃は誰もが持っているそんな心を、大人になるにつれてだんだん忘れてしまうのかもしれないですね。詩も科学もない世界は美しいのでしょうか??
・・・などということを、時々読み返して思います。
中学生の皆さんは、今持っている「好き」も「不思議」も手放してはいけない。そう思います。勉強したり、いろいろな活動をがんばったりしながら、磨きをかけていってください。
大幅に横道に逸れました。
今日は、今週火・水と二日間にわたり行った「1年生オンライン懇談会」についてお知らせしようと思います。
「各イベントや授業参観などに代わる保護者同士の交流の機会をなんとか提供できないか」という思いから、まずは、「1年生でオンラインの懇談会を試してみよう」ということになりました。
学年代表の芝原さんが、早速日にちを設定して案内の文書を作ってくださり、更に、一通一通気持ちのこもった美文字で封筒に宛名書きをして、配付をしてくださいました。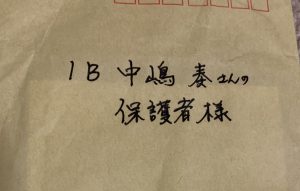
↑一通一通の美文字に愛を感じます
「夏休み前になんとかやりたい!」という思いから、開催一週間前のお知らせという特急スケジュールだったにもかかわらず、各クラスたくさんのかたが参加してくださいました。
(PTA初の試みだからというやや強引な理屈で、わたし中嶋も全クラスに参加させていただきました。ありがとうございました。)
まずは簡単な自己紹介から、さまざまな意見交換へ。
子どもたちの学校での様子や部活のこと、スマホやS N Sの利用について、また保護者同士の交流について、附中保護者の悩みNo. 1の「上履いつ持って帰ってくるの」問題についてなど・・・。
今回は無料プランでの利用だったため、40分という制限があり、あっという間に時間が過ぎてしまいました。(わたしたちがZoomの扱いに不慣れだったため、お話に夢中になり途中でブチっと切れてしまったクラスもあり、大変申し訳ありませんでした。)
その他音声や画像の接続がうまくいかないなど、個別のトラブルもあり、素早く対処ができずご迷惑をおかけした点も多々ありましたが、何より新しい試みを皆さんが面白がっていただけたことで、わたしたちもとても充実した楽しい時間を過ごすことができました。附属中の保護者の皆さんは本当にすばらしいです!
ピンクの可愛いモフモフマイクで参加してくださった方(欲しい)、お仕事中に職場から参加してくださった方、下のお子さんも一緒に参加してくださった方や、お着物で参加してくださった方など(その後驚きの事実も明らかに!)・・・、もしかしたら実際に学校でお会いするよりも、皆さんのいろいろな面を見せていただくことができたのかなとも思っています。
本当にありがとうございました。
今回はご予定が合わず参加できなかったというかたもたくさんいらっしゃると思いますので、また次回、グレードアップしての開催を狙っています!楽しみにしていてくださいね。
それから、謎のベールに包まれた「Project SHIBAHARA」について、来週あたり、ブログでお知らせすることができそうです。
今日の懇談会でチラリとお知らせできたクラスもありましたね、例のアレです。
何のこっちゃ、という皆さん、来週をお楽しみに!!
⑩ PTA活動初の「オンライン文化セミナー」に向けて
7月21日(火)
こんにちは。文化部の北村です。
早くも2回目のバトンを受け取りました。
学生時代、陸上部に所属していました。
バトン渡しはドキドキするものです。
…これは、4×100mとかじゃなくて、きっとエンドレスリレーですね!?
北村、走ります。
先日、「オンライン文化セミナー」の試作会へ、PTA役員の有志で参加してきました。
今回教えていただく先生は、主に三河地域で活動されている素敵な方です。
先生のご紹介は、後日オンライン文化セミナーの案内にてさせていただきますので、お楽しみに!
「糸かけ曼荼羅」をご存知の方、または、体験された方はどのくらいいらっしゃるでしょうか?
昨年、先生の「糸かけ曼荼羅」の作品に出会い、その魅力に引き込まれていきました。
なんと、木の板に釘を打ち込むところからはじめるのです。
ここから、もう既に無心。
普段、釘を打つことはありませんからね。
円形に打ち込まれた釘をみて、それだけで何だか心地よく・・・。
あ、ここで終わりではありませんよ。ここからが本番です。
「オンライン文化セミナー」では、2種類の糸掛けをご用意しています。
お好きな方を選んで受けていただきます。
一つ目は、「糸掛曼荼羅」。
6回に分けて糸を掛けていくと、あら不思議!
曼荼羅模様が浮かび上がってきます。
二つ目は、「渦(うず)」。
8回に分けて糸を掛けていくと、綺麗な渦模様ができあがります。
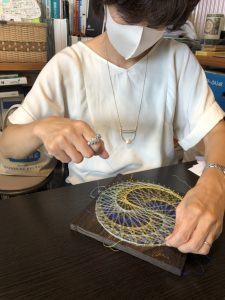
参加される方には、その規則性を体験していただけます。
糸の色選びが、これまた楽しいのです。
全て色を変えるのもよし、色の系統を合わせてシックに作るのもよし。
唯一無二の作品が生まれます。
PTA活動初の「オンライン文化セミナー」は10月開催予定です。
附属中の先生方のご協力のもと、今回のオンライン文化セミナー開催に向けて動き出すことができました。感謝申し上げます。
今だからこそチャレンジできること。
現状を前向きに捉え、私たち自身も楽しみながら準備を進めています。
保護者の皆様のご参加をお待ちしております。
(文責:文化部 北村 恭子)
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
こんにちは、中嶋です。
北村さん素敵な紹介をありがとうございました。
陸上部、似合いすぎますね。(速すぎてついていけません)。
バトンパスで追い抜かされないように、私も少し体を鍛えなおそうと思います。
糸かけ曼荼羅は、作業自体は単純な繰り返しにみえますが、なかなか奥が深いです。
もともとはドイツの教育家・思想家であるルドルフ・シュタイナーが、数学の教材として使っていたものだとか。
素数や倍数が美しい模様を作りだす様子は、とても神秘的です。
皆さんと一緒に、その感動を味わえるのを楽しみにしています。
ところで、私自身はバリバリ文系人間ですが、数学の話や、エッセイ、小説などを読むのは大好きです。
大数学者や天才と呼ばれる人がどんな世界を見ているのか、わからないけれども知りたいと思うからです。
『青の数学』(王城夕紀)という小説の中で、「なぜ数学をするのか」と問われた数学者がこう答えます。
「数学にたった一人で挑んでいるのが、たった一人ではないと知るためだ」
テスト週間に入り、勉強をがんばっている生徒の皆さんも、不安になったり、挫けそうになったりすることがあるかもしれません。
自分だけが取り残されたように感じるかもしれません。
悩みも、不安も、目指す目標も、人それぞれで違うけれど。
悩んだり、苦しんだり、挑戦したりしているのは、たった一人ではありません。
自分らしくがんばって。
・・・ブラックホールおばさんより(前回ブログ参照)。
ちなみに、私は乙女座バルゴのシャカ推しです。
(文責:中嶋 あかね)
⑨ 3年生保護者会&体育部㊙報告~3年生学年代表紹介~
7月17日(金)
皆さん、こんにちは。中嶋です。
「附中日記」で、新連載「手紙」が始まりましたね!
思わず、「そう来たか!」と唸ってしまいました。
さすがです。が、負けません。
自分の中学時代を思い返してみると、「暗黒時代」のひとことに尽きます。
「そんなに辛いことがあったのか!」というとそうではなくて、簡単に言うと「記憶がない」のです。
特に、テスト勉強のことなんて皆無。
たぶん何にも考えていなかったのか、不思議の国に住んでいたんですね。
すべてブラックホールに吸い込まれてしまいました。
・・・それに引き換え、今の附中生たちが輝いていることと言ったら!
勉強や学校行事、その他さまざまな活動に全力投球している姿は、本当に眩しいです。
あまりに全力投球すぎて、心配になってしまうほどですが。
いつも最高の、キラキラと輝いた自分でなくてもいいし、ときどきはゆっくり歩いても大丈夫だよ・・・、とブラックホールおばさんは思ってしまいますが、余計なお世話ですね。すみません。
ただひとつ、アドバイスできるとしたら、好きなものを(できるだけたくさん)見つけて、それを手放さないように、ということかなと思います。「好き」の種でもよいです。
たくさん「好き」があると人生超楽しいです。
もちろん、「勉強が好き!」も素敵です。
がんばってください。
それはさておき。
今日は、月曜日に行われた三年生保護者会について、三年生学年代表の坂田さんが紹介してくださいます。
体育部の㊙︎活動についても、ちょっとしたお知らせがあるようです。
楽しみですね。それでは坂田さん、お願いします!
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
こんにちは。
今年度、3年生の学年代表と体育部部長を務めさせていただく坂田康子と申します。
1年間、よろしくお願いいたします。
お先にどうぞと言ってる間に女性役員最後の登場になってしまいました。
前回のブログに「真打ち登場」と煽られて少々ビビっておりますが、今までの流れを壊さぬよう、ご報告させていただきます。
7月13日(月)、3年生は、評議員会、進学説明会、学年保護者会がありました。
私は早めに着いたので校長先生が駐車場整理係をしてくださっているとは知らず…。
レアなお姿、ちょっと見てみたかったです。
まず、進学説明会です。
開始時間前には育朋館に入り、静かに待っていた子供たち。さすがです。
今回は国立、私立の各高校の先生方よりお話がありました。
直接お話が聞けたことは進路選択、体験入学申し込みの参考になったのではないでしょうか。
2学期には公立高校の説明会があり、だんだん現実的になって来たように思います。(私がのんびりしてるだけかもしれません)
引き続き、学年保護者会です。
進路の事はもちろん、延期になっている修学旅行のお話など、3年部の先生方よりお話がありました。
例年どおりには始まらなかった学校生活ですが、今できることを精一杯やるべく、話し合いを重ねていると聞きました。
例年と形は違えど学校行事が滞りなく行えるとよいなと思います。
さて、翌日14日には、体育部の小部会を行いました。
今年度はスポーツ懇親会の開催ができません。
先生方と卓球やミニバレーで汗を流し、ハイタッチを交わし、その後の懇親会で飲食しながらゲームをして盛り上がる(アルコールありです!)。
なんとかあの楽しいスポ懇のような活動ができないかと話し合いました。
しかし、スポ懇は「3密」のオンパレード。
どうしたものかと話し合った結果、光が見えてきました!
一人で考えていても、よい案が思い浮かばなかったですが、やっぱり話し合いは大事ですね。
今、「運動」と「懇親」が一緒にできる楽しそうな案がまとまりつつあります。
皆さんにお伝えできるように、これからも話し合いを重ねたいと思います。
もうしばらくお待ちくださいね。
その後、前日の評議員会でお声がけした消毒作業を行いました。
私は用事があって参加出できなかったですが、ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。
制限のある日々が続きますが、今年だからこそできる活動もあるんじゃないかと思っております。生徒たちが大人になったとき、「2020年は大変だったけど、思い出深い年だった」と言ってもらえるように、先生方、PTA役員、保護者様と協力しあって活動していけたらと思っております。
改めまして、1年間よろしくお願いいたします。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
⑧ 「学級懇談会」に参加して~1年生学年代表紹介~
7月14日(火)
皆さん、こんにちは。中嶋です。
梅雨らしい日が続いています。
水害の出ている地域もあり、天気予報が気になる毎日ですね。
戸田校長先生のお便りや、昨年の厚生部学習会の内容を参考に、皆さんも十分、災害に備えてくださいね。
さて、昨日は三年生の進路説明会と保護者会が行われました。
午前中は曇りがなんとか保ちそうな予報でしたが、残念ながら朝から少し雨が降り出していました。
今回の駐車場整理係はなんと、戸田校長先生自らがお出ましに!
(心なしか嬉しそう)
ありがとうございました。
青いレインウェアが素敵でした。
いつか地球について、南極について、心ゆくまでお話を伺ってみたいと思っています。(忖度ではなく、本気です)
三年生保護者会の様子などについては、後日またお知らせするとして(真打ち登場予告)…。
今日は、またまた新メンバー登場。
一年生学年代表の芝原明恵さんが、PTAにかける熱い熱い思いを語ってくださいました。号泣必至です。それでは芝原さん、どうぞ。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
附属岡崎中の保護者の皆様、はじめまして。
1年学年代表を務めて参ります芝原明恵と申します。
どうぞ宜しくお願いいたします。
先日行われました学年保護者会では、多数の保護者の皆様にご出席いただきまして、ありがとうございました。
保護者会後の学級懇談会の様子と、そのときに感じた私の思いを少し紹介させていただきたいと思います。
限られた時間の中で行われた懇談会はとても有りがたく、貴重な時間でした。
どのクラスも、懇談会の雰囲気はよかったです。
「先生方の明るく丁寧な対応に励まされて会が和みました」という感想もいただきました。
他には、「もっと時間があると良かった!」「もっと先生や保護者の皆さんと、話がしたかった!」というご意見が多数ありました。
また、今回はご都合により欠席された保護者の方もみえますし、可能ならばZoomによるオンライン懇談会の実施ができないだろうか?という意見もいただきました。
検討してみる価値はあると思いました。
例年ですと、クラスのお食事会が実施され、楽しい時間を過ごしながら保護者同士の交流が深まるきっかけとなっていたのですが、お食事会の実施は今のところ中止となっております。(ですが状況は日々変化しておりますので、個人的には、会の実施をまだ諦めてはいません!)
附属岡崎中学校は、学区のない中学校ですので、PTA活動が保護者同士の交流を深める中心の場となると思います。
そのために試行錯誤し続けていき、
今できることは何か!
小さな事でも大きな事に繋がるかもしれない!
まずはトライしてみよう!
という前向き思考で、コロナを寄せつけないようにしよう!!!
・・・すみません。
だんだん熱くなってしまいました。
これは、中嶋副会長をはじめ先輩役員の皆様が本当に素敵で、熱い想いが日々あふれているかたばかりで、それが私にも伝染しているからだと思います。
「スタートからコロナ禍で臨時休業になり、不安な気持ちが大きいのは一年生ではないか?」と、どの学年よりも一年生保護者の事をまず心配してくださいます。
また、子どもたちが、後輩たちを思いやる気持ちと同じように、「何かできることはないか」と常に考えてくださっています。
「私にできることは何でもやります」精神でがんばります!
ですが、私一人の力では微力すぎるので、各クラスの評議員の皆様が中心となり保護者の皆様にもお力添えをいただきまして、これからも、熱い熱い気持ちを胸に活動ができたらいいと思っています。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
⑦ 「消毒作業」を体験して ~2年生学年代表紹介~
7月10日(金)
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
初めまして。
今年度、2年生の学年代表を務めさせていただく大河内と申します。
一年間よろしくお願いいたします。
さて、今回、突然の私の登場ですが、副会長中嶋さんよりご指名を受け、既に保護者会や学級懇談会、消毒作業の様子もこのブログで伝えられている中、特筆することもなく(泣)、お任せと言われても……。
そこで、私が先日二度参加しました「消毒作業」で発見したことを、三つ書かせていただきます。
まず、一つ目は、各クラスの教室に飾られている色紙です。
皆さん、子どもたちがこの色紙に「一年の抱負」を自由に書いていることをご存じでしたか?
私は4年目にして、初めて知りました(ごめんなさい…)。
どれも目を引く言葉、字、デザインで、とても興味をひかれました。
二つ目は、図書室の本の充実さ!
偶然にも私の読みたかった『スラムダンク』の英語版を発見。
さっそく我が子に借りてきてもらい、ただ、「明日には返すから」と言われ…、「せめて明後日に」と交渉し、一晩、英語の勉強をしてみました。
三つ目は、特別な日ではない何気ない日常の子どもたちの学校生活を垣間見ることができたことです。
どの子どもも楽しそうに笑顔で過ごしている姿をうれしく感じました。
学校に足を運んだおかげで、今まで知らずに過ごしていたことを知ることができました。
こういった機会をもらえたことを感謝しております。
来週は、体育部の小部会があります。
どんな発見があるのか楽しみにしております。
(文責:大河内 彩)
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
突然ですが、中嶋です。
今回は、二年生学年代表の大河内さんに登場していただきました。
ありがとうございました。
強引にお願いしてしまってごめんなさい。
あ、パワハラではありませんよ。
なかよく活動していますので、ご家族の皆さん、ご安心くださいね。
ただ、私はPTAの活動について、そして活動している役員について、保護者の皆さんにも知っておいていただきたいと思っているのです。
「PTA」=「どこの誰ともわからない物好きな人たちが集まって何かやっているところ」ではなく、皆さんと同じ、普通の保護者が、ああでもないこうでもないと、知恵をしぼりつつがんばっているところなのだな、と。
そして、皆さんも一緒に考え、参加して、楽しんでいただけたらさらに嬉しく思います。
もちろん、厳しいご意見にも謙虚に耳を傾けます。
メンバー紹介、まだまだ続きますので、お楽しみに…。
(文責:中嶋 あかね)
⑥ 2年生学年保護者会&文化部紹介<後編>
<⑤の「前編」を読んでないかたは先にそちらをどうぞ>
附属中保護者の皆様、初めまして。
今年度、PTA文化部を担当させていただく北村恭子と申します。
「『食卓シリーズ』のような人気コンテンツを目指して…」との中嶋副会長のお言葉にプレッシャーを感じつつ、渡されたバトンを落とさないよう、がんばっていきたいと思います。
7月6日(月)、2年生評議員会・保護者会・学級懇談会が開催されました。
新しいクラスの保護者の方々との初顔合わせ、久々の再会…。
マスクの下の表情を読み取ることは、なかなか難しいものですが、皆様の明るい雰囲気に懐かしい日常が一時戻ったような気がして嬉しくなりました。
学級懇談会後は、先日の1年生評議員の皆様と同様に、ご都合のつく2年評議員の方々がPC室と教室の消毒をお手伝いしてくださいました。
ありがとうございました。
では、話を文化部に戻して…。
今年度は、例年通りのイベント開催が困難であることから、「従来の文化セミナーに代わるものはないか」、「この状況下、無理前提より、どうすればできるか」を考えました。
そこで、子ども達が休校中にオンライン授業に柔軟に対応していたことを見習って、「オンラインPTA文化セミナー」の企画に至りました。
ZOOMを使用し、「糸かけ曼荼羅」の講座開催に向けて現在動いております。
糸かけ曼荼羅とは…
木製の板にピン(釘)を打ってピンに糸を掛けてつくります。
ある規則性を元に糸を掛けていくと、曼荼羅模様ができあがります。
ピンを糸に掛けるので「糸かけ曼荼羅」です。


↑セミナーで作るものとは違いますが、参考までに。
「オンライン文化セミナー」については、8月頃に案内配布、10月上旬セミナー開催予定です。
PTAとして初めての試みです。
どうなるのか??と一抹の不安しか感じませんが、伊倉剛先生「名言集」から引用させていただき…、
「TRY & ERROR」(名言⑥)「どんどんチャレンジ!」(名言⑦)
して、保護者の皆様とともに新しいものを作り出せる機会になれば、と考えています。
どうぞよろしくお願いいたします。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
北村さん、ありがとうございました。
再び、中嶋です。伊倉先生名言集、実に気になります。(そこ?)
「あれもこれもできない」「無理」と考えて落ち込んでいるときは、とても実現しそうにないように見えたことが、少し動き出してみると、実現できるかどうかは関係なく、たちまち、「あれもこれもやりたい!」と楽しみにかわるんだなと思っている今日この頃です。
みなさんもいっしょに、面白がってくださいね。
—考えること、悩むことが大事なのは、そうすれば問題を解決できるからではない。~そうではなく、考え悩みながら問題を引き受け、その時々に右往左往しつつさらに考え悩むとき、私たちは自分自身の苦労を担い、自分自身の生き方を取り戻すことになるからだ。—(『治したくない』斎藤道雄 より)
⑤ 2年生学年保護者会&文化部紹介<前編>
7月7日(火)
–答をえるために考えるのではない。答がないからこそ、ではどうすればいいかを考えるのだ。– (『治したくない』斎藤道雄 より)
ちょうど読んでいた本にこんな一節が出てきたので、つい引用してしまいました。
いつでもそのときどきに、大切な言葉は向こうからやってくるものだなと思います。どこかにたったひとつの正しい答えがあるとしたら、それ以外は全部間違いということになってしまいますが、誰も正解を知らないならば、間違いも失敗もないし、悩んで、考えて、トライすることそのものに意味や価値があるのかなあと思っています。
それに、もし正しい答えがあったとしても、寄り道したり遠回りしたり、迷ったりするのはちょっと面白い。いろんなことを面白がる。それって附中スタイルかも。と、考えた雨の日でした。
早速寄り道しながらのスタートですが、皆さん、こんにちは。中嶋です。
昨日は二年生の学年保護者会が行われました。
朝から雨が降り続いていたので、正直「行きたくないな」とちょっと思ってしまったのですが(本当にごめんなさい)、グラウンドに入ると、てるてる坊主のような青いポンチョ&半パンを着た馬場先生が、いつもと変わらぬ春の日差しのような笑顔で迎えてくださったので、自分のわがままを猛烈に反省したのでした。
先生方、悪天候のなか車の誘導をしてくださり、ありがとうございました。
私は評議員会で少しご挨拶させていただき、その後は学年代表の大河内さんと文化部長の北村さんにお任せして失礼してしまいましたが、今回も二年生評議員の皆さんにお声をかけ、授業後の消毒作業をお手伝いいただきました。

急なお願いだったのにもかかわらず、また多数の方に参加していただいたと伺っております。本当にありがとうございました。
さて、今日は文化部の活動についてお知らせしようと思います。
部員さんはいませんが、文化部長の北村さんを中心に、みんなで着々と準備を進めています。
今年度は、10月の上旬に、なんと附中初の「オンラインPTA文化セミナー」を予定しています!
なんだか、すごそうですよね、カッコよくないですか。
「ウチのPTAの講習会、オンラインなんだよね~」とぜひ、自慢しちゃってください。
では、文化部長の北村さんにバトンタッチ。
<後編へつづく>
④ 1年生学年保護者会
7月3日(金)
皆さんこんにちは。
附中日記の「食卓シリーズ」終了が寂しいです。
今年は、楽しみにしていた「給食試食会がない」とのことで、バーチャル給食を楽しませていただいていたので、とても残念で涙が止まらないです。
あのような人気コンテンツを目指してがんばりたいと思います。
さて、今回は7/1(水)に行われた一年生の理事評議員会、学年保護者会の様子と、その後の消毒作業についてお知らせしたいと思います。
前日深夜まで激しい雨が降っていたので、このまま雨が降り続いていたらグラウンドが田んぼ化してしまうなあ・・・と思って心配していたところ、奇跡のように午後から天気が好転したのでした。
きっと、皆さんの日頃の善行のおかげですね。
保護者会の少し前、図書室に各クラスから選ばれた評議員の皆様に集まっていただき、活動の現状、今後の予定などについてお話しさせていただきました。
前回のブログでお伝えした「消毒作業」のこと、二学期以降オンラインでの開催を予定・企画している「文化セミナー」のこと、「コーラスクラブ」、「Pネット」への登録のお願いについてなど。
いろいろお伝えしなければならないことがありすぎて、予定時間をオーバーしてしまい、大変ご迷惑をおかけしました。
その後、育朋館で行われた学年保護者会の中でも同様のご案内をさせていただきました。(手作りマスクをしていたのですが、効果を高めようと生地を何枚も重ねて作ったため、酸欠気味になり、頭が朦朧としてしまいました。皆さまにきちんと内容が伝えられたか若干不安です。)
そんな私の拙い挨拶のあと、子どもたちが各クラスの級訓を紹介してくれたのですが、そのプレゼンが素晴らしすぎて度肝を抜かれてしまいました。(その前の自分の挨拶が恥ずかしくなりました。)
朦朧としていた意識もシャキッとしました。
少ない時間の中でも議論を尽くしてできあがったのであろう級訓はどのクラスも素晴らしいものでした。
今回は壇上に上がっていなかったみんなの気持ちも、採用されなかった案も、一緒に伝わってきました。
この級訓を胸に、一年がんばってくれることと思います。
時間が大幅に押して保護者会は終了(私のせいのような気がします、反省しています)し、場所を移動して各クラスの懇談会へ。
入学式の後、初めて先生やクラスの保護者の皆さんとマスク越しではありますが顔を合わせてお話をすることができました。
コロナ禍に対する不安や心配はもちろん、中学校生活について、学習面や反抗期、思春期のことについてなど、親の悩みはつきませんよね。
こういう場で少しでも繋がりができ、気軽に相談したり、意見を交換したりできたらとてもいいなと思いました。
今回は簡単な自己紹介で時間切れとなってしまいましたが、今後、オンラインなどで懇談会ができないか、という意見も出ました。私たちPTAでも、積極的にそのような場を提供したいと考えています。(あ、「ちょっと考える」だけではなく「やり始める」ことが大事ですね!森先生!)
子どもたちの下校時間に合わせて懇談会も終了し、そのあと消毒の作業に入りましたが、今回は突然、評議員の皆さんにもお声をかけて、一緒にお手伝いしていただきました。
当日の呼びかけであったにもかかわらず、たくさんの方に参加していただきとても助かりました。



パソコン室、図書室、教科棟の理科室をまわって(理科室の亀さんを見たりしながら)、一年生の教室へ。
先ほどの級訓を黒板上に掲げているクラスもありました。教室に飾ると、さらに立派に見えます。誇らしいですね。
後ろに掲示してある、ひとりひとりの思いを記した色紙にも、どことなくクラスの特色が現れているようで面白いなあと思いました。
あ、もちろん消毒はきちんとしましたよ。
今回はたくさんの方が手伝ってくださったので、さっさと終わりました。ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。
またこのような機会がありましたらお声がけさせていただきたいと思います。
来週は、2年生の学年保護者会、再来週は2年生の進路説明会・学年保護者会が続きます。
更に蒸し暑くなりそうなので、皆様も体調に気をつけて、元気に夏を迎えましょう。
(文責:中嶋 あかね)
③ 校内消毒作業ボランティアについて
6月30日(火)
皆さまこんにちは。
雨が降っても降らなくても、蒸し暑い日が続いていますね。
マスク焼け・マスクかぶれ・熱中症などに、十分気をつけないといけませんね。
そんな中、連日の更新が暑苦しくてすみません。
今日は、昨日のブログにもご紹介した、「校内消毒作業ボランティア」についてお伝えしたいと思います。
現在、附属岡崎中学校では、感染予防のため、生徒が使う教室や教材、トイレや教科教室などの共用のスペースの消毒を一日一回は必ずしているそうです。
生徒たちが帰った後、先生方は、教室の机や椅子、共用のスイッチや手すり、窓枠などを中心にアルコール除菌スプレーをかけ、拭き取ります。
難しい作業ではありませんが、先生方だけで「全ての教室を毎日」となると、かなり時間もかかりますし、大変です。
そこで、保護者の皆さまのお力を借りて、「先生方のご負担を減らすことができないだろうか」、「ボランティアを募ってはどうだろうか」という案が役員会で出たのでした。
実際のところ、皆さまにお願いするとなったらどのようなやり方がいいのか、まずはやってみないとわからないので、「とにかく役員でお試しに行ってみよう!」ということになりました。
そして、先々週から、週2回くらいのペースで、そのとき時間に都合のつく役員でペアになり、お手伝いさせていただいています。
一日にだいたいワンフロア(各学年の教室プラス、パソコン室、図書室など)を受け持ち、20分くらいで終わります。

個人的な感想ですが、各クラスを回りながら掲示物をチラ見できたり、帰り際の生徒さんが気持ちよい挨拶をしてくれたりするのは、お釣りがくるくらいの役得ですし、先日は、今年度始まったばかりの部活動の様子を見学させていただくことができて、とても嬉しく思いました。(我が子は部活に入っていませんが)
マスクの着用やこまめな手指の消毒・換気などについては、子どもたちが自主的に心がけているように感じました。(教室に入るとき「このアルコールスプレーで、手を消毒してくださいね!」と私に声をかけてくれた子がいました)
従来とは違う制約のある生活スタイルの中で、どのように「やりたいこと」を「できること」にしていくのか、ということを、附中の子達はごく自然に、考えて実行しているのではないかと思いました。
とても素敵です。
また、モリモリ書店店長(森教頭先生)にご指示いただくからなのか、だいたい最後に図書室の消毒がセットになっていて、個人的にはそれが楽しみです。

あえてゆっくり机を拭いたり、要らない二度拭きしたりしつつ、棚の本を横目で見ています。本棚を見るのは楽しいですね。ついつい並べ替えたくなったりしますが。
全然消毒と関係ない話になってしまいました。
次回は、今後の活動予定などについてお知らせできたらと思います。
(PTA副会長 中嶋 あかね)
② 今できることは何か
6月29日(月)
附属中学校の保護者の皆さま、こんにちは。
今年度、PTA副会長を務めさせていただきます、中嶋と申します。
上級生の保護者の皆さんはご存知かと思いますが、例年ならば今頃ちょうど、文化部主催の「文化セミナー」、体育部主催の「スポーツ懇親会」が開催されている時期です。
いつもどおりであれば、評議員の皆様にお力を貸していただいたり、保護者の皆様にはイベントを楽しんでいただいたりして、楽しい時間を過ごしていたところでした。(本当ならば今日は代休でお弁当もなかった!)
しかし、現状、大人数で集まっての講習会や懇親会は、まさしく避けなければならない「三密」であり、残念ながら各イベントは延期・中止を余儀なくさせていただいております。
そこで、生徒たちの安全な学校生活の確保が最優先である今、例年どおりのPTA活動はできないと考え、「今できることは何か」という視点から、6月上旬、役員一同で今年度の活動方針を話し合いました。
○今年は、例年の活動にはとらわれないこと
○子どもたちや学校の活動を最優先に考え、サポートしていくこと
○その上で保護者の皆さんの不安や心配事についてもできる限りサポートすること
○オープンに意見交流や情報交換できる場を提供すること
○今できることをやること
○今しかできないことも試してみること
このようなことを活動の軸にしながらスタートしていこうと思っています。
(役員会の中で、今すぐにできそうな活動の一つとして挙がったのが、「校内の消毒・清掃作業のお手伝いボランティア」です。これについては、先々週より役員で少しお試しをさせていただいています。実際の様子については改めてレポートしますね。)
不安だらけですが、不安100%でもなく、少し?いや結構なワクワクも抱いております。私だけかもしれませんが。
そんなこんなで、かなり危なっかしくではありますが、「まずはやってみる」精神で始めていきます。皆様のご意見、ご助言、ご協力、いつでもお待ちしております。よろしくお願いいたします。
突然ですが、ミヒャエル・エンデの『モモ』より、最近特によく考えている言葉を引用します。
「時間とはすなわち生活なのです。そして生活とは、人間の心の中にあるものなのです。」
本当なら、例年どおりなら、ああだったのに・・・と、なかった過去を惜しんだり、そのうちいつも通りになることを信じて何もしないで待つことは、いまを生きていない、そんなふうに言われている気がします。
豊かに生きたいなあと思います。弁当は辛かったですが。
(PTA副会長 中嶋 あかね)
① <会長あいさつ> 令和2年度、PTA活動へのご協力お願いいたします。
6月29日(月)
令和2年度PTA会長を務めさせていただきます、齋藤と申します。
新型コロナウィルスの影響で、例年とは異なる学校生活を余儀なくされています。
保護者の皆様は学校へ行く機会も少なく、PTAの行事も現状行われていないため、様々な情報が不足していることと思います。
このような状況の中、PTAの活動を少しでもお伝えしたく、ブログを始めてみます。
このブログをとおして、現在の様子が皆様に伝われば、嬉しく思います。
今年のPTA活動は例年と違う動きになるかもしれません。
コロナウィルスの影響の中、子供たちが安心安全な学校生活をおくることができるよう活動していきたいと思いますので、よろしくお願い致します。
(PTA会長 齋藤 登)